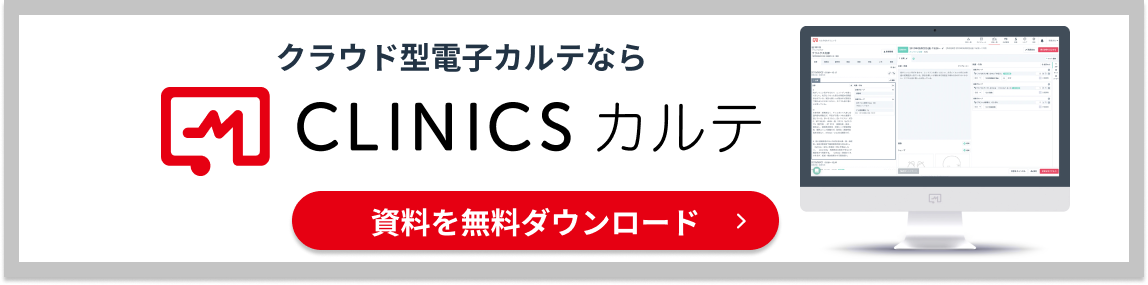Web問診システム19選を紹介!メリットから選び方まで詳しく解説
「Web問診を導入するメリットを知りたい」
「具体的にどんな問診システムがあるのか知りたい」
クリニック経営者のなかには、上記のような疑問を抱えている方も少なくありません。
Web問診の導入により、クリニックスタッフの業務負担を軽減できます。しかし、どのような基準で選べばよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
当記事では、Web問診の概要や導入するメリットのほか、導入する際の注意点などを詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.Web問診とは
- 2.Web問診システムを導入する3つのメリット
- 2.1.1.受付スタッフの負担が軽減する
- 2.2.2.患者の来院前に問診表を確認できる
- 2.3.3.患者の待ち時間が減少する
- 3.Web問診システムを導入する際の3つの注意点
- 3.1.1.スタッフと運用方法を相談する
- 3.2.2.費用を確認する
- 3.3.3.サイトの改修が必要か確認する
- 4.Web問診システムのタイプ
- 4.1.Web問診特化タイプ
- 4.2.クリニック業務全般支援タイプ
- 4.3.健康診断・人間ドック向けタイプ
- 5.Web問診システムを比較する際のポイント
- 5.1.問診票の設問を柔軟に設計できるか
- 5.2.マーケティング機能
- 5.3.電子カルテと連携できるか
- 5.4.AI問診
- 6.Web問診システムの選び方
- 6.1.カルテ・予約システムとスムーズな連携ができるか
- 6.2.自院の雰囲気にマッチしたUIか
- 6.3.求めている問診の運用を満たすかどうか
- 7.おすすめのWeb問診システム【Web問診特化タイプ】
- 7.1.1.CLINICS問診(株式会社メドレー)
- 7.2.2.メルプweb問診(株式会社HERO innovation)
- 7.3.3.SymView(株式会社レイヤード)
- 7.4.4.AI問診UBie(Ubie(ユビー)株式会社)
- 7.5.5.imon(アイ・ティ・エス株式会社)
- 7.6.6.Ace(株式会社ARS(アルス))
- 7.7.7.Dr.TAP(株式会社福島情報処理センター)
- 7.8.8.問診票入力システム(トップオフィスシステム株式会社)
- 7.9.9.Mac24-Tab(株式会社マクロスジャパン)
- 7.10.10.Myclinic問診票(エンパワーヘルスケア株式会社)
- 7.11.11.MedicalTQ(株式会社ユー・アイ・エス)
- 7.12.12.Confy(アイテック阪急阪神株式会社)
- 7.13.13.wellnessMonsin(株式会社アドバンスブレイン)
- 8.おすすめのWeb問診システム【クリニック業務全般支援タイプ】
- 9.おすすめのWeb問診システム【健康診断・人間ドック向けタイプ】
- 10.まとめ
Web問診とは

Web問診とは、スマートフォンやタブレットなどを利用して入力できる問診システムです。Web問診は病院やクリニックに来院する前でも、インターネットがあれば場所を問わず入力できます。
それでは、紙問診とAI問診との違いについて詳しく紹介します。
紙問診との違い
紙問診とは、みなさんがご存知の紙の問診表です。紙問診は患者が病院やクリニックに来院してから記入するのが一般的です。患者が来院してから記入するため時間がかかりやすく、カルテへの転記やスキャン、廃棄作業が手間になる場合もあります。
一方で、Web問診は場所を問わず入力できたり、カルテと連携している場合、そのままカルテに自動で転記されます。
AI問診との違い
AI問診は、患者の入力内容に合わせて疑われる症状や病気を推測できるのが特徴です。症状や病気を推測できる質問が細かいため、患者の症状を見落とすリスクを軽減できます。
一方、Web問診は事前に設定した設問に対して患者が入力する流れのため、入力内容をもとに医師が病気や症状を考えるのが一般的です。AI問診のほうが、患者の症状や病気を見落とさず、適切に診断できる可能性があります。
Web問診システムを導入する3つのメリット

Web問診システムを導入するメリットは、以下の3つです。
- 受付スタッフの負担が軽減する
- 患者の来院前に問診表を確認できる
- 患者の待ち時間が減少する
それぞれ詳しく紹介します。
関連記事:WEB問診とは?導入のメリットとシステムの選び方について解説します/Web問診導入時のクリニックのデメリットとは?導入時の注意点も徹底解説します!
1.受付スタッフの負担が軽減する
Web問診システムを導入すると、受付スタッフの業務負担を軽減できるのがメリットです。受付スタッフは、患者の問診票の受け渡しだけでなく、電話対応やデータ入力など、多くの業務を担当しています。
Web問診システムを導入すると、患者が自宅や出先から直接自分の情報や症状をオンラインで入力します。さらに、電子カルテと連携している場合、電子カルテに自動で転記されます。その結果、スタッフの紙問診の受け渡し、スキャン、電子カルテへの転記、廃棄等の作業を削減できます。
2.患者の来院前に問診表を確認できる
患者の来院前に問診表を確認できるのが、Web問診システムを導入するメリットです。患者が来院する前に、オンラインでの問診が完了していると、医師や看護師は患者の問診内容を事前に確認できます。
その結果、診療の効率が向上し、より詳細なカウンセリングや治療計画の策定が可能になります。また、発熱外来のトリアージや急を要する患者への迅速な対応が可能な点もメリットです。
3.患者の待ち時間が減少する
Web問診システムを導入すると、患者の待ち時間が減少するのは大きなメリットです。従来の問診方法では、患者は病院に到着してから問診票を記入する必要がありました。
しかし、Web問診システムを導入すると、患者は自宅や移動中など事前に問診の入力が完結できるようになります。病院に到着した際の待ち時間が大幅に短縮され、患者のストレスも減らせる効果が期待できます。
Web問診システムを導入する際の3つの注意点

Web問診システムを導入する際の注意点は、以下の3つです。
- スタッフと運用方法を相談する
- 費用を確認する
- サイトの改修が必要か確認する
それぞれ詳しく紹介します。
1.スタッフと運用方法を相談する
Web問診システムを導入する際は、どのような運用をするのかをスタッフと相談して詰めておく必要があります。特に受付スタッフとは、どのような流れだと業務が進めやすいのかをシミュレーションしながら進めると、導入後の対応がスムーズです。
2.費用を確認する
Web問診システムの導入には、初期費用だけでなく月額費用もかかるケースがほとんどです。
具体的な費用を明確にし、予算を超えない程度に機能や利用範囲を抑える配慮が必要です。システムによって費用はさまざまなため、予算を超えないシステムの選定と、運用後の費用を把握し、検討を進めるようにしてください。
3.サイトの改修が必要か確認する
Web問診システムを導入する際は、サイトの改修が必要かどうか確認しましょう。Web問診システムの導入によって、既存のWebサイトにボタンを設けたり、ページの変遷を変えたりと影響が出る可能性もあります。
システムによっては、サイトの構造やデザインの変更を要する場合があるため、前もって改修の必要性をチェックしておくとスムーズに導入できます。
Web問診システムのタイプ

Web問診システムは、医療機関のニーズに応じてさまざまなタイプが提供されています。主に「Web問診特化タイプ」「クリニック業務全般支援タイプ」「健康診断・人間ドック向けタイプ」の3つに分類されます。ここではそれぞれの特徴を解説します。
Web問診特化タイプ
Web問診特化タイプは問診業務のデジタル化に特化しており、紙の問診票を電子化することで医療スタッフの業務負担を軽減します。患者は自分のスマホやタブレットで問診票を記入でき、記入内容は自動的に電子カルテと連携されるため、転記ミスの防止や業務効率の向上が期待できます。
Web問診特化タイプの主なメリットは、導入や運用が比較的容易であり、既存の業務フローに大きな変更を加えることなく導入できる点です。
一方で、問診以外の機能は限定的であることが多いです。予約管理や検査結果の管理など、ほかの業務支援機能を必要とする場合は、別途システムの導入を検討しなければならない場合もあるでしょう。
クリニック業務全般支援タイプ
クリニック業務全般支援タイプは、問診業務に加えて、予約管理や受付、電子カルテ、会計など、クリニックの業務全般をサポートする多機能なシステムです。一つのシステムで複数の業務を管理できるため、情報の一元化や業務効率の向上が期待できます。
クリニック業務全般支援タイプのメリットは、情報の一元管理が可能な点です。患者の予約から問診、診療、会計までの流れをシームレスに管理でき、スタッフ間の情報共有も容易になります。患者にとっても、予約や問診、検査結果の確認などをオンラインで行えるため、利便性が向上します。
一方で、システムが多機能である分、導入や運用に際しての初期設定やスタッフのトレーニングが必要です。また、コストも高くなる傾向にあります。
健康診断・人間ドック向けタイプ
健康診断・人間ドック向けタイプは、健康診断や人間ドックに特化した機能を備えています。大量の受診者のデータ管理や問診票の効率的な収集・管理にも役立ちます。
健康診断・人間ドック向けタイプのメリットは、大量の受診者データを効率的に管理できる点です。問診内容のエラーチェックや入力漏れの確認が自動化されるため、スタッフの負担が軽減されます。受診者にとっても、事前に問診票を入力することで、当日の待ち時間が短縮され、スムーズな受診が可能です。
一方で、健康診断や人間ドックに特化しているため、一般外来の診療業務には適さない場合があります。
Web問診システムを比較する際のポイント

Web問診システムには数多くのサービスがあります。自院に適したシステムを選ぶには、サービスを比較検討することが大切です。ここでは、Web問診システムを選定する際のポイントについて詳しく解説します。
問診票の設問を柔軟に設計できるか
問診票の設問を自由に設計できるかどうかは、Web問診システムを選ぶうえで重要なポイントです。医療機関ごとに診療内容や患者層が異なるためです。例えば、小児科ではワクチン接種歴、整形外科では過去の外傷歴や生活習慣など、科目ごとに必要な情報は異なります。
問診の流れを患者の回答に応じて分岐させる機能が便利です。例えば、初診と再診で問診内容を変えたり、特定の疾患が疑われる場合に追加の質問を自動で表示したりする仕組みがあると、より効率的な問診が可能です。
マーケティング機能
Web問診システムは単なる事前問診のツールとしてだけでなく、マーケティングの観点からも活用できる場合があります。特に、集患を強化したい医療機関にとって、マーケティング機能が充実しているかどうかは重要な要素です。
例えば、Web問診完了後にLINE公式アカウントの登録を促す機能があると、再診のリマインドや健康情報の配信が容易です。また、予約システムと連携して次回診察の案内を自動送信できる機能があると、患者のリピート率を高めることができます。
電子カルテと連携できるか
Web問診システムが電子カルテと連携できるかどうかも大切です。電子カルテと連携していないと、問診データを手入力する手間が増え、スタッフの負担が大きくなるだけでなく、入力ミスのリスクも高まります。
電子カルテと自動連携できるシステムを導入すると、患者が記入した問診情報をそのままカルテに反映できるため、業務の効率化が図れます。特に、クラウド型のシステムはリアルタイムで問診データが電子カルテに取り込まれるため、診察の準備がスムーズです。
AI問診
AI問診のメリットは、患者の症状に応じて適切な質問を自動で生成し、医師が診察する前に必要な情報を的確に収集できる点です。例えば、患者が入力した症状や既往歴に基づいて、質問を自動生成し、詳細な情報を収集することができます。
また、AIが収集したデータを分析し、疾患を推定する機能があれば、診断の精度向上にも役立つでしょう。さらに、言語解析技術を活用することで、患者の表現を医療用語に変換し、医師が理解しやすい形で情報を提供することも可能です。
Web問診システムの選び方
Web問診システムの選び方は、以下のとおりです。
- カルテとスムーズな連携ができるか
- 自院の雰囲気にマッチしたUIか
- 求めている問診の運用を満たすかどうか
カルテ・予約システムとスムーズな連携ができるか
Web問診システムを選ぶ際には、カルテと予約システムとスムーズな連携ができるかが重要です。まず、電子カルテについては、Web問診のデータが患者のカルテに迅速に反映されることが理想です。そのため、クリニックで使用している電子カルテとスムーズに連携できるかが、比較・検討の肝になります。
次に、予約システムについては、Web予約が完了したあとにWeb問診の回答に誘導できる連携が理想的な運用です。患者がWeb予約後にWeb問診に回答することで、漏れなくWeb問診に回答いただくことができます。
システム選びの際には、データ連携の方法やカルテとの情報の同期頻度など、技術的な側面についても詳しく確認してください。同じカルテを使っている、他施設にヒアリングするのも有効な手段です。
自院の雰囲気にマッチしたUIか
Web問診システムを選ぶ際は、自院の雰囲気にマッチしたUIかを確認してください。UIとは「ユーザーインターフェース」の略称で、Webサービスやアプリケーションなどにおいてユーザーの目にふれるすべてのものを指します。
UIは、患者やスタッフが感じる使いやすさや操作性に大きく影響します。そのため、クリニックの雰囲気や患者層に合った、シンプルで分かりやすいUIが求められます。
導入する前にデモ版を実際に操作して、初めてでも迷わずに操作ができるか、デザインが自院のイメージに適しているかなどを確認してください。
求めている問診の運用を満たすかどうか
求めている問診の運用を満たすかどうかで、Web問診システムを選ばなければなりません。医療機関ごとに、求める問診の内容や運用方法は異なります。たとえば、初診時の詳細な問診から再診時の簡易な問診まで、多岐にわたるニーズが考えられます。
導入するシステムが上記の要件を満たしているかの確認が、導入後の満足度に影響を与えるため、非常に大切です。
おすすめのWeb問診システム【Web問診特化タイプ】
おすすめのWeb問診特化タイプシステムは、以下の13選です。
- CLINICS問診
- メルプweb問診
- SymView
- AI問診UBie
- imon
- Ace
- Dr.TAP
- 問診票入力システム
- Mac24-Tab
- Myclinic問診票
- MedicalTQ
- Confy
- wellnessMonsin
それぞれ詳しく紹介します。
1.CLINICS問診(株式会社メドレー)
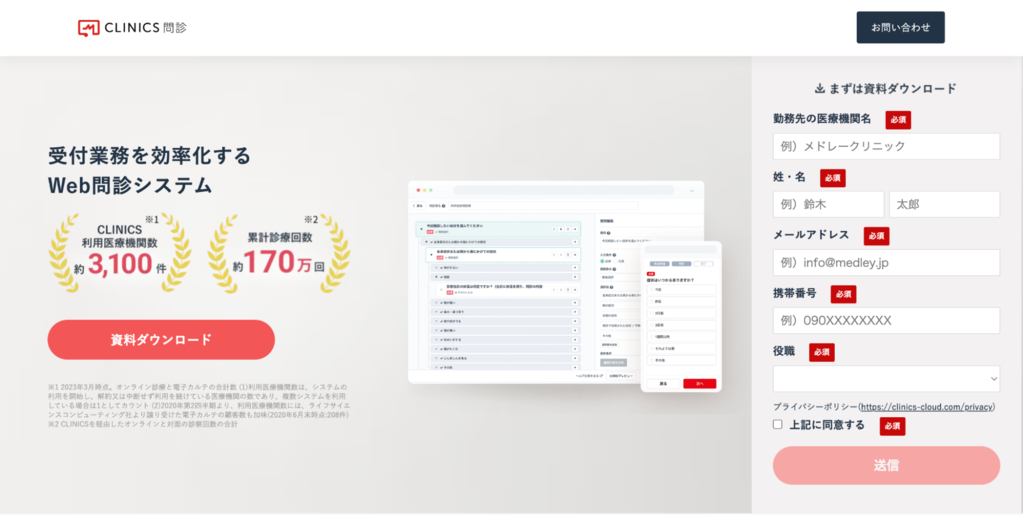
参考:CLINICS問診
CLINICS問診は、クラウド型電子カルテ「CLINICSカルテ」に搭載されているWeb問診機能です。CLINICSカルテとの連携により、転記作業を軽減でき受付スタッフの業務負担を軽減できます。
患者は、自分の都合のよい時間にWeb問診を受けたうえで来院できるため、来院後の混雑解消に効果を発揮します。
2.メルプweb問診(株式会社HERO innovation)

参考:メルプweb問診
メルプweb問診は、カスタマイズ性の高さやチャット形式の画面デザインなどが特徴です。医師と対話形式で問診回答するデザインにより、初診患者でも迷わずに入力ができます。
また、クリニックの特徴や雰囲気に合わせて、使いやすいシステムにカスタマイズが可能です。医師好みに柔軟にカスタマイズできるので、医療現場におすすめのWeb問診システムです。
3.SymView(株式会社レイヤード)

参考:SymView
SymViewの導入により、かかりつけ医と患者の関係を良好にできます。電子カルテや予約システム、オンライン診療システムなど周辺システムとのスムーズな連携が可能です。
来院前に詳細な症状を確認できるため、適切な医療を提供できるようになります。受付スタッフの業務負担の軽減だけでなく、患者や他施設との関係を良好にしたいクリニックにおすすめです。
関連記事:symview(シムビュー)とは?評判・口コミ・料金を解説!
4.AI問診UBie(Ubie(ユビー)株式会社)

参考:AI問診UBie
AI問診UBieの導入により、クリニック内の業務効率を軽減できます。ユビーAI問診やユビーリンクなど充実した機能が導入されており、診療の効率化や充実化を同時に実現可能です。
症状をチェックした患者とクリニックとのマッチングも支援しており、適切な受診を実現しています。患者の診療の質を向上させたいクリニックにおすすめのサービスです。
5.imon(アイ・ティ・エス株式会社)

参考:imon
imonは、クラウド対応のタブレット問診入力システムです。imonには問診票入力機能や問診票確認機能など、充実した機能が搭載されています。
また、患者の院内滞在時間の短縮を目的とした設計されたシステムでもあります。医事会計システムとの連携や、転記作業の負担が軽減される工夫が施されており、スタッフの負担軽減にも役立つでしょう。
関連記事:i monとは?特徴・機能・料金を解説!
6.Ace(株式会社ARS(アルス))

参考:Ace
Aceは、患者に適したさまざまなテンプレートを選択できるのが特徴です。外来受診の初診問診に利用でき、診療に必要な複数のプロセスを一気にシステム化できます。
また、紹介病院からの簡易的な患者紹介として、安全にWeb情報の送信も可能です。患者に合わせた質問設定や、問診テンプレート登録など充実した機能を利用できます。
7.Dr.TAP(株式会社福島情報処理センター)

参考:Dr.TAP
Dr.TAPは、予防注射の管理やさまざまなシステム連携に対応しているWeb問診システムです。
たとえば、Dr.TAPの予防接種管理システムは、接種予定アシスト機能がついており、予防接種のスケジュール管理の手間が省けます。そのほか、独自の問診票や予約受付機能などの機能も搭載されており、業務の効率化に役立つシステムといえます。
関連記事:Dr.TAP(ドクタータップ)とは?口コミ・機能・料金を解説!
8.問診票入力システム(トップオフィスシステム株式会社)

参考:問診票入力システム
問診票入力システムは、患者の診察前にiPadで簡単に入力できるシステムです。事前に患者に問診表を入力してもらうことにより、症状に合わせた適切な治療を提供できるようになります。
ほかにも、問診対応者の署名機能や患者情報の取り込みなど、充実した機能が搭載されています。レセコンやカルテとも連携できるため、業務の効率化を実現可能です。なお、電子カルテとの連携については、ベンダーに確認が必要な点は忘れないようにしましょう。
関連記事:問診票入力システムとは?口コミ・機能・料金を解説!
9.Mac24-Tab(株式会社マクロスジャパン)
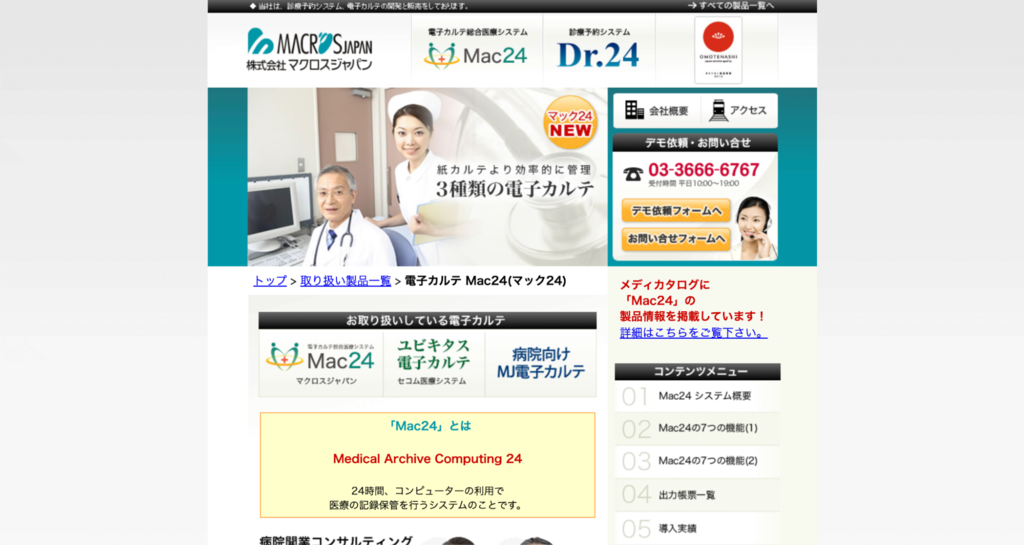
参考:Mac24-Tab
Mac24-Tabは、外部の医療機関から送られてきたレントゲンフィルムや検査結果など、患者の情報を一元的に管理が可能です。また、Mac24-Tabに登録されている用語などは、厚生労働省が提供する基本マスターをダウンロードして管理するため、今後の標準化の流れにも対応しています。
豊富なオプションが用意されており、ニーズにあわせて利用可能です。自院に合っているオプションを利用して、業務を効率化したいクリニックに向いたシステムといえます。
関連記事:「Mac24-Tab」の評判は?システムの特徴から口コミなどご紹介!
10.Myclinic問診票(エンパワーヘルスケア株式会社)

参考:Myclinic問診票
Myclinic問診票は、クリニックの業務効率の向上と患者の問診負担を軽減できるサービスです。導入すると、ホームページにリンクボタンを設置し、患者に対してスムーズな入力を促せます。
患者は問診表のボタンを選択するだけで入力できるため、迷わずに手続きを進められるのが特徴です。なお、入力はパソコンだけではなく、スマートフォンやタブレットからも利用できます。
関連記事:「My clinic 問診票」の評判は?システムの特徴から口コミなどご紹介!
11.MedicalTQ(株式会社ユー・アイ・エス)

参考:MedicalTQ
MedicalTQは、iPadで利用できるタッチパネル式の問診票アプリケーションです。オリジナルの問診票作成や電子カルテとの連携に対応しています。
数字入力や名前入力、人体シェーマなど1問1答形式で文字が大きく見やすく、患者に優しいWeb問診システムです。
関連記事:「Medical TQ」の評判は?システムの特徴から口コミなどご紹介!
12.Confy(アイテック阪急阪神株式会社)

参考:Confy
Confyは、予約や問診、結果参照をWebで利用できるサービスです。TOHMAS-iをはじめ、さまざまなサービスと連携できるため、診療業務を効率化できます。
そのほか、会員管理やコース検索、料金表示など業務に必要な機能が搭載されているのが特徴です。予約や問診、結果参照の1つから利用できるため、スポットで使いたい機能がある場合も検討してみてください。
13.wellnessMonsin(株式会社アドバンスブレイン)

wellnessMonsinは、健診業務の問診を効率化できるWeb問診サービスです。問診票の受け取りや提出の手間が不要になり、スタッフの業務負担を軽減できます。
シンプルな画面で設計されており、Web問診自体が初めての方でも簡単に操作可能です。また、準備作業の軽減や書類を探す手間なども軽減できます。
関連記事:wellness Monsinとは?評判・口コミ・料金を解説!
おすすめのWeb問診システム【クリニック業務全般支援タイプ】
おすすめのクリニック業務全般支援タイプは、以下の3選です。
- 医'sアシスト
- CLIUS
- デジスマ診療
それぞれ詳しく紹介します。
医'sアシスト
「医'sアシスト」は、予約・受付管理、オンライン問診票、診療支援など、クリニックの多岐にわたる業務を効率化するDXサービスです。AIを活用したオンライン問診により、患者の症状に応じた精度の高い問診が可能です。
また、健康管理アプリ「ウィズウェルネス」と連携し、検査結果やメッセージを患者に直接送信でき、患者との継続的な関係構築を支援します。
CLIUS
「CLIUS」は、クラウド型電子カルテで、オンライン診療機能や予約システムなどを搭載しています。
使いやすさを追求したUI・UXにより、診療中のストレスを軽減し、AIによる自動学習機能やクイック登録機能でカルテ入力時間を大幅に削減します。そのため、医師は患者と向き合う時間を増やすことが可能です。
デジスマ診療
「デジスマ診療」は、予約、受付、問診、電子カルテ連携、決済、次回予約までを一つのシステムで完結する総合診療支援システムです。QRコード読み取りによる自動受付や、キャッシュレス決済機能を備えており、患者の利便性を高めるとともに、クリニックの業務効率化を実現します。
また、リマインド機能や相互チャット機能により、患者とのコミュニケーションを強化し、再来院の促進にも寄与します。
おすすめのWeb問診システム【健康診断・人間ドック向けタイプ】
おすすめの健康診断・人間ドック向けタイプは、以下の3選です。
- スマートジェイ・メディキュー(小林クリエイト株式会社)
- どこでも問診(株式会社マーストーケンソリューション)
- CAMPUS Web問診(株式会社ヘルステック研究所)
それぞれ詳しく紹介します。
スマートジェイ・メディキュー(小林クリエイト株式会社)
「スマートジェイ・メディキュー」は、健診の受診前や当日に、受診者がスマートフォンやタブレット、PCからWeb上で問診内容を入力できるシステムです。そのため、従来の紙の問診票による業務負荷やデータ精度の課題を解決し、健診業務を効率化します。
どこでも問診(株式会社マーストーケンソリューション)
「どこでも問診」は、クラウド型のWeb問診システムで、受診者がPCやスマートフォン、タブレットから問診を入力できます。入力データはクラウドサーバーに格納され、健診実施時にダウンロードして閲覧・修正が可能です。
また、タブレットやスマホで誰にでも使いやすい入力画面を提供し、整合性チェック・入力漏れチェックにも対応しています。
CAMPUS Web問診(株式会社ヘルステック研究所)
「CAMPUS Web問診」は、大学保健管理センター向けに開発されたWeb問診システムで、受診者が事前に問診回答・データ送信することで、健診当日の業務負担や混雑を大幅に軽減します。
問診データをアップロードするだけで簡単に標準項目での問診フォームを作成でき、手間がほとんどかかりません。
まとめ

Web問診の導入により、受付スタッフの負担を軽減できるほか、来院前に患者の状態を確認できるなど、多くのメリットがあります。カルテとの連携や、他施設との情報共有など、豊富な機能を備えているシステムもあるため、自院の目的に合ったサービスの選定が重要です。
当記事を参考に、自院に適したWeb問診システムを選んでみてください。