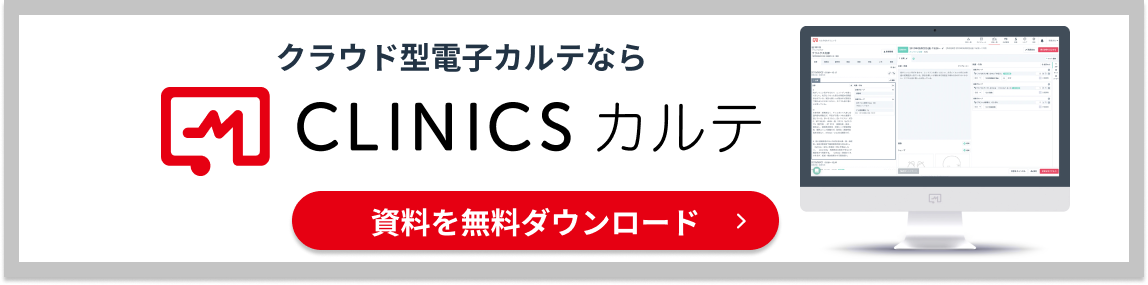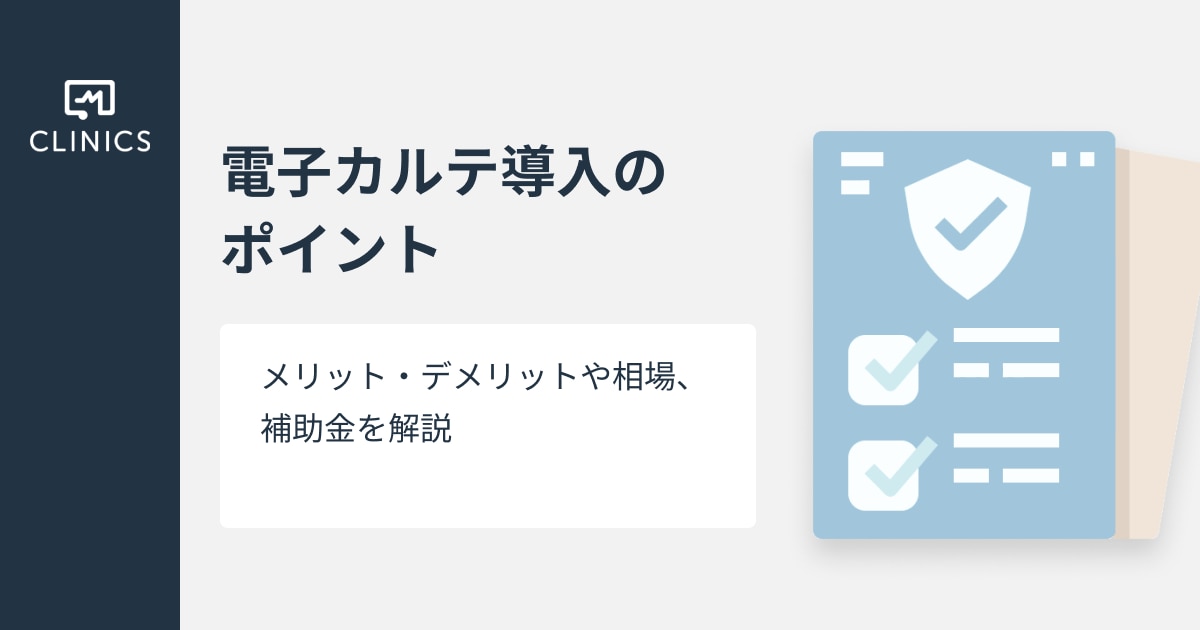
電子カルテ導入のメリット・デメリットとは?相場、補助金について解説
クリニックの業務効率化に欠かせないのが電子カルテです。しかし「何を基準に選定し導入すればよいのか」「運用にあたって注意点すべき点は?」など、さまざまな悩みや疑問が生じるかもしれません。
本記事では、電子カルテを選ぶ際のポイントや、導入時に留意すべき事項、そして効果的な運用の注意点について詳しく解説しています。電子カルテの導入を検討している方は、ぜひ一読ください。
目次[非表示]
- 1.電子カルテ導入のメリットとデメリット
- 1.1.電子カルテ導入のメリット
- 1.2.電子カルテ導入のデメリット
- 2.電子カルテの普及率
- 3.電子カルテの導入は大変?
- 4.電子カルテの導入費用の目安
- 4.1.オンプレミス型の目安
- 4.2.クラウド型の目安
- 4.3.ハイブリッド型の目安
- 5.電子カルテの導入に使える補助金・助成金
- 6.電子カルテの導入の流れ
- 6.1.1.電子カルテの絞り込み
- 6.2.担当者との打ち合わせ+デモ画面の確認
- 6.3.電子カルテメーカーの決定
- 6.4.試験運用
- 6.5.運用開始
- 7.まとめ
電子カルテ導入のメリットとデメリット
電子カルテ導入最大のメリットは、業務の効率化です。具体的には、会計時間の短縮や文書作成時間の削減など、複数の業務効率向上が期待できます。
メリットとデメリットの詳細については、こちらの記事で紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
電子カルテ導入のメリット
電子カルテを導入すると、診療記録や検査結果を瞬時に確認でき、診察時間の短縮や診療の質向上に繋がります。自動計算機能で会計もスムーズになり、待ち時間を減らせるでしょう。さらに、読み間違いや書き間違いを防ぐことができるため、医療ミスや事故の防止に役立ちます。
処方・検査テンプレートや定型文登録などの機能で、医師やスタッフの業務効率化も図れます。また、クラウド型であれば保管スペースも削減でき、院内の情報共有も容易になります。
電子カルテ導入のデメリット
電子カルテの導入には、初期費用や月額費用などさまざまなコストが発生します。見積もり内容をしっかり確認し、予算計画を立てましょう。
また、操作に慣れるまでには時間がかかる場合があり、導入前の研修やサポート体制が重要です。セキュリティ対策も必要です。ウイルス対策やアクセス制限など、セキュリティレベルの高いシステムを選びましょう。
電子カルテの普及率

電子カルテの普及率は、令和2年度時点で、一般病院の導入率57.2%、一般診療所の導入率49.9%となっています。この結果から分かるように、約半数の病院・診療所が電子カルテを導入しています。
ただし、病床規模別に見ると、導入率には大きな差があります。たとえば、400床以上の病院では導入率が91.2%に達していますが、200〜399床の病院では74.8%、200床未満の病院では48.8%にとどまっています。
このデータから明らかなように、大規模な病院ほど電子カルテの導入が進んでおり、一方で小規模な病院や診療所では普及が進んでいない傾向があります。
出典:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」
電子カルテの導入は大変?

電子カルテの導入に不安を感じる方も多いかもしれませんが、専門家のサポートがあればスムーズに進められます。
導入前には、複数の電子カルテメーカーを比較したうえで最適な電子カルテを選ぶようにしましう。
電子カルテの導入費用の目安

電子カルテの導入には、導入と運用にコストが発生します。ここでは「オンプレミス型」「クラウド型」「ハイブリッド型」の3つについて、導入費用の目安を紹介します。
導入費用の相場については、次の記事も参考にしてください。
オンプレミス型の目安
オンプレミス型の電子カルテは、院内にサーバーを設置してシステムを構築するタイプです。そのため、初期費用が高額になる傾向にあります。導入費用は300万円から500万円程度が目安です。
ただし、導入するシステムの規模や機能、カスタマイズの程度によって費用は大きく変動します。例えば、大規模病院で高度な機能やカスタマイズが必要な場合は、初期費用が1,000万円を超えることもあります。
クラウド型の目安
クラウド型の電子カルテは、インターネット経由でサービスを利用するタイプです。初期費用はオンプレミス型に比べて安価で、月額料金制で利用するのが一般的です。導入費用は100〜200万程度が相場です。
クラウド型の電子カルテは初期費用に加えて、基本的に月額料金が発生します。月額料金は1万円から数万円程度が目安です。
ハイブリッド型の目安
ハイブリッド型の電子カルテは、オンプレミス型とクラウド型の両方の特徴を併せ持つシステムです。基本的にはオンプレミス型のように院内にサーバーを設置しますが、クラウドの機能も利用できます。
初期費用は、オンプレミス型とクラウド型の中間程度になることが多く、100万円から300万円程度が目安です。月額料金はクラウドサービスの利用料などが含まれ、数万円から数十万円程度が目安となります。
電子カルテの導入に使える補助金・助成金

電子カルテの導入に使える補助金・助成金が「IT導入補助金」です。IT導入補助金は中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際に、費用の一部を補助する制度です。電子カルテも対象となり、最大450万円の補助を受けられます。
補助率は1/2以内なので、導入費用の半額を補助金で賄える可能性があります。詳しくは公式ページを参考にしてください。
電子カルテの導入の流れ

続いては、電子カルテを導入する際の流れについて下記項目ごとに解説していきます。
- 電子カルテの絞り込み
- 担当者との打合せ+デモ画面の確認
- 電子カルテメーカーの決定
- 試用運用
- 運用開始
1.電子カルテの絞り込み
まず電子カルテを絞り込みます。診療科によって求められる電子カルテの機能は異なるため、適切なメーカーを選ぶ際には診療科ごとの注意点を考慮することが重要です。
たとえば、眼科の場合、視野検査や眼底カメラ撮影など院内にさまざまな検査機器が導入されています。これらの周辺機器が電子カルテと連携できるかどうかが重要な観点になります。
検査結果を電子カルテに取り込めるようになれば、院内のどこにいても検査結果を確認できるため、患者の待ち時間短縮にも寄与するでしょう。
このように、診療科によって必要な機能は異なるため、注意点を踏まえた上でまずは、適したメーカーを3つほどに絞ることをおすすめします。
担当者との打ち合わせ+デモ画面の確認
次に、選定したメーカーの担当者との打ち合わせに入ります。この際、クリニックの診療科目や電子カルテ導入で実現したい要件などを具体的に伝えておきましょう。さらに、デモ画面を通じて見やすさや操作性の確認も重要です。
電子カルテ以外にも実現したい内容があれば、一緒に相談しておくとよいでしょう。最近では電子カルテと連携できるシステムも増えており、合わせて導入すれば、業務効率の向上が期待できます。
電子カルテメーカーの決定
担当者との打ち合わせを通じて、具体的な要件や運用に求める機能を明確にしたうえで最適なメーカーを選びましょう。この段階でメーカーが提供するデモを活用して、実際の操作性や使いやすさを多職種で確認し、意見をすり合わせることも重要です。
試験運用
電子カルテを発注した後、メーカーの担当者と仕様設定の打ち合わせが行われます。この時に、処方や治療、病名などの頻繁に入力する項目を設定し、運用時のスムーズ化を図ります。
設定作業が完了し納品されたら、開業の1〜2ヵ月前にスタッフ向けの説明会や研修を開催し、開業の1週間前には試験運用で問題がないかチェックしましょう。スタッフの視点からシステムの操作方法を確認することで、見落としていた課題や不明点が明らかになる場合もあります。
一部のメーカーでは、研修や試験運用時の立ち会いをしてくれる場合もあるため、サポート体制の有無やサポート内容などを事前に確認しておきましょう。
運用開始
検討・選定・発注・試験運用のステップを経て、電子カルテを本格稼働させる準備が整います。電子カルテの導入直後は、慌ただしくなり、不慣れなシステムで思わぬトラブルが発生する可能性はゼロではありません。
前述したように、導入直後は担当者や販売代理店のインストラクターがクリニックに立ち会い、サポートを提供する場合もあります。その間に浮かび上がった問題点を解決し、必要な設定変更で業務の効率化を図りましょう。
まとめ

電子カルテは、自院に適したメーカーを導入する必要があります。診療科ごとに必要な電子カルテの機能は異なるため、適切なメーカーの選定には各診療科の特性も考慮しましょう。
電子カルテは数々の利点を有し、効果的な活用により業務の効率化が期待できます。導入段階では、適切な選定が重要です。電子カルテの導入によって、業務プロセスを更に効率化しましょう。