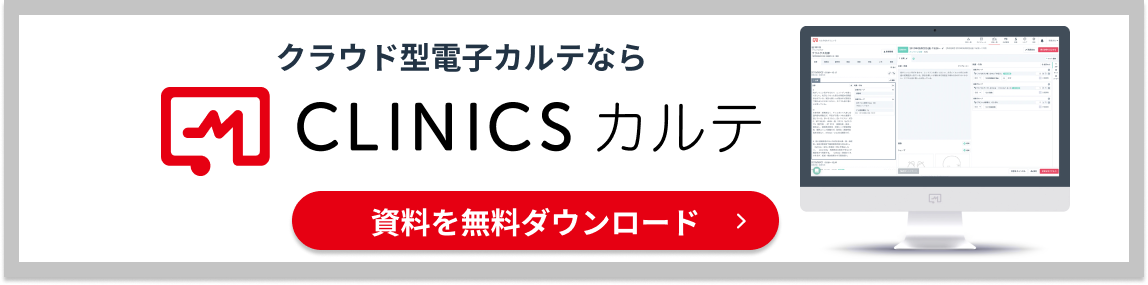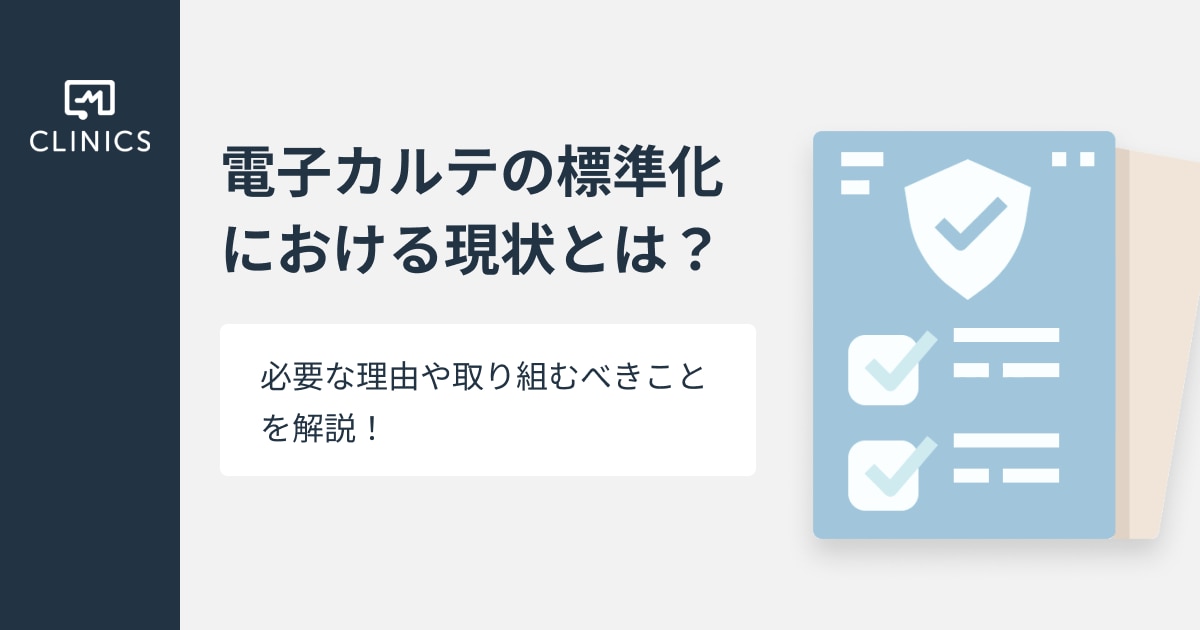
電子カルテの標準化における現状とは?必要な理由や取り組むべきことを解説!
内閣府が公表した「経済財政運営と改革の基本方針2022」に電子カルテ標準化の必要性が明記されました。
電子カルテの普及が進む中でなぜ標準化の必要性が叫ばれているのか、理解できていない方は多いでしょう。そこで、当記事では電子カルテの標準化が必要な理由や現状、取り組むべきことについて解説します。
目次[非表示]
- 1.医療情報システムに標準化が必要な理由
- 2.電子カルテの標準化によって期待される効果
- 2.1.【医療機関】業務効率化などにつながる
- 2.2.【保険者】検査の重複などを避けられる
- 2.3.【国民】健康の増進に役立つ
- 3.電子カルテを標準化する4つのメリット
- 3.1.メリット1.システムの導入や移行をしやすくなる
- 3.2.メリット2.院外でのデータ連携が容易になる
- 3.3.メリット3.問診を効率的かつ正確に実施できるようになる
- 3.4.メリット4.院内の情報共有もスムーズになる
- 4.電子カルテを標準化する4つのデメリット
- 4.1.デメリット1.紙カルテに比べてコストがかかる
- 4.2.デメリット2.操作を周知する必要がある
- 4.3.デメリット3.個人情報の取り扱いが難しくなる
- 4.4.デメリット4.停電が起きると利用ができない可能性がある
- 5.日本における電子カルテの標準化に対する現状
- 6.日本で電子カルテの標準化が普及しない理由
- 7.電子カルテの標準化を普及させるために取り組むべきこと
- 8.まとめ
医療情報システムに標準化が必要な理由

医療機関に蓄積された診療データをより高度に活用し、新しいサービスの創出、よりよい医療社会の実現が求められています。これらを実現するには、異なる施設間でのデータ交換を容易かつスムーズにする必要があります。
しかし現在、各医療機関が独自方式でシステム連携をしている状況です。この状況ではスムーズなデータ連携が行えません。そこで必要になってくるのが、医療情報システムの標準化です。
共通規格に準拠する標準化が行われれば、すべての施設・ベンダーが対応可能になるため、データの連携・交換がスムーズになります。また、内閣府が公表した「経済財政運営と改革の基本方針2022」では、医療・介護サービスの効率化・質の向上を目的にPHR事業を促進し、電子カルテを標準化することの必要性も明記されました。
高齢者人口が増加し医療・介護への負担が増す中で、質の高い医療提供と、医療業務の効率化を両立させるためには、医療情報システムの標準化が必要不可欠と言われています。
電子カルテの標準化によって期待される効果

電子カルテの標準化は、さまざまな効果が期待できます。ここでは医療機関、保険者、国民という3つの立場から、期待される効果をわかりやすく解説します。
【医療機関】業務効率化などにつながる
電子カルテの標準化が実現すれば、ほかの医療機関で処方された薬や検査情報を容易に参照できるようになり、患者からの聞き取りや情報収集にかかる負担が大幅に軽減されます。さらに、短時間で紹介状や診療情報提供書などの書類を作れるようになるでしょう。
また、データ入力や情報検索が簡便になることで、事務作業の負担軽減や診療時間の短縮、患者の待ち時間の削減といった効果も期待できます。
【保険者】検査の重複などを避けられる
電子カルテの標準化によって他医療機関の情報が参照可能になれば、重複検査を防ぎ、医療費や患者の負担を軽減できます。例えば、患者さんが複数の医療機関を受診した場合、過去の検査データや投薬歴を共有することで、同じ検査を何度も繰り返す必要がなくなります。
また、特定健診や診療情報を活用した企業の保健指導を実施しやすくなります。さらに、診療内容や医療費のデータを集計・分析することで、医療費の適正化に向けた取り組みや、医療の質向上のための施策を検討できるようになるでしょう。
【国民】健康の増進に役立つ
電子カルテの普及により医療機関間の情報共有がスムーズになると、国民は適切な医療を受けやすくなるでしょう。引っ越し先や旅行中でも過去の病歴やアレルギー情報を共有できるため、迅速で正確な診察や治療が期待できるようになります。
さらに、スマートフォンで自分に合った医療情報を確認できるようになり、健康意識が向上するでしょう。オンライン診療の利用も進み、通院の手間が減ります。将来的には、健康データを活用した予防医療や健康増進サービスの普及が見込まれ、安心で質の高い医療の実現につながります。
電子カルテを標準化する4つのメリット

電子カルテを標準化すると次の4つのメリットが得られます。
- システムの導入や移行をしやすくなる
- 院外でのデータ連携が容易になる
- 問診を効率的かつ正確に実施できるようになる
- 院内の情報共有もスムーズになる
近年自院で完結する医療から、地域で完結を目指す医療を求められるケースが増えています。電子カルテを標準化することにより、患者さんの情報を自院から他の医療機関に共有しやすくなるのです。
ほかの病院に対しても情報共有をスムーズにできれば、患者さんは何度も説明をする必要がなくなり、スムーズな医療提供が可能となります。
メリット1.システムの導入や移行をしやすくなる
電子カルテを標準化するメリットとして、システムの導入や移行をしやすくなる点が挙げられます。従来の医療情報システムは、複数の会社のシステムをつなげて稼働していることが一般的です。
システム同士の接続部分が多ければ多いほど、手間や費用がかかることになります。しかし、システムを標準化することによりシステム間の接続が容易になることから、導入や移行がスムーズになります。また、このことからコスト削減や業務負担の軽減も期待できるのです。
メリット2.院外でのデータ連携が容易になる
電子カルテを標準化するメリットとして、院外でのデータ連携が容易になることが挙げられます。近年では高齢化社会や疾病構造の変化によって地域での完結が求められています。
このことから、地域の医療機関と患者さんの情報を共有することが必要です。そこで、カルテの電子化を標準化することでスムーズに院外でもデータ連携をできます。
メリット3.問診を効率的かつ正確に実施できるようになる
電子カルテを標準化するメリットとして、問診を効率的かつ正確に実施できるようになることが挙げられます。従来の紙カルテの情報だけでは、十分な情報をスムーズに共有できないことがあります。
例えば転院する場合は紹介状が必要ですが、紹介状だけでは十分な情報を提供できないのです。そこで、電子カルテを標準化することにより、他の医療機関にもデータをスムーズに共有できるようになります。
メリット4.院内の情報共有もスムーズになる
電子カルテを標準化するメリットとして、院内の情報共有もスムーズになることが挙げられます。現在の電子カルテシステムは、検査システムや放射線システムなどさまざまなシステムを連携して利用しています。そこで、電子カルテを標準化してシステム全体を統一することにより、院内の情報共有がスムーズになります。
電子カルテを標準化する4つのデメリット

電子カルテを標準化すると次の4つがデメリットとなる場合はあります。
- 紙カルテに比べてコストがかかる
- 操作を周知する必要がある
- 個人情報の取り扱いが難しくなる
- 停電が起きると利用ができない可能性がある
しかし、いずれのケースにおいても進化した電子カルテが登場しています。そのため、結果的に紙カルテを運用しているよりもスムーズになる可能性があります。
デメリット1.紙カルテに比べてコストがかかる
電子カルテを標準化するデメリットとして、紙カルテに比べてコストがかかる可能性があります。まず、導入費用に100万円〜300万円必要でクラウド型であれば月額費用も発生します。
しかし、担当者の負担を大幅に減らすことで人件費の削減になり、紙代や印刷代などをなくせることから長期スパンで考えるとコスト削減につながることもあるのです。
デメリット2.操作を周知する必要がある
電子カルテを標準化するデメリットとして操作を周知する必要があります。電子カルテは医師や医療事務担当者などすべての担当者が扱う必要があり、操作に慣れなければ結果的に手間を増やす可能性があります。
このような状況にならないように、操作を周知したりできる限り簡単に使えるシステムを導入したりすることが重要です。
デメリット3.個人情報の取り扱いが難しくなる
電子カルテを標準化するデメリットとして個人情報の取り扱いが難しくなります。しかし、近年ではセキュリティや個人情報の扱いに特化した電子カルテが増えており紙で個人情報を管理するよりもスムーズであるケースが増えています。
そのため、必ずしも電子カルテを導入することによって個人情報の取り扱いが難しくなるとは限りません。
デメリット4.停電が起きると利用ができない可能性がある
電子カルテを標準化するデメリットとして停電が起きると利用ができない可能性があります。停電以外にも機材トラブルが起きる可能性があるため、トラブル時に対応してもらえるような業者に依頼することが重要です。
日本における電子カルテの標準化に対する現状

日本では電子カルテ情報の全国的な共有を実現するため、標準化の取り組みが進められており、2025年度中の本格運用を目標にプロジェクトが加速しています。具体的には、医療機関において既存の電子カルテを国際標準規格であるHL7 FHIRに対応させる取り組みや、未導入施設での新規導入が求められているのが現状です。
また、健康診断結果や診療情報、処方箋情報などを標準化し、全国の医療機関で閲覧可能とする仕組みの整備が進められています。2025年度の全国展開を目指し、すでに9地域でモデル事業が計画されています。
しかしながら、課題も指摘されています。厚生労働省は病院規模や電子カルテの導入状況に応じた補助金を用意しているものの、未導入施設への支援策が不十分であることが問題視されています。さらに、大規模病院(400床以上)での改修スケジュールの遅れや、導入費用の高騰への対応も大きな課題です。
日本で電子カルテの標準化が普及しない理由

日本で電子カルテの標準化が普及しない理由はさまざまなものが挙げられますが、1番の理由は目的が不明瞭な点です。
例えば、アメリカは病院内ではなく、病院間や患者向けといった病院外で使用するシステムを目的にし、推進に向けて2兆円の予算を確保しました。そして、地域の医療機関間でデータ連携・共有するEHR(EHRのフルの名前をここに書く)と患者の診療情報を入手するPHRを実現するという明確な目標を掲げています。
一方で、日本は早い時期に電子カルテが発展したことで目的が不明瞭となり、病院は業務効率化を目的に電子カルテを導入するようになりました。その結果、標準化よりも個別化が優先され、標準化が普及しないという状況に陥っています。
電子カルテの標準化を普及させるために取り組むべきこと

電子カルテの標準化を普及させるために取り組むべきことは次が挙げられます。
- 標準化の目的を明確にする
- 実現計画の立案・必要予算の確保
- 確立されている国際的な標準化の積極利用
PHRの実現と基盤となるEHRの整備や、地域医療計画の実現に向けたEHRでの情報共有のような、標準化の目的を明確にすることが大切です。その上で、期間を設定し、期間内で実現するための計画を立案し、推進するための予算を確保する必要があるでしょう。
まとめ

すでに病院内でシステム運用ができている中でシステムの標準化をする場合、仕様変更の手間もかかりますし、その分の改修費用も見込まなければなりません。したがって、いくら地域医療の推進といっても、効果が期待できなければ標準化の推進は難しいといえます。
電子カルテの標準を普及させるためには、国が主体となって標準化の目的を明確にするとともに、その効果や重要性を説き、推進に向けて支援する必要があるといえるでしょう。