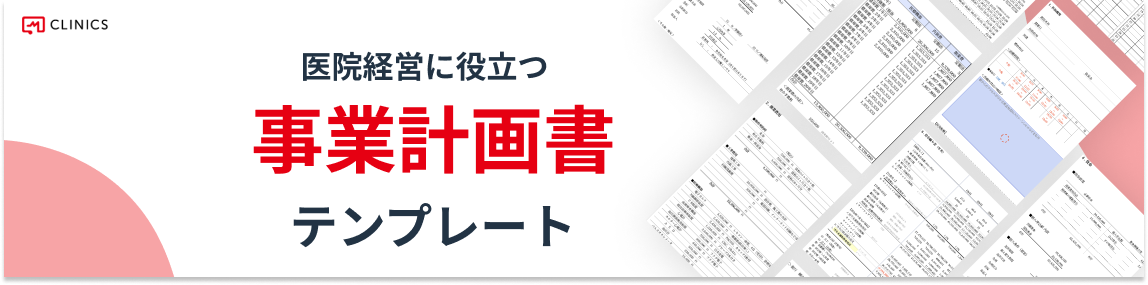クリニックの事業計画書を書くには?書き方や作成手順を紹介【テンプレートあり】
クリニックの開業にあたり事業計画書を作成する必要がありますが、上記のような疑問を抱く方もいます。
初めてクリニックを開業する場合、なぜ事業計画書の作成が重要なのかイメージできない方もいるでしょう。当記事では、クリニックの事業計画書を作成する目的やクリニックの事業計画書が必要な3つの理由などを紹介します。
目次[非表示]
- 1.クリニックの事業計画書を作成する目的
- 2.クリニックの事業計画書が必要な3つの理由
- 2.1.1.開業後に安定して経営するため
- 2.2.2.融資に通るため
- 2.3.3.運転資金不足を防止するため
- 3.事業計画書のテンプレート
- 4.事業計画書を作成する際の5つのステップ
- 4.1.1.開業資金(初期投資)の見積もり
- 4.2.2.支出の見積もり
- 4.3.3.収入の見積もり
- 4.4.4.資金繰り表の策定
- 4.5.5.開業までのスケジュール策定
- 5.事業計画書の書き方
- 5.1.数字で表示する項目
- 6.クリニックの事業計画書テンプレートについてよくある質問
- 7.まとめ
クリニックの事業計画書を作成する目的
クリニックの事業計画書を作成する目的は、開業に伴うリスクを最小限に抑えるためです。
事業計画書が曖昧だと不要な医療機器を導入してしまったり理念に合わないスタッフを採用したりするなど、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
詳細な事業計画書を作成すると、戦略が明確になり安全にクリニックを運営できるでしょう。
クリニックの事業計画書が必要な3つの理由

クリニックの事業計画書が必要な理由は次の3つです。
- 開業後に安定して経営するため
- 融資に通るため
- 運転資金不足を防止するため
それぞれ詳しく紹介します。
1.開業後に安定して経営するため
クリニックの事業計画書が必要な理由は、開業後に安定して経営するためです。
クリニックは開業して終わりではなく、経営を安定させる必要があります。事業計画書が曖昧だと、不要な医療機器の購入などにより資金不足に陥る場合も少なくありません。
詳細な事業計画を作成すれば、開業後の資金繰りで困ることが少なくなり安定した経営につながるでしょう。
関連記事:クリニック経営について徹底解説|失敗する原因や成功させるためのポイントについてご紹介/潰れるクリニックの6つの特徴|潰さない対策や倒産動向についても徹底解説します
2.融資に通るため
融資に通るためにも、事業計画書は必要です。
クリニックの事業計画書は、以下の3つで構成されています。
- 経営基本計画
- 収支計画
- 資金計画
収支計画と資金計画には、必要な資金の具体的な記載が必要です。資金について記載されていると、融資する銀行がお金を貸していいか判断しやすくなります。
融資先から信頼を獲得し、審査に通るためにも事業計画書は詳細に作成しましょう。
関連記事:クリニック開業の融資について徹底解説|融資の流れや受ける際のポイントもご紹介/クリニックの開業資金調達で活用できる融資4選!融資を受けるステップや注意点も徹底解説!
3.運転資金不足を防止するため
事業計画書を作成することで、運転資金不足を防止できます。
クリニックを開業しても経営が上手くいくとは限りません。先を見越した資金を準備していない場合、資金不足に陥りクリニックを続けられなくなります。
事業計画書があると、必要な資金が明確になり安定して経営することができるでしょう。開業後の資金不足を回避するためにも、事業計画書の作成は重要です。
関連記事:クリニックの開業資金はどれくらい必要?自己資金や費用内訳についても解説します!/【最新版】開業しやすい診療科TOP5!開業資金の目安や開業に失敗しないためのポイントも紹介
事業計画書のテンプレート

事業計画書のテンプレートは、資金調達をする際の金融機関などに合ったものを選びましょう。金融機関によって、所定のテンプレートが用意されていることもあります。
ここでは日本政策金融公庫のテンプレートにしたがって、事業計画書の作成例を紹介します。
- 創業の動機
- 内科医師として総合病院に勤務し、地域の高齢者医療に携わってきた経験から、慢性疾患を抱える患者の長期的なフォローアップの重要性を感じ、より丁寧な診療を提供できる環境を求め、独立してクリニックを開業したいと考えた。
- 知人から○○駅近くに適した物件を紹介され、周囲に競合のクリニックがなく、市場調査 の結果、十分な需要が見込めることを確認したため、開業を決意した。
- 経営者の略歴
年月 |
内容 |
H○年○月 |
○○大学医学部卒業 |
H○年○月〜 |
○○総合病院 内科勤務(6年間) |
H○年○月〜 |
○○クリニック 副院長(4年間、現在の月給50万円) |
R○年○月 |
退職予定 |
過去の事業経験
☑ 事業を経営していたことはない。
☐ 事業を経営していたことがあり、現在もその事業を続けている。(→事業内容: )
☐ 事業を経営していたことがあるが、既にその事業をやめている。(→やめた時期: 年 月)
取得資格
☑ 有( 医師免許(H○年○月取得) )
☐ 特になし
知的財産権等
☑ 特になし
☐ 有( 申請中 / 登録済 )
- 取扱商品・サービス
取扱商品・サービス |
売上シェア |
①一般内科診療 |
60% |
②生活習慣病管理 |
25% |
③予防接種・健康診断 |
15% |
セールスポイント
- 経験に基づいた診療技術を提供する。
- 診療とあわせ、十分なカウンセリングを行い、生活習慣病予防の指導や定期的なアフターケアサービスを行う。
- ○○駅を利用する会社員向けに早朝診療をするなど差別化を図る。
販売ターゲット・販売戦略
- 地域住民(会社員・高齢者)
- 企業・自治体と連携し、健康診断サービスを提供。
競合・市場など企業を取り巻く状況
- ○○駅周辺には4か所の内科クリニックがあり、差別化を意識する必要がある。
- 取引先・取引関係等
取引先名 |
シェア |
掛取引の割合 |
回収・支払いの条件 |
|
|
販売先
|
一般個人(自己負担・自由診療) |
70% |
- |
即金 日〆 |
一般個人(社保・国保) |
30% |
100% |
末日〆 翌々20日・翌々25日回収 |
|
|
仕入先 |
○○商事(診療機器) |
50% |
100% |
末日〆 翌末日支払 |
△△会社(医薬品) |
50% |
100% |
末日〆 翌末日支払 |
|
外注先 |
□□技工(外注業務) |
100% |
100% |
末日〆 翌末日支払 |
|
人件費支払 |
末日〆 翌15日支払(ボーナス支給月) |
|||
- 従業員
常勤役員の人数(法人のみ) |
従業員数(3ヶ月以上継続雇用者) |
うち家族従業員 |
うちパート従業員 |
-人 |
4人 |
0人 |
1人 |
- お借入の状況(法人の場合、代表者の借入)
お借入先名 |
お使いみち |
お借入残高 |
年間返済額 |
○○銀行△△支店 |
☑ 住宅 □ 車 □ 教育 □ カード □ その他 |
2,500 万円 |
130 万円 |
□□ファイナンス |
□ 住宅 ☑ 車 □ 教育 □ カード □ その他 |
500 万円 |
25 万円 |
- 必要な資金と調達方法
必要な資金 |
見積先 |
金額 |
設備資金 |
1,700万円 |
|
診療所内外装工事(設備工事含む) |
〇〇建設 |
600万円 |
診療設備(超音波検査機、心電図、診察ベッド等) |
◯☓医療機器 |
900万円 |
| 什器・備品類 |
△△商事 |
100万円 |
保証金 |
100万円 |
|
運転資金 |
300万円 |
|
医薬品・消耗品仕入 |
150万円 |
|
人件費支払 |
150万円 |
|
合計 |
2,000万円 |
調達の方法 |
金額 |
自己資金 |
700万円 |
日本政策金融公庫 国民生活事業からの借入 |
1,000 万円 |
(元金12万円×84回・年○.○%) |
|
他の金融機関等からの借入 |
300 万円 |
(○○信用金庫 元金5万円×60回・年○.○%) |
|
合計 |
2,000 万円 |
- 事業の見通し(月平均)
項目 |
創業当初 |
1年後(軌道に乗った後) |
売上高 ① |
250万円 |
325万円 |
売上原価 ② |
50万円 |
65万円 |
| 人件費 |
70万円 |
95万円 |
家賃 |
20万円 |
20万円 |
支払利息 |
3万円 |
3万円 |
その他経費 |
50万円 |
67万円 |
経費合計③ |
143万円 |
185万円 |
利益(①-②-③) |
57万円 |
75万円 |
<収支計画>
- 売上高:保険診療平均単価 8,000円 × 15人 × 23日 = 276万円
- 自由診療:月7万円
- 原価率:20%
- 人件費:
- 医師(院長)1名
- 看護師2名(28万円×2人)
- 医療事務2名(22万円×2人)
- パート1名(12万円)
- 家賃:20万円
- 支払利息:
- 1,500万円 × 年○.○% ÷ 12ヵ月 = ○万円
- 計 3万円
- その他光熱費・消耗品費等:50万円
<創業1年後(軌道に乗った後)>
- 売上高:創業当初の1.3倍(勤務時の経験から)
- 原価率:当初の20%を維持
- 人件費:
- 従業員1人増加(+25万円)
- その他経費 +17万円
事業計画書を作成する際の5つのステップ

所定のテンプレートがない場合、ご自身で事業計画書を作成する必要があります。
事業計画書を作成する際の流れは以下の通りです。
- 開業資金(初期投資)の見積もり
- 支出の見積もり
- 収入の見積もり
- 資金繰り表の策定
- 開業までのスケジュール策定
それぞれ詳しく紹介します。
1.開業資金(初期投資)の見積もり
事業計画書を作成するにあたって、最初は開業資金の見積もりを出す必要がありますま
開業当初は物件の費用や医療機器の購入費用、内装工事代などが必要です。また、クリニックの認知度を広めるための広告費やコンサルティング代も含まれます。
融資を受けるためにも、開業資金の見積もりを出しましょう。
2.支出の見積もり
開業資金の見積もりが決まったら、支出の見積もりを出しましょう。
クリニックで支出となる項目は、固定費と変動費に分けられます。固定費ではスタッフの人件費や賃借料、水道・光熱費が対象です。
変動費としては薬品費や診療材料費などが該当します。
特に医療機器や賃借料は高額です。大きな出費になるため、どれくらいの金額になるか事前に把握しておきましょう。
3.収入の見積もり
支出のあとは、収入の見積もりを出しましょう。
クリニックの収入に含まれる項目は、以下の通りです。
- 患者数
- 診療日数
- 患者一人当たりの平均単価
1日の患者数は診療科目によって大きく異なります。例えば、頻繁に手術が必要な診療科目であれば対応できる患者数は少なくなるでしょう。
患者数を計算する場合は、患者数が多い場合と少ない場合の両方を検討すると見積もりを立てやすくなります。
診療日数に関しては、1年間で何日営業するのか検討しましょう。また、患者一人あたりの平均単価も診療科目によって異なります。
上記の項目を考慮した上で、クリニックの収入がいくらになるか見積もりを立てましょう。
4.資金繰り表の策定
収入の見積もりまで立てられたら、資金繰り表を策定しましょう。
開業時、不要な医療機器などの導入により資金繰りが上手くいかないことは少なくありません。詳細な資金繰り表を策定すると、不要なものに費用を割かなくなり経営を安定させられます。
資金繰り表で記載が必要な項目は以下の通りです。
- 毎月の支出
- 毎月の診療収入
- 開業時に用意できる運転資金
- 月末の運転資金残高
資金繰りが上手くいかない場合、追加で融資を受ける必要が出てきます。
追加融資を受けることなく安定して経営できるように、資金繰り表は正確に策定しましょう。
5.開業までのスケジュール策定
資金繰り表を作成したあとは、開業までのスケジュールを策定しましょう。
開業に伴い準備するものは数多くあります。開業までに物件の選定や内装工事、スタッフの採用などが必要です。
また「開業の1ヵ月前には内装工事を完成させる」など、開業日から逆算したスケジュールを策定しなくてはいけません。
開業後スムーズに運営するために、スタッフの教育も必要であるため1〜2年ほど準備期間があると抜け目なく準備することができます。
開業の失敗を防ぐためにも、開業までのスケジュールを綿密に決めましょう。
関連記事:【新規開業医必見】クリニック開業申請の流れを徹底解説!スケジュールや必要書類まで/クリニック開業のスケジュールを徹底解説!タイミングごとに必要な内容を詳しくお伝えします
事業計画書の書き方

事業計画書の書き方は、以下の2つです。
- 数字で表示する項目
- 言葉で表示する項目
それぞれ解説します。
数字で表示する項目
事業計画書の中で、数字で表示する項目は以下の通りです。
- 資金調達方法
- 資産・借り入れ状況
- コスト
- 事業の見通し
資金調達方法
クリニック開業に必要な資金は、主に自己資金と外部からの借入金で構成されます。自己資金は、個人の貯蓄や家族からの支援などが該当します。外部からの借入金としては、金融機関からの融資が一般的であり、日本政策金融公庫や民間銀行からの医療機関向けローンが利用可能です。
資金調達の際には、開業資金(初期投資)と運転資金の総額を明確にし、それぞれの調達方法と金額を具体的に計画書に記載することが重要です。例えば、総資金2,000万円のうち、自己資金800万円、金融機関からの借入金1,200万円といった具合です。このように具体的な数字を示すことで、資金計画の信頼性を高めることができます。
資産・借り入れ状況
事業計画書には、開業時点での資産状況と既存の借入金の状況を詳細に記載する必要があります。資産には、現金預金、不動産、株式などが含まれ、これらの評価額を明示します。借入金については、借入先、残高、年間返済額を具体的に記載します。
例えば、〇〇銀行からの借入金500万円、年間返済額50万円といった情報です。これらの情報を正確に示すことで、金融機関は返済能力を評価しやすくなり、融資審査の際の重要な判断材料となります。
コスト
クリニックの運営には、初期費用と継続的な運営費用が発生します。初期費用には、物件取得費、内装工事費、医療機器購入費、広告宣伝費などが含まれます。運営費用としては、人件費、賃借料、水道光熱費、医療材料費、外注費などが挙げられます。
これらの費用を月別や年別に詳細に見積もり、事業計画書に記載することで、資金繰りの計画を明確にし、経営の安定性を示すことができます。例えば、月間の人件費が50万円、賃借料が20万円、水道光熱費が5万円といった具体的な数字を示すことが重要です。
事業の見通し
事業の見通しを立てる際には、収入と支出の予測を基に損益計画を作成します。収入面では、診療科目ごとの1日あたりの平均患者数、患者一人当たりの平均単価、診療日数などを考慮し、月間および年間の売上を予測します。例えば、1日平均患者数30人、平均単価5,000円、月間診療日数20日とすると、月間売上は30人×5,000円×20日=300万円となります。
支出面では、前述のコスト項目を考慮し、固定費と変動費を合計します。これらの情報を基に、損益分岐点を算出し、何人の患者数や売上があれば黒字化するのかを明確にします。このような詳細な数値計画を示すことで、事業の実現可能性や収益性を客観的に伝えることができます。
言葉で表示する項目
事業計画書の中で、言葉で表示する項目は以下の通りです。
- 開業の動機
- コンセプト
- 経営理念コンセプト
- 経営理念
- 医師を目指した理由
開業の動機
開業の動機は、医師がなぜ独立してクリニックを開設しようと考えたのか、その背景や目的を明確にする部分です。これまでの医療現場での経験や、地域医療への貢献意欲、特定の医療ニーズへの対応など、具体的なエピソードや課題意識を盛り込むことで、開業への熱意や使命感を伝えることができます。
例えば、「総合病院での勤務を通じて、地域の高齢者医療の重要性を痛感し、在宅医療を充実させるために開業を決意した」といった具体的な動機を記載します。このように、開業の動機を明確に示すことで、事業計画書全体の説得力が増し、金融機関からの融資審査や関係者の理解を得やすくなります。
コンセプト
コンセプトは、開業するクリニックの基本的な方針や特徴を示すもので、他の医療機関との差別化を図るための重要な要素です。具体的には、提供する医療サービスの内容や対象とする患者層、診療時間、診療体制などを明確にします。
例えば、「地域の子育て世代を支援するため、小児科専門のクリニックとして、土日診療や夜間診療を行い、予防接種や育児相談にも力を入れる」といった具体的なコンセプトを設定します。このように、クリニックの特徴や強みを明確にすることで、患者からの信頼を得やすくなり、集患にも効果的です。
経営理念
経営理念は、クリニックの運営における基本的な価値観や信念を示すもので、スタッフ全員が共有すべき指針となります。例えば、「患者様の立場に立った思いやりのある医療を提供し、地域社会の健康増進に貢献する」といった理念を掲げることで、クリニックの目指す方向性を明確にします。
このような経営理念を設定することで、スタッフのモチベーション向上や一体感の醸成につながり、組織全体の質の向上にも寄与します。また、経営理念は患者や地域住民にも伝えることで、クリニックの信頼性やイメージ向上にもつながります。
クリニックの事業計画書テンプレートについてよくある質問

クリニックの事業計画書テンプレートについてよくある質問は以下の通りです。
- 事業計画書を作成する際の注意点とは?
- 事業計画書は自分で作成すべき?
- 開業を成功させる資金計画の考え方とは?
疑問を解消できるように、それぞれ詳しく回答していきます。
1.事業計画書を作成する際の注意点とは?
事業計画書を作成する際は、以下の項目に注意しましょう。
- 初期費用を抑える
- 収入は厳しく見積もる
- 計画の見直しや開業時期の変更
開業時の支出や負債はおおよそ見積もり通りになりますが、収入は見積もり通りにいかない可能性があります。
患者数を確保できず、予想より収入を見込めないケースもあるでしょう。収入を見込めない場合を想定して、不要な投資はせずに初期費用を抑えることが大切です。
「十分な収入を見込めない」「開業を失敗するリスクが大きい」などの場合は、計画や開業時期の変更も必要です。
2.事業計画書は自分で作成すべき?
事業計画書は、開業コンサルタントへ依頼しても良いでしょう。
ただし、開業コンサルタントへすべてを依頼するのはおすすめできません。
開業医が事業計画書の内容を把握するためにも、大まかな部分は自分で作成し、開業コンサルタントには修正などを依頼しましょう。
関連記事:【最新版】クリニックにおすすめのコンサル28選!業務内容や選ぶポイントを徹底解説
3.開業を成功させる資金計画の考え方とは?
開業を成功させるには逆算思考が必要です。
「必要な生活費はいくら」「毎月これくらい貯金したい」などを先に決めると、大きな支出も避けられます。
不要な出費により資金不足になる開業医も多いため、逆算思考を取り入れると開業が成功しやすいでしょう。
まとめ

ここまで、クリニックの事業計画書を作成する目的やクリニックの事業計画書が必要な3つの理由などを紹介しました。
事業計画書は開業時に加えて、経営を安定させるためにも重要です。詳細な事業計画書があると支出や収入が明確になり、資金不足を回避できます。
将来的に開業予定の方は、安定して経営できるように時間をかけて事業計画書を作成しましょう。