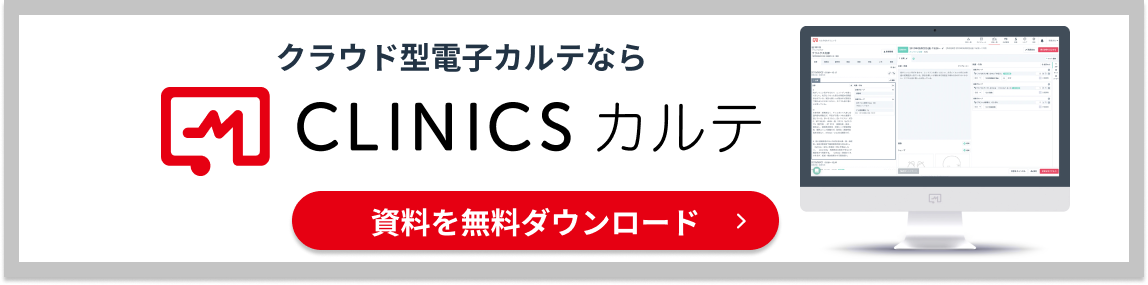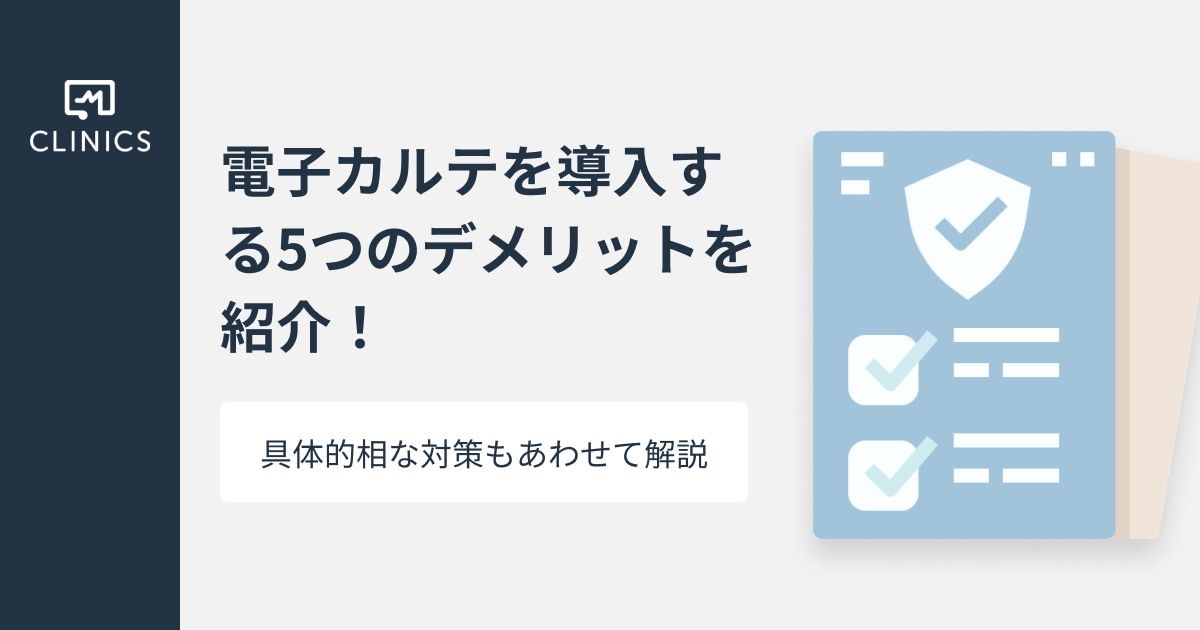
電子カルテを導入する5つのデメリットを紹介!問題点とその対策もあわせて解説

DX推進や人手不足の解決を目的に医療分野でもIT化の波が押し寄せています。近年、医療業務を効率化できるツールとして注目を集めているのが「電子カルテ」です。
管理の正確性や情報共有の素早さなどのメリットを享受できることから、電子カルテの普及は進んでいます。しかし、電子カルテには問題点もあり、導入したからといって必ず業務を効率化できるわけではありません。
当記事では、電子カルテを導入するデメリットと、問題点を解決するための具体的な対策について解説します。
目次[非表示]
- 1.電子カルテの3つの種類
- 1.1.1.クリニック向け
- 1.2.2.中小規模病院向け
- 1.3.3.大規模病院向け
- 2.電子カルテを導入する5つのデメリット
- 2.1.1.導入やランニングにコストがかかる
- 2.2.2.情報漏洩のリスクがある
- 2.3.3.インターネット環境が常に必要
- 2.4.4.一定のPCスキルが必要になる
- 2.5.5.院内における運用体制の変更が伴う
- 3.電子カルテを導入するデメリットへの対策
- 3.1.メーカーのサポート体制を確認する
- 3.2.全体費用を考慮する
- 3.3.導入目的を明らかにする
- 3.4.提供形態を確認する
- 4.問題点を解決するならクラウド型電子カルテ
- 4.1.導入やランニングを抑えられる
- 4.2.更新・メンテナンス作業の負担軽減
- 4.3.外部のサーバーにバックアップが残る
- 5.クラウド型の電子カルテがおすすめ
電子カルテの3つの種類

電子カルテの種類として次の3つが挙げられます。
- クリニック向け
- 中小規模病院向け
- 大規模病院向け
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.クリニック向け
クリニック向けの電子カルテはクラウド型の電子カルテが豊富で、オンプレミス型と比較すると安価に使用することが可能です。また、クラウド型はインターネットを介して、既に完成されているシステムを使用します。
したがって、保守・管理はクラウドサービスを提供する企業が担うため、保守・管理の手間もかかりません。サービスによっては無料利用できる場合もあるため、予算や機能といった点を精査しながら自社に最適な種類を選ぶとよいでしょう。
2.中小規模病院向け
中小規模病院向けの電子カルテもクリニック向け同様、クラウド型の電子カルテがおすすめです。前述のとおり、クラウド型であれば初期費用や月額料金を抑えることができ、サーバーを院内に設置する必要がありません。
保守・管理の手間がかからないため、IT人材が少ない中小病院でも問題なく導入・運用ができるでしょう。ただし、クラウドサービスとは連携できない独自システムを使用していたり、院内に保有したりしている場合、クラウド型よりもオンプレミス型を選んだ方がよいでしょう。
3.大規模病院向け
専門分野を取り扱っている病院の場合、一般提供されているクラウド型の電子カルテでは対応できない場合があるため、独自システムを構築しなければなりません。
そのため、大規模病院向けの電子カルテはカスタマイズ性の高いオンプレミス型が中心となります。オンプレミス型はクラウド型と比較すると、導入や保守・管理に多額の資金がかかりますが、資金力のある大規模病院だからこそ導入できるといえるでしょう。
関連記事:電子カルテとは?メリットや注意点、選び方などをわかりやすく解説
電子カルテを導入する5つのデメリット

電子カルテを導入するデメリットとして次の5つが挙げられます。
- 導入やランニングにコストがかかる
- 情報漏洩のリスクがある
- インターネット環境が常に必要
- 一定のPCスキルが必要になる
- 院内における運用体制の変更が伴う
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.導入やランニングにコストがかかる
電子カルテは導入費用を皮切りに、維持費やサーバー更新費などの定期的なランニングコストがかかります。したがって、少なからず固定費が増大し、病院経営に影響を及ぼしてしまうでしょう。
費用対効果を見定めながら、電子カルテを選ばなければなりません。
2.情報漏洩のリスクがある
電子カルテは多くの個人情報が含まれているため、ネットワークを介して使用する場合、サイバー攻撃を受けて情報漏洩のリスクがあります。また、スタッフがUSBメモリを持ち出し、そこから情報漏洩してしまう可能性もゼロではありません。
したがって、セキュリティ対策を施したり、院内に患者データを残さない電子カルテを導入したりするといった情報漏洩対策を行う必要があります。
関連記事:【医療機関向け】サイバー攻撃から電子カルテを守る!ランサムウェア被害を防ぐセキュリティ対策を紹介/安全なクラウド型電子カルテの選び方とセキュリティの基礎知識
3.インターネット環境が常に必要
クラウド型電子カルテの場合、インターネットを介してサーバーにデータ保存・共有されます。つまり、インターネット環境が常に必要なため、インターネット環境が切れてしまうと、カルテ入力に支障が出てしまうでしょう。
したがって、ネットワークが切れた時の対処法も考えておく必要があります。
4.一定のPCスキルが必要になる
電子カルテもデジタルツールの1つであるため、電子カルテを問題なく取り扱うには一定のPCスキルが不可欠です。紙カルテに慣れている、スタッフのPCスキルが十分ではない場合、教育や研修を実施してPCスキルを向上させる必要があります。
新規開業の場合はPCスキルも重視して採用することも1つの手段です。既にPCスキルを持っているため、教育や研修の手間を省くことができ、スタッフの育成コストを抑えられます。
5.院内における運用体制の変更が伴う
電子カルテの導入によってカルテの記載方法が変わったり、電子カルテで発行できる帳票の変更が発生したりする可能性が高く、電子カルテを導入すると院内における運用体制を変更しなければなりません。そのため、電子カルテで対応できる業務、対応できない業務を確認し、それぞれの運用について取り決めをすることが大切です。
ただし、いきなりすべての業務プロセスを変更すると現場の混乱を招く恐れがあるため、注意が必要です。
関連記事:医療事務にとって電子カルテが難しい理由とは?電子カルテを導入するメリットも解説電子カルテを導入するデメリットへの対策

電子カルテのデメリットを解決する対策として次の4つが挙げられます。
- メーカーのサポート体制を確認する
- 全体費用を考慮する
- 導入目的を明らかにする
- 提供形態を確認する
それぞれ詳しくみていきましょう。
メーカーのサポート体制を確認する
メーカーのサポート体制を確認しましょう。IT人材が乏しい病院やクリニックの場合、トラブルに上手く対応できず、業務効率が悪化する恐れがあります。
入院患者を受け入れていて24時間体制の病院の場合は「カスタマーサポートが24時間対応なのか」や「拠点が近くにあってすぐに駆けつけることができるか」といった点も確認しておく必要があるでしょう。
また、電子カルテを活用するためにはセキュリティ対策が重要なため、最初の設定でしっかりと対策しなければなりません。サポート体制がないもしくは不十分な場合、別途ITに強い人材を採用したり、専門家に依頼したりする必要があります。
充実したサポート体制が整備されているかどうかは非常に大切です。
全体費用を考慮する
電子カルテを導入する場合、全体費用を考慮して導入を検討しなければなりません。電子カルテはハードウェアの購入ならびにシステム構築など、初期費用が高額となるため、そちらに目が行きがちです。
しかし、導入費用だけでなく、システム運用におけるライセンス料や保守・管理費用などのランニングコストがかかる場合もあります。したがって、初期費用やランニングコスト含む全体費用を把握したうえで導入を検討しなければなりません。
導入目的を明らかにする
電子カルテの導入には多額な初期費用がかかります。そのため、システムを導入したものの必要な機能がなく、システムの変更を余儀なくされた場合、余計な費用がかかってしまうでしょう。
導入目的を明確にしておけば、必要な機能がはっきりするため、自院にあったシステムを選ぶことができ、システム変更による手間や出費を回避できます。
提供形態を確認する
提供形態を確認することも重要です。「クラウド型」は初期費用や運用コストが抑えられて安価に使用できる一方、カスタマイズ性に欠けます。
「オンプレミス型」は電子カルテのカスタマイズ性に優れている一方、導入費用や運用コストが高額です。そのため、システムの特性を十分に理解し、自院がどこを重視するか検討したうえでシステムを選びましょう。
問題点を解決するならクラウド型電子カルテ

電子カルテの問題点は、コストがかかることや一定のPCスキルが必要であることです。
しかし、これらの問題点はクラウド型電子カルテを導入することで解決できる可能性があります。ここでは、オンプレミス型の電子カルテではなく、クラウド型を選択することで、どのように問題点を解決できるかを解説します。
関連記事:クラウド型電子カルテの特徴を徹底解説!メリットや注意点まで紹介します
導入やランニングを抑えられる
クラウド型電子カルテは、オンプレミス型と比較して導入やランニングにかかるコストを抑えられる傾向があります。サービスによって費用は異なりますが、相場は次のとおりです。
初期導入費用 |
月額費用 |
|
| クラウド型 |
数十万〜200万円 |
2〜5万円 |
| オンプレミス型 |
250万〜400万円 |
2〜3万円 |
オンプレミス型は院内にサーバーを設置したり、電子カルテが入ったパソコンを購入したりといった導入コストがかかることが一般的です。しかし、クラウド型の場合は外部企業が管理するサーバーを使うため院内に設置不要で、パソコンの購入やリースも必要ありません。
また、オンプレミス型は電子カルテの耐用年数によって一定期間で更新が必要なため、更新コストも加味しなくてはなりません。クラウド型は月額利用料がかかりますが、オンプレミス型を選ぶよりコスト削減につながる可能性があります。
関連記事:電子カルテの導入費用相場とは?オンプレミス型とクラウド型で徹底比較!
更新・メンテナンス作業の負担軽減
クラウド電子カルテはサーバを企業側で管理しているため、更新やメンテナンスの際に医療機関側で作業が発生することはありません。
オンプレミス型電子カルテの場合は、CD-ROMを用いた更新作業を自身で行ったり、担当者が医療機関に訪問してメンテナンスしたりする必要がありましたが、クラウド電子カルテは常に最新の状態で電子カルテを利用できるというメリットがあります。
外部のサーバーにバックアップが残る
クラウド型電子カルテでは、院内にサーバーを設置する必要がないため、保管スペースが不要です。また、日常的な保守・管理の手間も軽減され、管理コストや人員の削減に寄与します。
クラウド型の電子カルテがおすすめ

オンプレミス型の電子カルテだと導入やランニングコストがかかってしまうため、少なからず固定費が増えてしまいますし、保守・管理の手間もかかります。比較的安価かつ保守・管理の手間を省いて電子カルテを使用したいのならばクラウド型の電子カルテがおすすめです
ただし、どの電子カルテであっても「導入やランニングにコストがかかる」「情報漏洩のリスクがある」といったデメリットがあります。そのため、電子カルテを上手に運用していくには「メーカーのサポート体制を確認する」や「提供形態を確認する」などの対策が欠かせません。