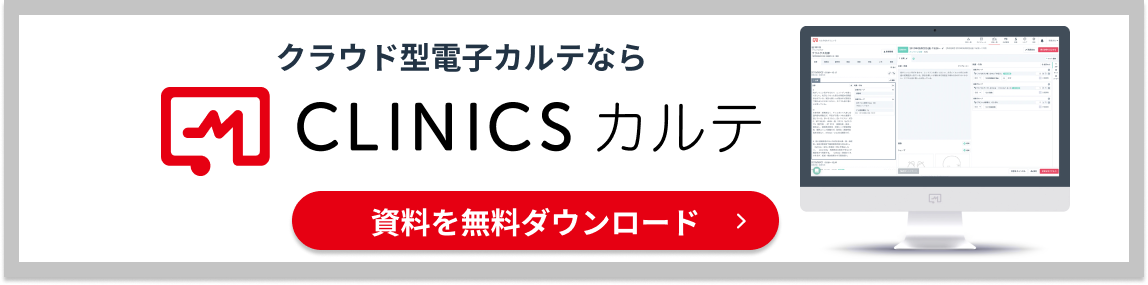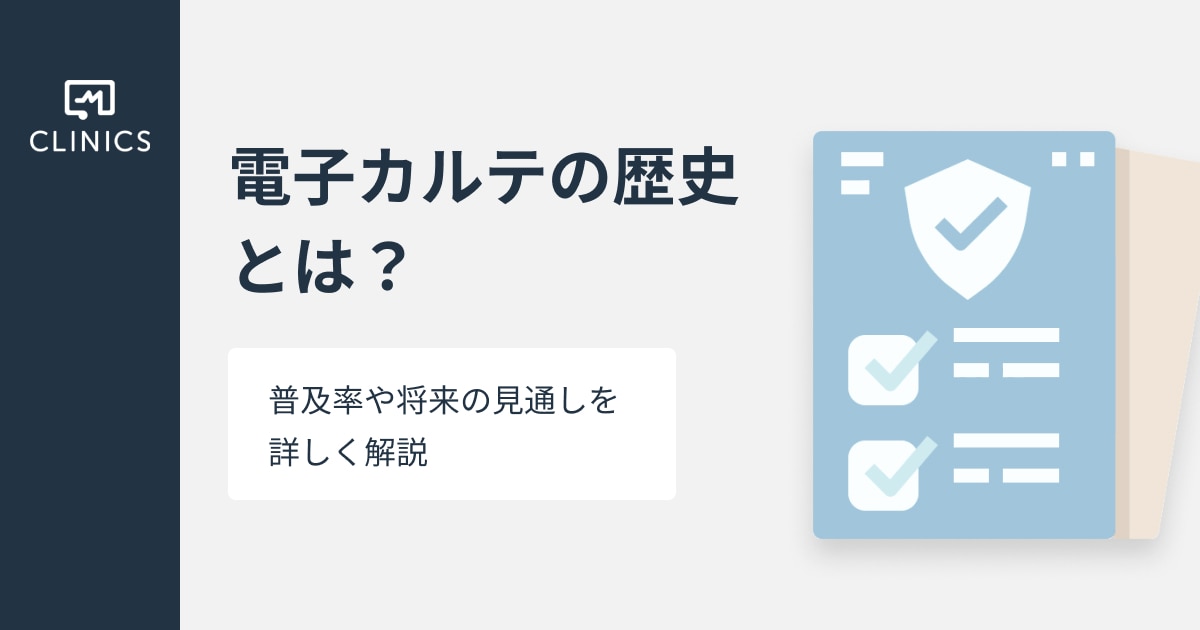
電子カルテの歴史とは?普及率や将来の見通しを詳しく解説
「電子カルテってどれくらい普及しているの?」
「電子カルテの歴史を知りたい」
病院・クリニックで働く医療関係者の方で、上記のような疑問を抱えている方も少なくありません。電子カルテの普及が進んでいるといっても、実際にどれくらいの医療機関が導入しているかわからないのではないでしょうか。
当記事では電子カルテの歴史や普及率、電子カルテを導入するメリットを紹介します。当記事を読むことで、電子カルテが普及した背景や導入するメリットが明確になるでしょう。
目次[非表示]
- 1.電子カルテの歴史とは?
- 2.電子カルテの普及率と将来の見通し
- 3.電子カルテを導入する4つのメリット
- 3.1.1.ヒューマンエラーを未然に防ぐ
- 3.2.2.スタッフの業務効率がアップする
- 3.3.3.保管スペースに困らない
- 3.4.4.情報共有がスムーズになる
- 4.電子カルテを導入する3つのデメリット
- 4.1.1.導入コストがかかる
- 4.2.2.操作方法に慣れる必要がある
- 4.3.3.震災時に使えない可能性が高い
- 5.電子カルテ歴史に関するよくある質問
- 5.1.質問1.電子カルテの課題とは?
- 6.まとめ
電子カルテの歴史とは?

電子カルテが誕生したのは、1999年です。
1999年より前から、レセコンの誕生など医療現場でのIT化は進んでいました。現代になり、クリニックにサーバーを設置する必要のないクラウド型電子カルテが開発されています。
そのため、狭くても電子カルテを導入できるクリニックが増えてきているのが現状です。
電子カルテの普及率と将来の見通し

令和2年度の電子カルテ普及率は、以下の通りです。
一般病院 |
400床以上 |
200〜399床 |
200床未満 |
一般診療所 |
|
令和2年 |
57.2 % (4,109/7,179) |
91.2 % (609/668) |
74.8 % (928/1,241) |
48.8 % (2,572/5,270) |
49.9 % (51,199/102,612) |
一般病院の電子カルテの普及率は「400床以上」「200〜399床」に比べて下回っています。しかし、平成29年度と比較すると普及率は向上しているため、今後も普及していくでしょう。
今まで導入費用・運用費用が高いため、電子カルテを導入できなかったクリニックや病院もあります。近年、電子カルテの開発が進み費用の安い電子カルテも登場しているので、将来的に普及率は向上していくでしょう。
引用:電子カルテシステム等の普及状況の推移
電子カルテを導入する4つのメリット

電子カルテを導入するメリットは、以下の4つです。
- ヒューマンエラーを未然に防ぐ
- スタッフの業務効率がアップする
- 保管スペースに困らない
- 情報共有がスムーズになる
それぞれ詳しく紹介します。
1.ヒューマンエラーを未然に防ぐ
電子カルテの導入により、スタッフのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
紙カルテを利用している場合、データや患者情報を誤って記入するケースも少なくありません。また、人によって文字に癖があるためカルテが読みにくいという問題も起こりやすい傾向です。
電子カルテを導入すると、誤字脱字も防げる上にデータ入力のミスも起こりづらくなるのです。患者に対して、データや画像を用いた説明もできるため安心して診療を受けてもらいやすくなるでしょう。
2.スタッフの業務効率がアップする
スタッフの業務効率がアップできるのが、電子カルテ導入のメリットです。
電子カルテがあると、効率よくカルテを記載したり処方したりできるようになります。また、診療情報提供書など、文書作成の手間も軽減可能です。
会計業務もスムーズになるため、患者の待ち時間も削減され満足度向上にもつながります。
3.保管スペースに困らない
電子カルテを導入すれば、カルテの保管スペースに困りません。
紙カルテを使用している場合、紛失を防ぐために保管場所を確保する必要があります。一方、電子カルテの場合はサーバー上でデータを保管できるため、保管場所は不要です。
クリニックによっては、スペースがなくカルテの保管に苦労するケースもあるでしょう。
電子カルテを導入すると、クリニックが狭くてもカルテを保管できるようになります。必要な情報もすぐに検索できるため、業務効率もアップできるでしょう。
4.情報共有がスムーズになる
情報共有がスムーズになるのが、電子カルテ導入のメリットです。
電子カルテは、入力した情報がすぐに反映されます。紙カルテの場合は、誰かがカルテを持ち出していると確認したいタイミングで情報を得られません。
患者情報をリアルタイムで収集し、最適な医療サービスを提供するためにも電子カルテの導入は必要不可欠です。
電子カルテを導入する3つのデメリット

電子カルテを導入するメリットは、以下の3つです。
- 導入コストがかかる
- 操作方法に慣れる必要がある
- 震災時に使えない可能性が高い
それぞれ詳しく紹介します。
1.導入コストがかかる
電子カルテは、導入コストがかかるのがデメリットです。
電子カルテの種類はさまざまで、機能も異なります。特にクリニック内にサーバーを設置するのが必要な、オンプレミス型電子カルテは導入コストも高額です。
しかし、近年開発が進み導入コストの安い電子カルテも販売されています。電子カルテの導入コストを抑えたい方は、複数の電子カルテを比較して予算内で利用できるものを探しましょう。
2.操作方法に慣れる必要がある
電子カルテは、操作方法に慣れる必要がある点がデメリットです。
スタッフのなかには、パソコンをはじめとした電子機器の操作が苦手な方もいるでしょう。特に高齢の医師などは、紙カルテに慣れているため電子機器の操作が苦手なケースが多いかもしれません。
電子カルテを導入しても、慣れていないとすぐに快適な操作はできないでしょう。電子カルテの操作に慣れるには「定期的な研修を実施する」「メーカーから操作方法を学ぶ」という方法が効果的です。
上記の方法で、電子カルテの操作に慣れると業務効率がアップするでしょう。
3.震災時に使えない可能性が高い
電子カルテの種類によっては、震災時に使えない可能性があります。
電子カルテは、電子機器で構成されているのが特徴です。そのため、地震や停電が起きた場合に使用できないケースも少なくありません。
紙カルテへの移行方法をスタッフ間で浸透させていると、震災時にも患者に適切な医療を提供できるようになるでしょう。
電子カルテ歴史に関するよくある質問

電子カルテ歴史に関するよくある質問は、以下の通りです。
- 電子カルテの課題とは?
疑問を解消できるように、それぞれ詳しく回答します。
質問1.電子カルテの課題とは?
高額な費用がかかる点が、電子カルテの課題です。
電子カルテは、導入費用に加えて運用費用も必要です。導入・運用費用を考えた際に、規模の小さいクリニックや病院では導入できないケースもありました。
しかし、電子カルテは年々開発が進んでおり、費用が安い電子カルテも販売されています。必要最低限の機能が搭載されて、かつ低額で利用できる電子カルテもあるため将来的には課題は解消されるでしょう。
今まで電子カルテを導入できなかったクリニックも、予算に適した電子カルテを見つけやすくなります。
まとめ

ここまで、電子カルテの歴史や普及率、電子カルテを導入するメリットを紹介しました。
医療現場のIT化は1970年代ごろから始まっており、レセコンなどが開発されていました。電子カルテは、1999年に登場し年々普及率も増加しています。
電子カルテの開発は毎年進んでおり、低額で利用できる機種も販売されているのが現状です。電子カルテの導入により、スタッフの業務効率をアップでき情報共有もスムーズになります。
患者により質の高い医療を提供するためにも、電子カルテの導入は必要不可欠といえるでしょう。電子カルテの導入を検討している方は、当記事を参考に自院に最適な機種を選んでみてください。