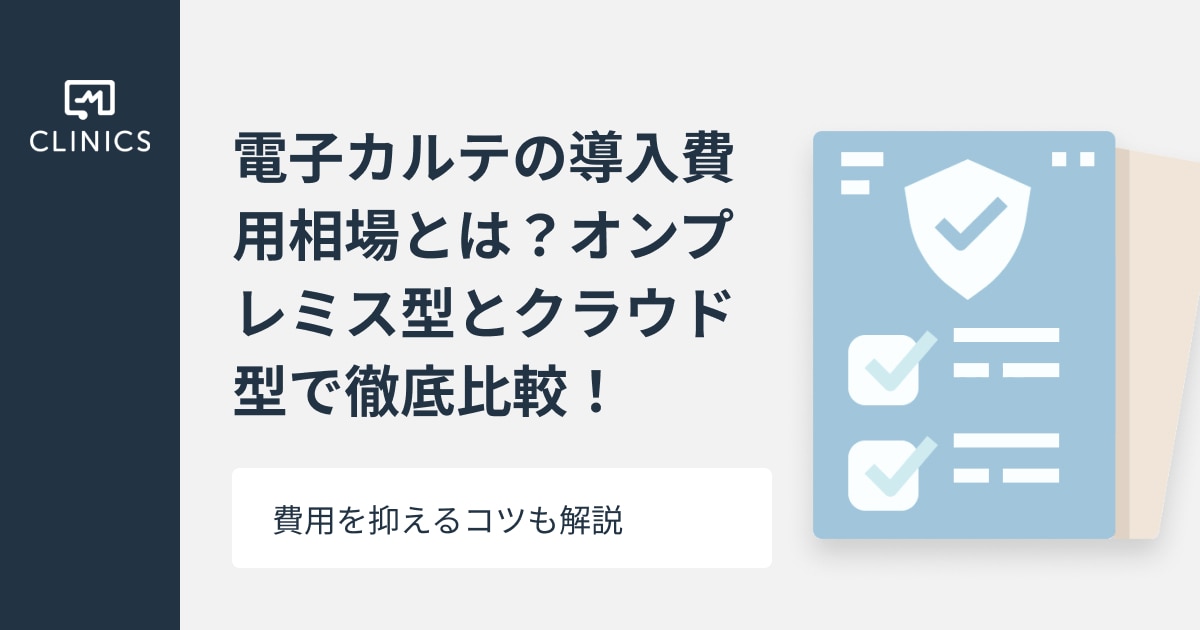
電子カルテの導入費用相場とは?オンプレミス型とクラウド型で徹底比較!
電子カルテの導入費用は実装される機能やサポート体制、システムなど、さまざまな要因で変化します。そのため、事前に見積もりを取得して複数の業者を見比べたうえで、導入する電子カルテを選ばなければなりません。
そこで、当記事では電子カルテの導入費用相場をオンプレミス型とクラウド型で比較しながら詳しく紹介します。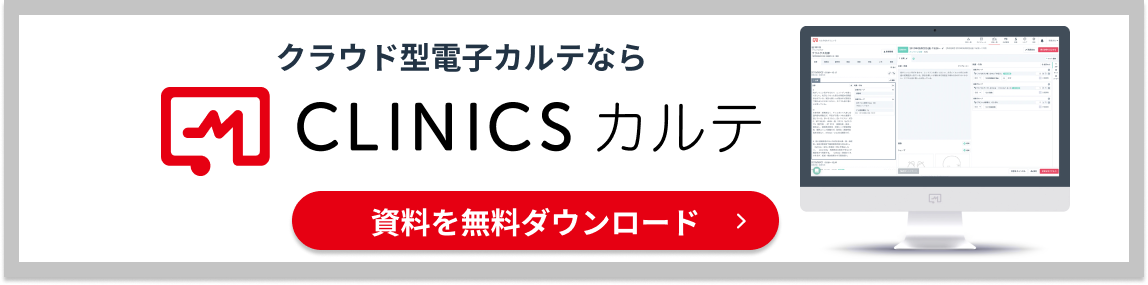
目次[非表示]
- 1.クリニックにおける電子カルテの導入費用相場とは
- 1.1.オンプレミス型の場合
- 1.2.クラウド型の場合
- 2.電子カルテの導入や運用に必要な費用の内訳
- 2.1.初期費用
- 2.2.月額費用
- 2.3.周辺機器の購入費用
- 2.4.サポート費用・メンテナンス費用
- 2.5.その他の費用
- 3.電子カルテの導入費用に影響する5つの要素
- 3.1.1.レセコンの導入形態
- 3.2.2.導入サポートの有無
- 3.3.3.カスタマイズの内容
- 3.4.4.ライセンス数
- 3.5.5.トラブルへの対策範囲
- 4.電子カルテの導入費用を抑える3つのコツ
- 4.1.1.総コストを算出して比較する
- 4.2.2.複数の業者から見積もりを取得する
- 4.3.3.助成金や補助金の利用を検討する
- 5.まとめ
クリニックにおける電子カルテの導入費用相場とは
クリニックにおける電子カルテの導入費用は提供する業者によってさまざまです。無料で導入できるものもあれば、1,000万円を超えるケースもあります。ただし、平均的な相場は「300万円程度」となる場合が多いでしょう。
ここまで価格に幅があるのは、選ぶ電子カルテの「システム」に関係しており、大きく次の2つに分けられます。
- オンプレミス型
- クラウド型
システムによってどれほど導入費用が異なるのか、それぞれみていきましょう。
オンプレミス型の場合
「オンプレミス型」とは、サーバーやソフトウェアなどを自院に設置・運用するタイプのシステムです。電子カルテやレセプトなどにそれぞれサーバーを用意することを前提にする場合、オンプレミス型の初期費用は「約300万〜500万円」が必要になります。
また、別途レセプトを用意する場合はさらに「約150〜200万円」の費用が必要です。さらに、パソコンのリプレースが発生する度に導入費用と同額程度の費用が発生します。
クラウド型の場合
「クラウド型」とは、サービスを提供する業者が用意している環境に接続して運用するタイプのシステムです。クラウド型の場合は院内にあるパソコンでそのままサービスを利用できるため、導入費用を大きく抑えられます。
ただし、パソコンが不足していたり老朽化していたりする場合は買い替えが必要となり、別途費用が生じる可能性もあります。
電子カルテの導入や運用に必要な費用の内訳

電子カルテは、医療現場の効率化と診療の質向上に大きく寄与する一方で、導入や運用には一定のコストがかかります。
ここでは電子カルテの導入・運用に必要な費用を詳細に解説し、それぞれの内訳について具体的に紹介します。
初期費用
初期費用には、システムのライセンス費用が挙げられます。多くの電子カルテシステムでは、クリニックや病院の規模、利用するユーザー数に応じて料金が変動します。小規模クリニックの場合、無料のものもありますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。
既存の紙カルテや他のシステムからのデータ移行には専門的な作業が必要であり、サポートを受けるには追加のコストが発生することがあります。スタッフへのトレーニング費用も見逃せません。導入時に行う研修やマニュアル作成にもコストがかかります。
月額費用
クラウド型の場合、システム利用料として月額費用が課されます。月額費用はシステムの使用権だけでなく、データのクラウド保管料やセキュリティ管理費用が含まれることが多いです。費用は、1ユーザーあたり数千円から数万円程度が一般的です。
オンプレミス型(院内設置型)のシステムの場合は、月額費用は発生しないことが多いものの、サーバーの維持管理や運用にかかる間接的なコストがかかる点に注意が必要です。
周辺機器の購入費用
電子カルテの導入には、周辺機器の購入費用も必要です。具体的には、診察室や受付で使用するパソコンやタブレット、バーコードリーダー、スキャナーなどの機器が挙げられます。特に、診療所や病院内で複数台の機器を使用する場合、それぞれの購入費用がかさむことがあります。
プリンターやラベルプリンターといった印刷機器の費用も見逃せません。処方箋や患者への説明資料を印刷する際に必要となるため、診療規模に応じて適切な機器を選定することが重要です。
サポート費用・メンテナンス費用
電子カルテを安定して運用するためには、システムのサポート費用やメンテナンス費用が欠かせません。サポート費用は、システムの操作に関する問い合わせ対応やトラブル時の支援にかかる費用です。
メンテナンス費用としては、システムのバージョンアップやセキュリティアップデートが挙げられます。また、システム障害が発生した場合の復旧作業や部品交換にもコストがかかります。
その他の費用
電子カルテの運用にはほかにも予期せぬ費用が発生することがあります。例えば、検査機器や診療報酬請求システムとの連携には、一般的に専用のソフトウェアやカスタマイズが必要です。
また、外部の薬局や他院との情報共有を行う際のデータ連携費用も発生する可能性があります。
電子カルテの導入費用に影響する5つの要素
電子カルテの導入費用に影響する要素として次の5つが挙げられます。
- レセコンの導入形態
- 導入サポートの有無
- カスタマイズの内容
- ライセンス数
- トラブルへの対策範囲
導入費用が想定よりも高くなるような事態を防ぐためにも、それぞれの要素について詳しくみていきましょう。
1.レセコンの導入形態
レセコンの導入形態には「一体型(内包型)」と「連携型」の2種類があります。
「一体型」は電子カルテとレセコンが一緒になったタイプで、導入費用は高くなりやすいです。ただし、設定や互換性によるトラブルが少なく、導入費用が高くなってもレセコン一体型を選ぶ医療機関は少なくありません。
一方「連携型」はレセコンであるORCAと連携可能な電子カルテのことで、一体型に比べると導入コストを抑えやすい傾向にあります。しかし、別システムとの連携や設定が必要な場合は、導入支援を受けるための費用が必要になるケースもあります。
2.導入サポートの有無
導入サポートの有無によっても導入費用が変わります。しかし、電子カルテの導入当初はもちろんのこと、ITに関して詳しいスタッフが少ない医療機関ではサポートがないとかえって作業時間が増える事態になりかねません。
何らかの形で導入サポートを利用できれば、設定や操作について適宜サポートを受けることができます。スムーズな電子カルテの導入を目指す場合は、費用がかかっても導入サポートのある電子カルテを選んだ方がよいでしょう。
3.カスタマイズの内容
電子カルテによっては、「フォーマットの変更」や「記入項目の追加」といったように、医療機関に合わせてカスタマイズできるシステムもあります。
ただし、カスタマイズの内容によっては従来の導入費用よりも高くなります。また、カスタマイズに対する開発時間も要するため、電子カルテの導入時期が伸びてしまう点には注意が必要です。
4.ライセンス数
ライセンス数も導入費用が変わる要素の1つです。例えば「クライアントライセンス」と呼ばれるライセンス体系の場合、パソコンの台数によって費用が決まります。3台のパソコンで同時ログインする場合、3つのライセンスが必要です。
一方「ユーザーライセンス」と呼ばれるライセンス体系の場合、利用人数で料金が決まります。6人のスタッフが同時ログインする場合は、6つのライセンスを用意しなければなりません。
ライセンス数は医療機関の規模に比例するため、大規模な医療機関であるほど導入費用は高くなります。
5.トラブルへの対策範囲
災害やシステム障害といったトラブルが発生したからといって、診察を止めることはできません。むしろ、大きな災害が発生した場合は被災者の手当てのために、積極的に患者を受け入れる必要があります。
ただし、選ぶシステムによってトラブルへの対策範囲は異なるのも事実です。もちろん、対策範囲が広いほどに導入費用も高くなる傾向にあります。
電子カルテの導入費用を抑える3つのコツ
電子カルテの導入費用を抑えるコツとして次の3つが挙げられます。
- 総コストを算出して比較する
- 複数の業者から見積もりを取得する
- 助成金や補助金の利用を検討する
自院との相性がよく費用対効果の高い電子カルテを選ぶためにも、それぞれの内容について詳しく解説します。
1.総コストを算出して比較する
導入費用だけではなく、総コストを算出して比較してみてください。毎月かかる運用コストや周辺機器の整備費用なども含め、年間でどれくらいの費用を要するかを把握する必要があります。
また、電子カルテの利用人数が増加すると、その分の月額料金も増加します。将来的に規模拡大を見込む医療機関では、利用者の増加も含めた予測コストも算出して比較しましょう。
2.複数の業者から見積もりを取得する
電子カルテの導入費用を含む総コストを把握するには、電子カルテを提供する業者から見積もりを取得する必要があります。
そして、複数の業者から見積もりを取得し、最も費用対効果の高い業者を選ぶことが大切です。ただし、異なる条件で見積もりを取得しても正確な比較ができません。できる限り条件を揃え、各項目ごとに比較できる状況を作りましょう。
3.助成金や補助金の利用を検討する
導入費用がネックとなって電子カルテの導入が難しい場合は、助成金や補助金の利用も検討してみてください。医療情報の連携推進を目的に、経済産業省では「IT導入補助金」といった補助金制度を設けています。
給付条件に合致して申請が通れば、電子カルテの導入費用負担を大きく軽減できます。ただし、補助金は導入後の支給となるのが一般的であるため、一旦は費用を負担しなければならない点には注意が必要です。詳しくは次の公式ページを確認してみてください。
参考:IT導入補助金
まとめ
電子カルテは「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類があり、それぞれに導入費用が大きく異なります。また「レセコンの導入形態」や「導入サポートの有無」といった部分を含めるかによっても変化します。
特に、規模の大きい医療機関は利用するスタッフが多い分、多くのライセンス数が必要です。そのため、導入費用だけでなく総コストを算出して複数のシステムで比較検討しましょう。さらに、助成金や補助金も上手く利用しながら、導入費用を抑えてみてください。













