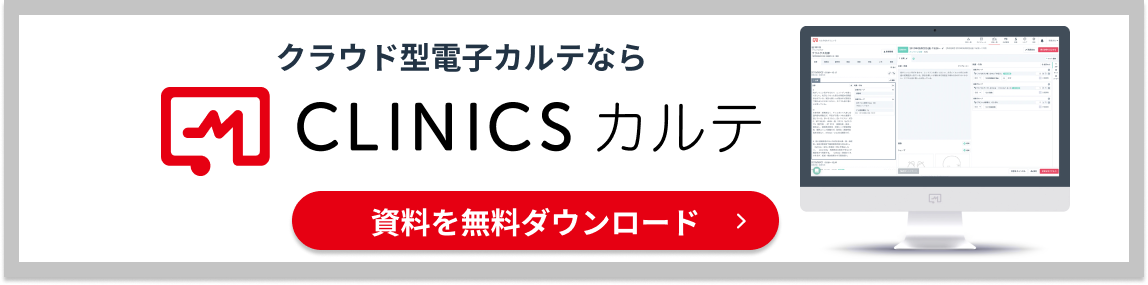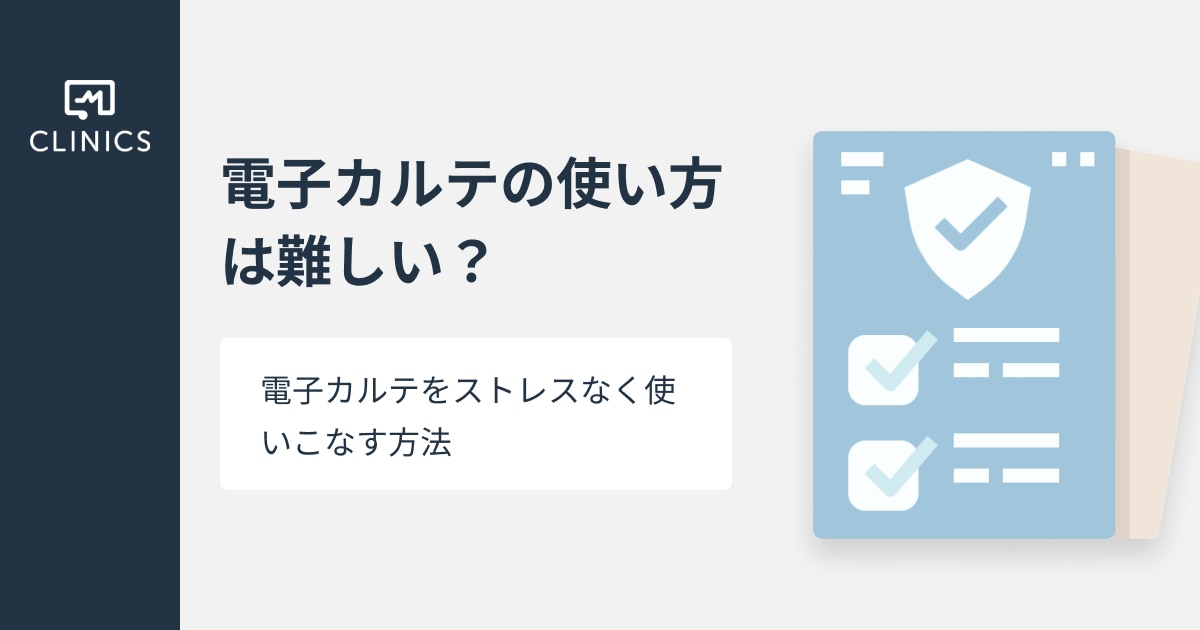
電子カルテの使い方は難しい?便利な機能やストレスなく使いこなす方法を紹介
「使い方がよく分からない」「操作が難しそう」という理由から電子カルテの導入に踏み込めないクリニック・医師の話もしばしば耳にします。しかし、最近の電子カルテの中には非常に分かりやすく、利用者をしっかりサポートしてくれる豊富な機能があるものも多くあります。この記事では、電子カルテの便利な機能と、電子カルテを使いこなすためのポイントについてご紹介します。
目次[非表示]
- 1.電子カルテの操作は難しい?
- 2.電子カルテってそもそも何?
- 3.「使い方が難しい」は誤解! 電子カルテの便利な機能
- 3.1.(1)「直感的」に操作できる画面設計
- 3.2.(2)電子カルテ入力がスムーズになる「セット登録機能」や「テンプレート」
- 3.3.(3)慣れた手書き入力と便利なタッチ操作
- 3.4.(4)過去の診療記録も一瞬で見つかる「検索機能」
- 4.電子カルテの主な使い方
- 4.1.カルテを新規作成する
- 4.2.診察内容を入力する
- 4.3.確認して保存する
- 5.電子カルテを扱えるようになるには?
- 5.1.情報セキュリティについて理解する
- 5.2.基本的な仕組みと使い方を学ぶ
- 6.まとめ
電子カルテの操作は難しい?

長年紙カルテ(診療録)を使っていたり、あまりパソコンに慣れていない方は、電子カルテは操作が難しいというイメージを持たれているかもしれません。しかし、ある程度の慣れは必要ですが、電子カルテは『簡単』なのです。むしろ電子カルテには入力をサポートするさまざまな機能が備わっている分、慣れてしまえば紙カルテよりも楽にカルテ管理ができるとさえ言われています。
電子カルテってそもそも何?
ご存知の通り、「カルテ」とは患者の診察内容や診断結果、処方薬や経過について記載した文書です。近年ではパソコンやタブレットなどを用いて作成し、電子的なデータとして保存できる「電子カルテ」が普及してきました。
電子カルテは、パソコンで患者の診察内容を打ち込むだけでデータが残ります。それにより、情報整理の時間短縮ができるのは電子カルテならではのメリットと言えるでしょう。
電子カルテには種類がありますので、自院の運用に適した電子カルテを選ぶ必要があります。システムごとに機能や設定は千差万別です。デモンストレーションをしてみて、入力操作がしやすいかやレスポンスの速さなども確かめることで、実際の運用がスムーズに始められます。診療スタイルに合ったものか確認しましょう。
「使い方が難しい」は誤解! 電子カルテの便利な機能

パソコン操作に苦手意識があっても、電子カルテは実は難しくないのです。ほとんどの電子カルテは、パソコンが苦手な人でも操作しやすいように設計され、使いやすさを考えた便利な機能がたくさんあります。ここでは、電子カルテの便利な機能について紹介します。
(1)「直感的」に操作できる画面設計
かつての電子カルテは、操作が面倒だったり、わかりにくい設計だったりして、不満が多かったのも事実です。カルテは一日のなかで接触する機会が非常に多いため、電子カルテの操作性が悪ければ悪いほどストレスがたまってしまうでしょう。
最近の電子カルテは操作が簡単なだけでなく、直感的な操作が可能な仕様のものがたくさんあります。
- 必要な診療情報が一つの画面上におさめられている
- 次にすべき操作手順が示されている
- ひとめで意味や機能を理解できるアイコンが多く使われている
など、機能が充実しているのです。直感的な操作が可能な電子カルテを導入することによって、時間短縮にもつながるでしょう。
(2)電子カルテ入力がスムーズになる「セット登録機能」や「テンプレート」
よく使う文章を「定型文」として登録しておくことができます。たとえば、「所見 頭痛:なし 発熱:なし 咳:なし」と登録しておくだけで、すべて入力しなくてもこの文が出てくることになります。
また、カルテ入力用のテンプレートを使ってカルテ入力ができるので、項目にチェックをしたり、入力欄に数値を入力するだけで入力が終了します。医療現場では実にたくさんの文書を作成しますので、カルテ入力がスムーズになることは、そのまま医師の手間と時間の軽減に直結するでしょう。
(3)慣れた手書き入力と便利なタッチ操作
タッチペンを使って、パソコンの画面に手書きでカルテを入力できる「手書き入力機能」もあります。紙カルテと同じ感覚でカルテを入力できますから、キーボード入力に慣れていない方でも電子カルテに親しみやすくなるでしょう。
また、電子カルテの操作を、キーボードではなく画面のボタンをタッチしてできる「タッチ機能」のある電子カルテもあります。タッチペンやタッチパネルの使い方は覚える必要がありますが、基本的には直感的な操作でできますので、それほど身構える必要はないでしょう。
(4)過去の診療記録も一瞬で見つかる「検索機能」
過去の情報を探す際、膨大な量のカルテの中から一人のカルテを探し出すのはたどり着くまでに時間がかかり大変という声を耳にします。しかし、電子カルテの「付箋機能」や「検索機能」を使えば、ドクターが、検索作業や入力作業に煩わされることなく、重要な部分へ一瞬でたどり着けるのです。
ふせん機能は、ドクターがカルテの中で重要と感じたページのいくつかに「ふせん(A)」を指定できます。ドクターが直観的に「気になった」テーマにタグ付けできるので、検索も容易になるということです。
電子カルテの主な使い方

電子カルテの基本的な使い方は次のとおりです。
カルテを新規作成する
診察内容を入力する
確認して保存する
各ステップを解説します。
カルテを新規作成する
まず患者の氏名、年齢、性別、住所、連絡先、保険情報などを入力します。中には、患者IDを自動生成する電子カルテもあります。
次に、患者の既往歴や家族歴、アレルギー情報、現在の服薬状況などの医療歴を入力しましょう。電子カルテの多くは、設定をテンプレート化しておくことが可能です。定型的な質問項目をあらかじめ設定しておくことで、入力の手間を省けます。
電子カルテのシステムによっては、手書き入力や音声入力に対応しているものもあり、紙カルテに慣れた医師でもスムーズに移行できるよう工夫されています。
診察内容を入力する
診察中には、患者から得た情報や診察結果をカルテに入力します。まず、患者が感じている症状や不調(主観的情報)を記録し、その後、医師が診察や検査を通じて得た客観的な情報を入力します。
電子カルテでは、過去の診療記録や検査結果をすぐに参照できる機能があるため、診察中に必要な情報を確認しながら効率的に入力を進めることが可能です。
確認して保存する
診察内容を入力したら、最後に内容を確認して保存します。入力内容に間違いや抜けがないかを確認することが重要です。特に、処方箋や検査の指示内容など、のちの治療や診療に影響を与える部分については慎重に見直します。
電子カルテには、多くの場合、自動保存機能が備わっているため、入力内容が突然消える心配はほとんどありません。ただ、診察が終わる前に必ず保存ボタンを押して、全体を確定させておきましょう。保存した内容は、医師だけでなく看護師や事務スタッフとも共有されるため、全体の医療チームでスムーズに連携できます。
電子カルテを扱えるようになるには?
多くの機能があり、活用もしやすそうな電子カルテ。扱い方も難しくはなさそうです。ではこの便利な電子カルテを「正しく扱える」ようになるには、どうすればいいのでしょうか?ここからは、これから電子カルテを導入する人が知っておきたい電子カルテの正しい扱い方を2つのポイントに絞って紹介します。
情報セキュリティについて理解する
電子カルテに登録され、参照・利用されるデータは「誰でも見て良いもの」ではありません。それは、電子カルテには「患者さんの診療に対して発生するデータすべて」が含まれているからなのです。これらの情報は非常に秘匿性が高く、必ず守られるべき情報です。
しかしその一方で、「見ても良い人はいつでも正しいデータが見られる」必要があります。患者さんは病状やその時の状況によって、かかりつけのクリニックと、大きな病院とを使い分けています。 こういった場合、大きな病院での手術の内容を、かかりつけのAクリニックの医師が見れるようにすることで、医療の質が向上するとされています。
そこで電子カルテ運用・取り扱いに必要になるのが、セキュリティに関する知識です。
- いつ、誰が、どのデータにアクセスできるのか
- どのデータなら見ても良いと判断する人はだれか
一般的なクラウド型電子カルテではサービス事業者やサーバーの管理者によって、不正侵入検知システム(IDS)やファイアウォールといったセキュリティが設けられていますから、流出の恐れは少ないですが、「USBメモリから患者の個人情報が漏えい」「病院で不正アクセス事件」などがニュースとして取り上げられることもあります。
電子カルテの扱いにおいて、セキュリティの確保のために、複数のセキュリティ対策を各医院で行っていくことが必要なのです。
基本的な仕組みと使い方を学ぶ
電子カルテを導入するなら、システムの特性も理解しておく必要があります。電子カルテの場合、古いデータも新しいデータも、すべて患者さんのIDを使って呼び出すことになります。
電子カルテの導入を検討するときは、自院の傾向や運用方法などを鑑み、一度試験導入をしてみるといいでしょう。試しに使ってみることで操作性などが分かり、忌避感も軽減されるはずです。
まとめ
電子カルテは非常に分かりやすく進化を遂げています。今後の医療体制は、より柔軟な対応ができる診療方法を求められるようになります。電子カルテはこれからも推進されていくと予想されます。電子カルテを導入して、スムーズな医療シーンを作っていきましょう。