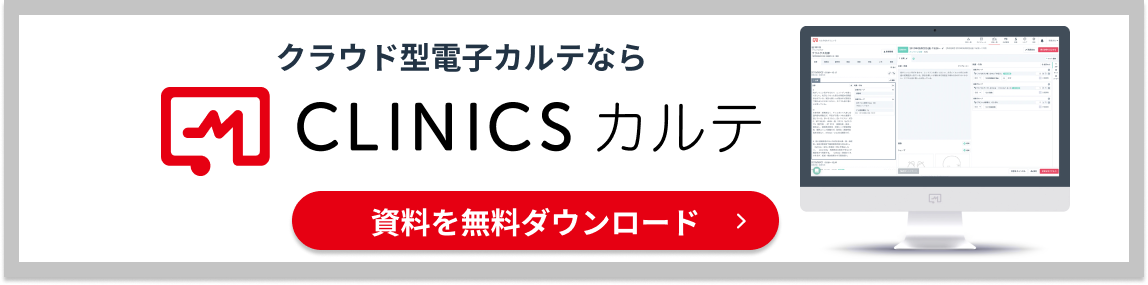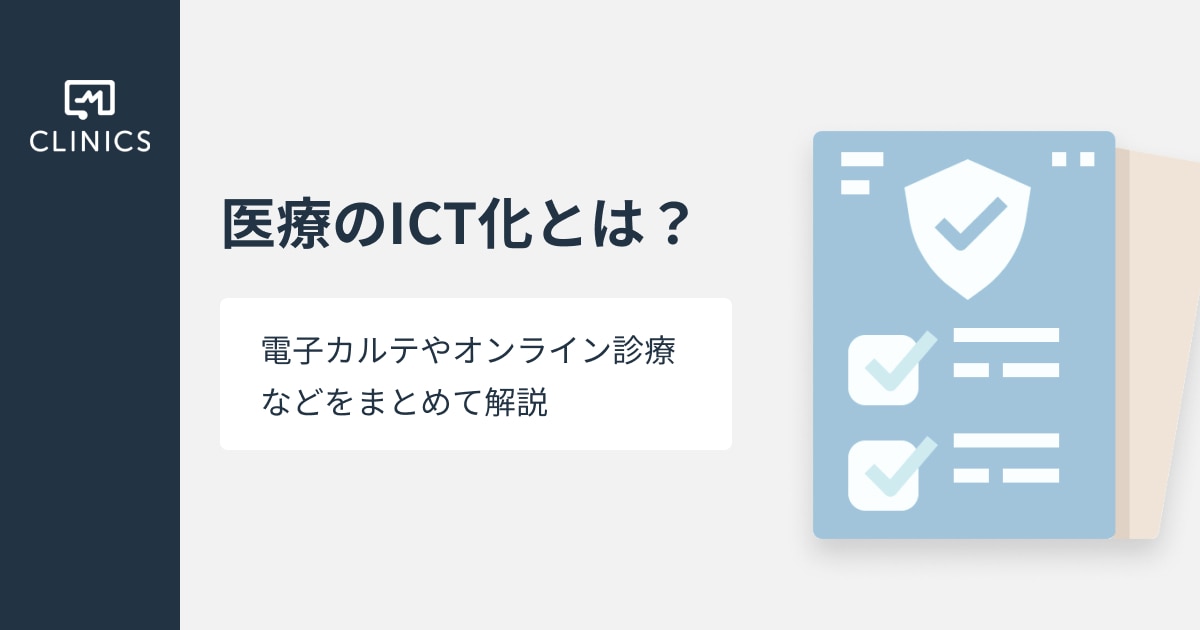
医療のICT化とは?電子カルテやオンライン診療などをまとめて解説
さまざまな業界で進められているICT化。医療業界でも、ICT化という言葉をよく聞くようになった方も多いのではないでしょうか。この記事では、医療のICT化について説明します。
この記事を読むと以下のことがわかります。
- 医療ICTとは
- ICT化により期待されるメリット
- 医療におけるICTの利活用
目次[非表示]
- 1.医療ICTとは
- 2.医療におけるICTの利活用
- 3.医療ICT化の現状
- 3.1.電子カルテの普及率
- 3.2.オンライン診療の導入
- 3.3.地域医療情報連携ネットワークの運用状況
- 4.医療ICTが他分野に比べて5年程度遅れている理由
- 5.医療ICTが進んでも紙との両立は必須
- 6.ICT化により期待されるメリット
- 6.1.最適医療の提供が可能となる
- 6.2.新たな診断技術や治療法、新薬の開発につながる
- 6.3.医療機関の業務効率化
- 6.4.地域医療の充実
- 7.ICT化で日本の医療はさらに推進される
医療ICTとは

ITと似たような意味で使われる「ICT」。ICTとは、「Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)」の略です。意味は「情報通信技術」で、SNS上でのやり取りやネット通販やチャットも広義ではこれにあたります。
医療分野でもICTを活用することでさまざまな課題解決につながると期待されています。
例えば、遠隔の患者の診療が可能となるオンライン診療やオンラインの予約システム、患者の情報を電子情報として管理できる電子カルテなどが医療分野のICT活用として挙げられます。
ITとICTの違い
ITとは、「Information Technology」の略で、「情報技術」を指す用語です。コンピューターのハードウェア・ソフトウェアや情報通信に関する技術などのすべてがITなのです。
ICTは意味合いとしてはITと近いのですが、「IT技術を使ってどのように人々の暮らしを豊かにしていくか」という、いわば「ITの活用方法」にあたります。特に医療ICTの場合は医療と患者とのコミュニケーションに重点が置かれているといえるでしょう。
医療ICTの必要性
現在の日本は少子高齢化によって、主に以下の3つの課題を抱えています。
- 医師や医療機能の不足
- 医師や医療機能の不足にともなう医療従事者1人あたりの作業量の増大
- 労働人口の減少にともなう国民1人当たりに対する医療費の増大
これらの課題を解決していくためには、医療全体の効率化が急務となっています。医療全体の効率化がさらに重要となった結果、医療ICTが推進されるようになりました。
医療におけるICTの利活用

ここからは、医療におけるICTの利活用について知りましょう。医療ICTは多岐にわたっていますが、中でも代表的な下記の3つについて解説します。
- 遠隔(オンライン)診療
- 電子版お薬手帳
- 電子カルテ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ICTの活用事例(1):遠隔(オンライン)診療
ICTの活用事例の最たるものが、遠隔(オンライン)診療でしょう。在宅医療での活用も期待されており、緊急往診に代わるツールとしてビデオチャットを用いたオンライン診療もすでに導入されています。
病院で長時間待つ必要もなく、時間と場所の制約を受けずに診察を受けることが可能です。医療機関に通うことによる感染症のリスクや病気の症状悪化を予防できるのも利点と言えるでしょう。
関連記事:【医療機関必見!】オンライン診療の特徴から導入方法までわかりやすく徹底解説!
ICTの活用事例(2):電子版お薬手帳
お薬手帳は忘れられやすく、医師や薬剤師が過去の服薬履歴を確認できないケースも非常に多いのが現状です。健康管理に役立つだけでなく、医師・薬剤師が同時に確認できることにより、相互作用防止や副作用回避にも貢献できます。
データ容量が大きいため、長期にわたる服用歴の管理が可能になります。さらに、医療ICTの発展により、電子版お薬手帳のアプリケーションに運動記録や健診履歴などの追加機能が備わりました。薬の管理だけでなく、健康管理も一緒にできるようになったのです。
ICTの活用事例(3):電子カルテ
医療のICT化と聞いて一番に思い浮かべるのが電子カルテという方も多いでしょう。
電子カルテとは、紙媒体に医療情報をまとめていた従来のカルテを電子データとしてまとめたものです。情報共有がスムーズになるだけでなく、今までであれば年数を経るごとに場所を圧迫していた紙カルテのスペースを縮小できます。
また、電子カルテシステムは、放射線科で撮影したX線画像を管理する医用画像情報システム(PACS)や臨床検査機器で得られたデータと連携できるのはもちろん入院から退院までの診療経路(クリニカルパス)のデータをナースステーションや病棟と瞬時に共有できます。
関連記事:電子カルテとは?導入のメリットや課題について解説します
医療ICT化の現状

医療ICT化の現状として次の3つが挙げられます。
- 電子カルテの普及率
- オンライン診療の導入
- 地域医療情報連携ネットワークの運用状況
それぞれ詳しくみていきましょう。
電子カルテの普及率
医療ICTの現状を知るうえでポイントとなるのが電子カルテです。電子カルテは診療予約や問診票システム、自動精算機といった各システムとの連携において基軸となるシステムであり、医療ICT化には欠かせません。
厚生労働省が公表した「電子カルテシステム等の普及状況の推移」によると、令和2年時点の普及率は一般病院で約57%、一般診療所で約49%でした。規模別に見ると400床以上の病院で約91%、200床未満の病院では約48%となっています。
規模が小さくなるにつれて普及率は減少傾向であるが、全体的に電子カルテの普及は進んでいると考えられます。
オンライン診療の導入
新型コロナウイルスによる感染拡大防止のため、導入が加速したオンライン診療ですが、その利便性から恒久的に利用できるように議論が重ねられているのが現状です。2022年4月の診療報酬改定では、オンライン診療の基本診療料が見直され、オンライン診療が導入しやすいように変更されました。
オンライン診療システムの種類も増えており、今後オンラインで診療可能な医療機関は増えていくことが予想されます。
地域医療情報連携ネットワークの運用状況
地域医療情報連携ネットワークとは、病院や薬局、他施設が患者の情報を電子化して共有・閲覧できるシステムです。
各医療機関が連携することで、過剰治療を防止し、地域医療の質を高めることができます。また、紹介や転院がスムーズに進み、シームレスな医療・介護を提供できるといった利点もあるでしょう。
しかし、2020年に厚生労働省が公表した調査結果によれば、システムがまったく機能していなかったり利用率が低く行政の指導が不十分だったりしたケースが多く見受けられました。
医療ICT化による情報連携の推進や行政によるフォローアップといった対策が行われているものの、システムが活性化されるには、もうしばらく時間がかかるというのが現状です。
医療ICTが他分野に比べて5年程度遅れている理由

電子カルテの普及率は高いものの、診療予約システムといった他システムの普及率は低いのが現状です。また、オンライン診療の診療報酬がようやく対面診療に近づいたこともあって、十分に普及しているとはいえません。
このことからわかるとおり、医療ICTはまだまだ途上です。一説には他分野よりも5年程度遅れているといわれています。
ここまで遅れてしまっている理由としては「開業医の平均年齢の高さ」が挙げられます。開業医の平均年齢は約57歳で、パソコンが苦手という方も少なくありません。
また、1人1台が基本の一般企業と違って、1台のパソコンを複数人が共有するのが基本的だった他、ICT化をペーパーレス化と勘違いしている方が多いことも医療ICTが遅れた理由といわれています。
医療ICTが進んでも紙との両立は必須

医療ICT化で多くの書類がデジタルにシフトしていますが、医療サービスを受ける9割は高齢者と子どもです。
高齢者の場合、パソコンやスマートフォンよりも、紙の処方箋や領収書の方が扱いやすいという方は多いかもしれません。また、医師が紙を渡すことで説得力が増すという医療側のメリットもあるでしょう。
万が一災害によってエラーや停電が起きて、システムが使用できなくなった際は紙で対応しなければなりません。以上の点から、医療ICT化がどれだけ進んでも、紙との両立は必須です。
ICT化により期待されるメリット

新型コロナウィルスによる在宅医療の急激な推進、超高齢化社会への移行など、多くの要素がある現在、医療ICTは確実に広まりつつあります。ここでは、今後より推進されていくであろう医療ICTのメリットを紹介します。
最適医療の提供が可能となる
オンライン診療を活用することによって、病院に通いにくい距離に住んでいる患者や、かかりつけ医のもとから引っ越した患者もかかりつけの医院に通い続けられます。また、足腰が悪くなかなか病院に通う頻度が上がらない高齢者も、より適切な間隔で診療を行えるようになります。
また、オンライン資格確認やお薬手帳の電子化やカルテの電子化によって、医師・薬剤師が違う場所にいても同じものを確認できることにより、診察内容の確認や薬の重複調剤・副作用回避にも貢献できます。医療ICTによって、患者それぞれに対しての最適医療の提供が可能となるのです。
新たな診断技術や治療法、新薬の開発につながる
現状、健診結果や医療情報を本人が有効活用できるようになっていないこともあります。自身の情報をスマホ等で簡単に確認し、健康づくりや医療従事者とのコミュニケーションに活用が可能になります。
医師は集まったビッグデータの活用により研究や適切な治療の提供がすすめられ、それに基づいて新たな診断・治療法が開発・提供される可能性があるのです。
医療機関の業務効率化
現状、カルテ入力が医療従事者の負担になっているケースもあります。AIを活用することで、診察時の会話からカルテを自動作成ができます。また、大量のカルテのなかから一枚を探し出すのは手間のことも多いですが、電子カルテの場合は検索機能などで探しやすくなります。
医療従事者が患者の治療等に専念できるよう、膨大な論文をAIで解析するなどのICT技術も発展しています。結果的に業務が効率化され、医師、看護師等の負担を軽減できるようになるでしょう。
地域医療の充実
高齢化社会を見据えた健康・長寿社会の形成過程において、地域医療に関しては、地域住民を中心とする視点からの見直しが急務です。
医療ICTによる「ICT による見守り」の仕組み(妊産婦医療、在宅患者、生体情報モニタリング、及び医師・医療者間の相互連携)を用いることで、全国どこでも最適化された患者本位の医療の提供ができるようになります。
医療ICTの課題

医療ICTの課題は以下の3つです。
- 被保険者番号
- セキュリティ対策
- 災害やエラーへの対策
加入保険が変化した場合、現状個人の資格情報は引き継がれません。加入保険が変化しても継続的に管理できるように被保険者番号のID化が求められています。
マイナンバーカードを健康保険証として活用できるようになり、2023年からはオンライン資格確認の導入が義務化されました。医療ICTが推進される一方、患者のセンシティブな医療情報を取り扱うため、セキュリティ対策を強化しなければなりません。
システムに依存してしまうと、災害によって停電が起きたり、システムエラーが発生したりすると、医療業務が行えなくなります。質の高い医療を提供し続けるためには、災害時の電力対策やシステムエラー時の対応策について事前に策定しておくことが大切です。
ICT化はシステム機器の連携が大切

ICT化を進めるにあたっては、各システムとの相性がよい電子カルテを導入するとよいでしょう。ただし、電子カルテを導入しただけでは業務効率化は単一的になってしまいます。
したがって、病院全体で業務効率化を図っていくためには、予約診療システムやWeb問診システムといった複数のシステムを導入し、連携していくことが大切です。ただし、導入するシステムに正解はありません。
医療機関の課題や状況、患者のニーズに合わせて、必要なシステムを導入していくとよいでしょう。
ICT化で日本の医療はさらに推進される
医療のICT化は、対面診療を補完する限定的なものとされていました。しかし、ICTの活用が広まるにつれて、そうした状況は変わりつつあります。電子カルテや電子版お薬手帳等、ICT技術は既に医療業界に大きな変革をもたらしているのです。
今後は国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧し、自らの健康管理や予防等に容易に役立てることが可能になるなど、医療の質の向上を促す重要なツールとして様々な場面で活用されていくことになります。そのためには医院側だけでなく患者側にもICTやインターネット、セキュリティについて周知しておくことが求められていくでしょう。