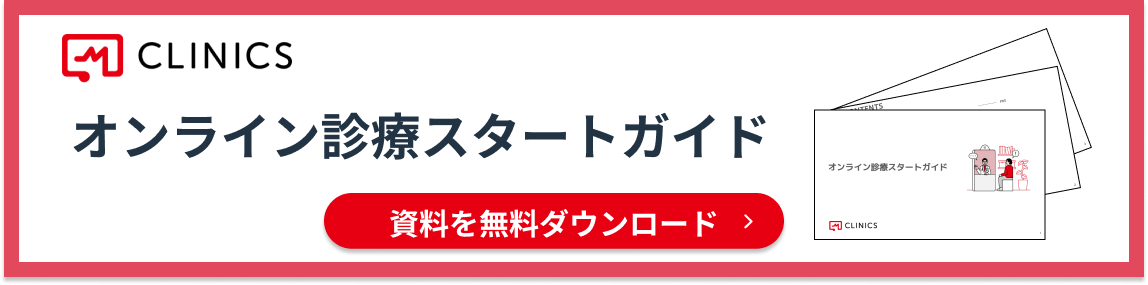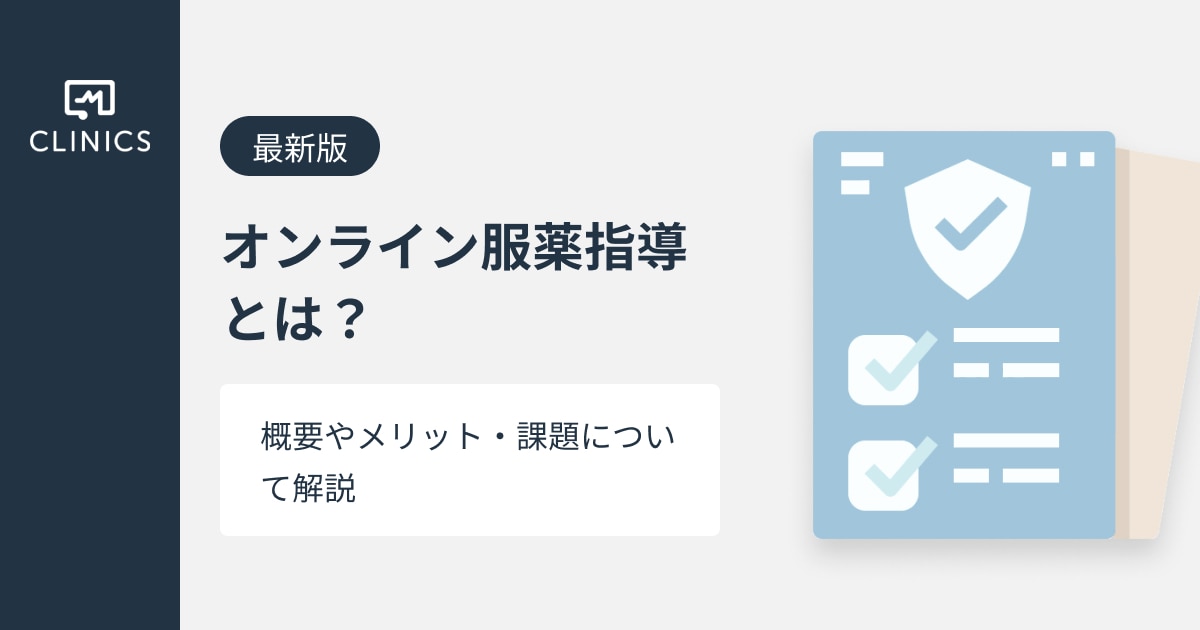
【最新版】オンライン服薬指導とは?概要やメリット・課題について解説
オンライン服薬指導についてどの程度の知識があるでしょうか?
今後より発展していくであろうオンライン服薬指導について、深い知識を得ておくことは、クリニックや調剤薬局の発展にも重要です。
この記事では、オンライン服薬指導の概要やメリット・デメリットを解説していきます。
この記事を読むと以下のことがわかります。
- そもそもオンライン服薬指導とは何か
- オンライン服薬指導に必要なもの
- オンライン服薬指導のメリット
- オンライン服薬指導の課題
薬は正しい使用方法によって初めて効果を発揮します。そのため、服薬指導はとても重要な役割を担っているのです。オンライン服薬指導により、服薬指導がどう変わるかを一緒に確認していきましょう。
目次[非表示]
- 1.そもそもオンライン服薬指導とは
- 2.オンライン服薬指導に必要なもの
- 2.1.1. ビデオ通話機能がある機器
- 2.2.2. 電子お薬手帳
- 2.3.3. クレジットカード
- 3.オンライン服薬指導の7ステップ
- 3.1.1.対面診療もしくはオンライン診療を実施する
- 3.2.2.医療機関から薬局へ処方箋が送付される
- 3.3.3.服薬指導計画書の作成
- 3.4.4.薬剤師による調剤
- 3.5.5.オンライン服薬指導の実施
- 3.6.6.患者へ医薬品を配送
- 3.7.7.医師との情報共有
- 4.オンライン服薬指導のメリット
- 4.1.患者の時間的負担軽減
- 4.2.在宅医療における負担軽減・業務効率化
- 4.3.病院や薬局内での感染防止につながる
- 5.オンライン服薬指導の課題
- 5.1.通信環境や情報リテラシーによって実施できないことも
- 5.2.オンラインでできることに限りがある
- 5.3.対応している薬局が少ない
- 6.令和4年の調剤報酬改正による変化
- 6.1.オンライン服薬指導の実施要件
- 6.2.オンライン服薬指導の加算点数
- 7.オンライン服薬指導の本格導入に向けて事前準備を!
そもそもオンライン服薬指導とは

服薬指導とは、薬剤師が患者に対して薬の飲み方を説明することを指します。医師の診察を受けてから薬局で薬をもらう際、薬についての説明を受けた経験を誰もがお持ちだと思います。まさにそれが服薬指導に当たります。
これまでの服薬指導は、「原則として薬剤師が対面で指導すること」と薬剤師法・医薬品医療機器等法により義務付けられていました。しかし、2019年度の医薬品医療機器等法が改正され、2020年9月から国家戦略特区内で特例としてオンラインでの服薬指導が行えるようになったのです。
超高齢社会の日本にとって、遠隔での治療・服薬指導は欠かせない医療サービスになっていくはずです。
参考:令和2年度診療報酬改定の概要 | 厚生労働省保険局医療課
オンライン服薬指導に必要なもの

実際にオンライン服薬指導を受けるにあたって必要なものがあります。これは、オンライン服薬指導だけではなくオンライン診療(病院に行かず自宅などで診察を受けること)にも通じますので、今後そちらの導入を検討している方もぜひ参考にしてください。
1. ビデオ通話機能がある機器
オンライン服薬指導では、ビデオ通話によって遠隔で患者に薬の説明を行います。そのため、ビデオ通話機能がある機器が必要になります。
2. 電子お薬手帳
オンライン服薬指導を行う際は「電子お薬手帳」の準備が必要です。
電子お薬手帳とは、クラウド上に薬の情報を保管し、オンライン服薬指導・オンライン医療で活用できるシステムです。通院日や服薬時間などを管理できるタイプのリマインド機能を備えた電子お薬手帳もあります。
厚生労働省は、処方箋の電子化の運用に向けた取り組みに着手し始めています。早ければ2022年にも電子処方箋を解禁するといわれているのです。今後は電子処方箋と電子お薬手帳との連携が始まる可能性もあり、利便性がより向上するのではと期待されています。
3. クレジットカード
オンライン服薬指導の場合、支払いもオンライン上で済ませることになっています。現在のオンライン服薬指導システムでは、クレジットカード払いが一般的です。
振り込みや後払いシステムでは支払えないケースがほとんどですので、クレジットカードを準備してからオンライン服薬指導・オンライン診療を受けるようにしましょう。
オンライン服薬指導の7ステップ

オンライン服薬指導のステップは次の流れです。
- 対面診療もしくはオンライン診療を実施する
- 医療機関から薬局へ処方箋が送付される
- 服薬指導計画書の作成
- 薬剤師による調剤
- オンライン服薬指導の実施
- 患者へ医薬品を配送
- 医師との情報共有
各ステップについて詳しくみていきましょう。
1.対面診療もしくはオンライン診療を実施する
まずは医師による診療を実施しましょう。
病院やクリニックでの対面診療はもちろん、オンライン診療でも構いません。診療を受けた際、オンライン服薬指導を受けたいかどうかを患者に訪ねておくとよいでしょう。
薬を渡した後に患者からオンライン服薬指導を受けたいと要望されても、手続きができていないため、服薬までに間に合いません。事前に確認しておくことで、医師から薬局へ必要な情報を円滑に伝達できます。
2.医療機関から薬局へ処方箋が送付される
診療により薬の服用が必要な場合は処方箋が発行されますが、従来のシステムでは処方箋を薬局に持っていくことで調剤と服薬指導を行います。
一方、オンライン服薬指導の場合は、医療機関が患者の希望薬局に処方箋を送付するため、患者が薬局に持っていく必要はありません。ただし、医師からオンライン服薬指導を受ける旨が伝わっていないと、患者が薬局に持っていくことになります。
患者の負担を減らすためにも、オンライン服薬指導希望かどうかしっかりと確認してあげましょう。
3.服薬指導計画書の作成
医療機関から患者がオンライン服薬指導を希望しているとの連絡が薬局に入ると、薬剤師は服薬指導計画書の作成やオンライン服薬指導に向けた準備を始めます。
「服薬指導計画書」とは、オンライン服薬指導で説明する医薬品の情報や、医薬品を渡すうえでのルールをまとめたものです。この服薬指導計画書に基づいて、オンライン服薬指導が行われます。
4.薬剤師による調剤
薬剤師は、服薬指導計画書の作成と並行して調剤を行い「処方に間違いがないか」や「投与量は適切か」を患者の状況と照らし合わせながら、薬が適切に処方されているかを確認します。
また、調合を行いながら疑問を感じた場合は、処方箋を発行した医師と相談するのが一般的です。
5.オンライン服薬指導の実施
服薬指導計画書の準備と調合が完了したら、オンライン服薬指導が実施されます。連絡方法は薬局によりさまざまですが、薬剤師から患者の電話やLINEに連絡する場合がほとんどです。
また、中には専用のアプリを用意している薬局もあるので、その場合は患者に説明して事前にアプリのインストールや登録といった準備をしてもらっておきましょう。
服薬指導内容は、従来のものと同様、薬剤の情報が提供され、処方されている薬の効能や効果、副作用、薬の飲み合わせ、取扱いの注意について薬剤師から指導を行います。対面での指導とは異なり、症状が伝わりにくいため、それらを踏まえて服薬指導を行わなければなりません。
6.患者へ医薬品を配送
オンライン服薬指導が終わった後、調剤薬局から患者へ医薬品を配送する方法と薬局の店舗で薬を受け取る方法があるため、患者にどちらが希望か聞くとよいでしょう。
配送する場合、薬局ごとに配送方法が違ったり、別途配送料がかかったりする他、配送料も異なるため、オンライン服薬指導をする前に料金体系を伝えることが重要です。
7.医師との情報共有
オンライン服薬指導の後、必要に応じて薬剤師は患者の状況について医師と情報を共有します。
万が一医薬品による副作用が出た場合にすぐに対応できるよう、医師と薬局が連携を深めておく必要があるからです。
オンライン服薬指導のメリット

オンライン服薬指導は、新型コロナウイルス流行後その範囲が広がり、今では多くの薬局で導入され始めてきました。現在、下記のようなメリットが見込まれています。
- 患者の時間的負担軽減
- 在宅医療における負担軽減・業務効率化
- 病院や薬局内での感染防止につながる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
患者の時間的負担軽減
オンライン服薬指導の意義については最初に軽く触れましたが、自宅で療養せざるを得ない患者に対して行っていた医療も、オンライン化によって、より便利になるとされています。
オンライン服薬指導では、離れた場所でも服薬指導ができるため、保険調剤薬局へ直接足を運んで対面指導を受けなくてよくなり、患者の時間的負担が大きく軽減されるのです。
在宅医療における負担軽減・業務効率化
高齢社会が続く日本では、今後より薬局・薬剤師が必要とされていくでしょう。その観点からみても、業務効率化は必須とされています。
これまでは通院が困難なために在宅医療を受けていた患者に対しても、服薬指導は薬剤師が自宅を訪れて、対面での指導をすることを義務付けられていました。こうした状況で、オンライン服薬指導が可能になると、訪問に伴う薬剤師の負担を軽減できます。
病院や薬局内での感染防止につながる
新型コロナウイルス感染症が流行している現在、医療機関で発生する感染症への感染リスクを鑑みて、なるべく通院を控えたいという方も多いはずです。しかし、通院しないことで患者の病気が悪化する可能性も大いにあります。
オンライン服薬指導を利用することで、外出せずに薬を受け取ることが可能です。患者側、医療者側共に感染リスクを最小限に留めることができ、診療の継続にもつながるのは大きなメリットと言えるでしょう。
オンライン服薬指導の課題

オンライン服薬指導は2020年の解禁後も多くの議論が交わされています。ここでは、オンライン服薬指導が抱える主な課題についてみていきましょう。
通信環境や情報リテラシーによって実施できないことも
オンライン服薬指導はスマホ・タブレット・パソコンなどの通信機器を使ってテレビ電話を用いて行われます。そのため、患者側にある程度の情報リテラシーがあることが前提となるのです。
近年では高齢者のスマートフォン所持者も増加しましたが、通信機器の操作に関する知識がまだ不足していることも事実です。ITリテラシーが不足していたり、通信環境が確立していない場合は、オンライン服薬指導がスムーズにできない可能性があります。
オンラインでできることに限りがある
オンラインでできることに限りがあることも、オンライン服薬指導の課題と言えるでしょう。
対面の服薬指導の場合、表情や細かな変化に気づけるため、服薬指導に対する理解度や、不安・疑問など、患者の状況を理解しやすくなります。しかしオンライン服薬指導では、画面越しで薬剤師が受け取れる情報に限りがあり、判断が難しい場面もあるでしょう。
対応している薬局が少ない
病院やクリニックでのオンライン診療は対応している医療機関が増えてきていますが、オンライン服薬指導に対応している薬局はまだまだ少ない現状です。
今後さらなる普及が見込まれているものの、希望者全員が気軽にオンライン服薬指導を選択できる状態にはなっていません。
令和4年の調剤報酬改正による変化

ここでは令和4年の調剤報酬改正による変化を以下2項目に分けて簡単に解説します。
- オンライン服薬指導の実施要件
- オンライン服薬指導の加算点数
それぞれ詳しくみていきましょう。
オンライン服薬指導の実施要件
新型コロナウイルス感染症対策の特例措置として、厚生労働省が一定の要件を満たす場合に電話を活用した診察や服薬指導を認める「0410対応」が令和2年に行われています。令和4年の調剤報酬改定では、0410対応の流れを加えながら次のように変化しました。
(改正前)オンライン服薬指導 |
0410対応 |
(令和4年改正)オンライン服薬指導 |
|
実施方法 |
初回は対面 |
薬剤師の判断により初回でもオンライン服薬指導が可能 |
薬剤師の判断により初回でもオンライン服薬指導が可能 |
通信方法 |
映像および音声による対応(音声のみ不可) |
音声のみでも可 |
映像および音声による対応(音声のみ不可) |
処方箋 |
オンライン診療または訪問診療を行った際に交付されたもの |
どの診療の処方箋でも可 |
どの診療の処方箋でも可 |
薬剤種類 |
これまで処方されていた薬剤 又はこれに準じる薬剤(後発品への切り替え等を含む。) |
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限 る。) |
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限 る。) |
調剤の取扱い |
処方箋原本に基づく調剤 |
医療機関からファクシミリ等で送付された処方箋情報により調剤可能(処方箋原本は医療 機関から薬局に事後送付) |
医療機関からファクシミリ等で送付された処方箋情報により調剤可能(処方箋原本は医療 機関から薬局に事後送付) |
上記のとおり、オンライン服薬指導の実施要件は通信方法を除いて大きく緩和されています。したがって、オンライン服薬指導が今まで以上に実施されやすくなりました。
引用元:令和3年度薬剤師の資質向上に向けた研修に係る調査・検討事業(ICTを活用した業務等に係る薬剤師の資質向上)|【各論1】 オンライン服薬指導について(前半)~制度と実務~
オンライン服薬指導の加算点数
調剤報酬改正によってオンライン服薬指導の加算点数も次のように変更されています。
現行 |
改定後 |
【薬剤服用歴管理指導料】 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点 |
【服薬管理指導料】 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者 45点 ロ イの患者以外の患者 59点 |
【在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料】57点 |
【在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン薬剤管理指導料】59点 |
(新) 調剤管理料 電子的保健医療情報活用加算 3点(月1回まで) |
引用:厚生労働省保険局医療課-令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)
現行の服薬管理指導料の点数と在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数が上がった他、新たに「調剤管理料 電子的保健医療情報活用加算」が追加されました。
オンライン服薬指導の本格導入に向けて事前準備を!
オンライン服薬指導によって、医療過疎地に住む患者への対応や、薬剤師の負担軽減や感染リスクの軽減などが期待されています。オンライン服薬指導は、近い将来、より良い医療を提供するためにオンライン診療と共に議論が進められていくことでしょう。