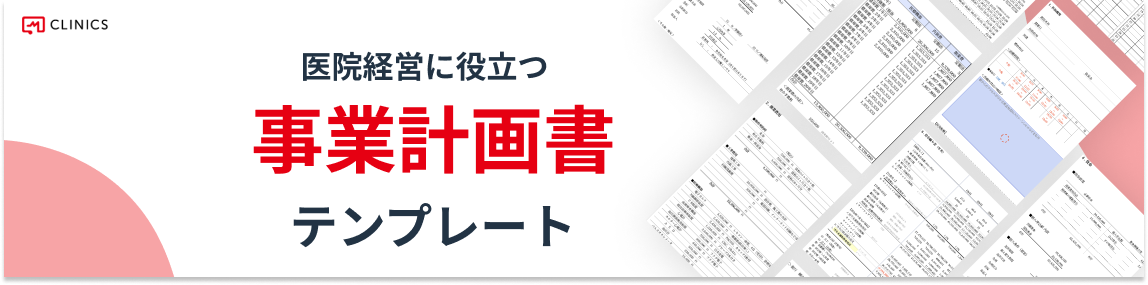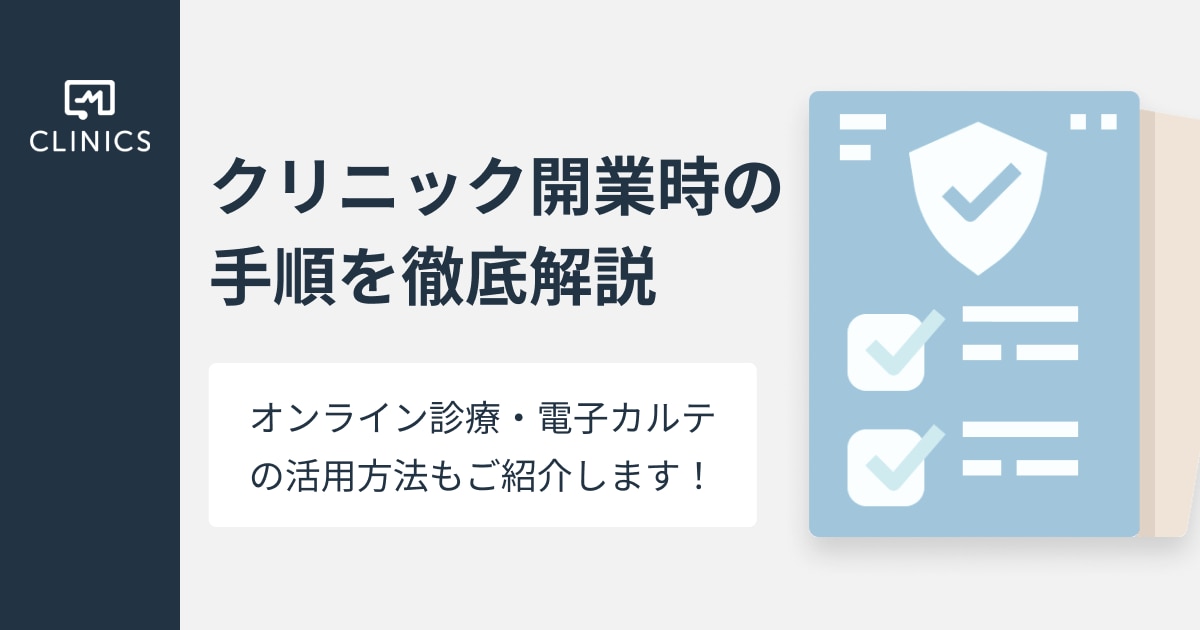
クリニック開業時の手順を徹底解説|オンライン診療・電子カルテの活用方法もご紹介します!
近年、自身のクリニックを開業する医師が増えています。開業することで収入が増えることはもちろん、独自のスタイルで診察することができるため、多くのメリットがあるからです。
しかし単に開業するのではなく、前もって計画を立てたり、クリニックを成功させるためのポイントを押さえたりする必要があります。
今回は、クリニック開業時の手順やオンライン診療・電子カルテの活用方法について紹介していきます。
また、新規開業時でも安心のサポート体制が整うCLINICSカルテの概要資料を以下に添付しておりますので、ぜひダウンロードください。
目次[非表示]
- 1.クリニック開業時のスケジュールおよび手順
- 1.1.1.事業計画の策定・開業時期の決定
- 1.2.2.資金調達・物件の決定
- 1.3.3.内装工事・導入医療機器の決定
- 1.4.4.スタッフ募集や採用・PR活動
- 1.5.5.税理士・公認会計士などの選定
- 1.6.6スタッフの研修・開業に関わる行政申請
- 2.クリニック開業における「資金調達」の3つのポイント
- 2.1.1.開業に必要な資金の目安
- 2.2.2.融資を行う金融機関
- 2.3.3.事業計画書の作成
- 3.【診療科別】クリニック開業に必要な自己資金額
- 4.クリニック開業後によくある4つのトラブル
- 4.1.1.人間関係のトラブル
- 4.2.2,システム面のトラブル
- 4.3.3.労使関係のトラブル
- 4.4.4.資金繰りのトラブル
- 5.クリニック開業を成功させるための7つポイント
- 5.1.1.コンセプトを明確にする
- 5.2.2.開業地をしっかりと選定する
- 5.3.3.資金調達の目途をつける
- 5.4.4.取り扱う診療科目によってポイントが異なることを理解する
- 5.5.5.経営戦略をしっかりと練る
- 5.6.6.医院開業コンサルタントへの依頼を検討する
- 5.7.7.地域の医師会に加入する
- 6.集患力アップに向けたシステムの活用方法
- 7.クリニック開業に関するよくある質問
- 7.1.クリニック開業に利用した費用は経費にできる?
- 7.2.クリニック開業に際して宣伝やスタッフ募集はどうすればいいの?
- 7.3.医師会に入る必要はある?
- 7.4.医療機器はリースと割賦どちらがよい?
- 7.5.クリニックの開業を思い立ったらまずやるべきことは?
- 8.まとめ
▼動画確認したい方はこちらの動画をご確認ください!
クリニック開業時のスケジュールおよび手順

クリニック開業時のスケジュールおよび手順は、以下のとおりです。
- 事業計画の策定・開業時期の決定
- 資金調達・物件の決定
- 内装工事・導入医療機器の決定
- スタッフ募集や採用・PR活動
- 税理士・公認会計士などの選定
- スタッフの研修・開業に関わる行政申請
これらの手順について詳しくみていきましょう。
1.事業計画の策定・開業時期の決定
開業の決意が固まったら、はじめに事業計画の策定・開業時期を決定しましょう。設立する場所によってクリニックの準備期間が異なります。
例えば戸建てを新築して開業する場合、建設期間を含み約18ヶ月の準備期間が必要です。
また、テナントで開業する場合は約12ヶ月の準備期間を設けた方がよいといわれています。クリニックの開業時期は、設立する場所に応じた準備期間を考慮して決定することが大切です。
開業時期が決定したら、クリニックの事業計画を策定していきます。
事業計画では、どんなクリニックにしたいのか、クリニックの特徴は何か、他院と違うところはどこなのかといった内容を詰めていきます。
あいまいな計画を立ててしまうと、事業が失敗する恐れがあるため、具体的な計画を立てることがポイントです。
さらに、事業計画を策定する際は、損益計算書や収支予算表といった金銭に関わる書類も作成しなければなりません。
開業にあたって、医師本人がクリニックの金銭の出入りを把握しておく必要はありますが、開業準備に時間がとられ苦戦することも多い傾向です。
そのような場合は、事業計画を策定する段階で開業コンサルタントに相談してみるとよいでしょう。
2.資金調達・物件の決定
事業計画をもとに希望借入金額が決まったら、金融機関との借入交渉をスタートさせましょう。事業計画書や趣意書を用意したうえで、担当者と面接し融資審査が行われます。
同時にクリニックの開業地や物件の選定しなければなりません。診療圏調査といった資料をもとに開業地や物件を決定しましょう。
ただし、物件を決めた後も内装プランの決定や工事、医療機器納入に時間を要するため、開業時期の半年前までには物件を決定し、賃貸借契約を締結しておく必要があります。
また、物件によっては診療に必要なスペースや水回りの確保をはじめ、事前に内装業者に協力してもらわなければなりません。
後々、トラブルに発展しないよう、あらかじめ専門家に相談することが大切です。
3.内装工事・導入医療機器の決定
開業する物件が決定したら、内装工事の手配および導入する医療機器を決めましょう。
内装工事を依頼する場合、可能であればクリニックの内装工事の実績が豊富な業者を選定し、打ち合わせを重ねながら内装を決めていきます。
クリニックを快適な環境に整備するためには、動線や広さの確保が重要です。
しかし内装段階で十分な広さが確保できていても、医療機器を搬入すると、狭くなるリスクがあります。したがって、搬入する医療機器のサイズも考慮しておかなければなりません。
4.スタッフ募集や採用・PR活動
スタッフ募集や採用・PR活動は開業時期の1〜3ヶ月前に始めるとよいでしょう。事業計画で定めた人員計画をもとに、必要な人材を募集していきます。
また、来院を見込む近隣住民へ自身のクリニックを周知してもらう必要があるため、スタッフ募集と並行してクリニックのPR活動を行っていきましょう。
周知する方法としては、新聞の折り込みチラシや、ホームページやネット広告といったオンライン媒体があります。
近年、クリニックのホームページ制作に特化した会社もあるため、自身でホームページを作成できない場合は、1度相談するのもおすすめです。
5.税理士・公認会計士などの選定
税理士や公認会計士といった専門家の選定も重要です。
特に医療法人会計は一般会計と違って、特殊なスキルが必要となるため、専門家にサポートしてもらった方がスムーズに会計業務を行えます。
また、従業員を雇用するのであれば、労務関係の専門家である社会保険労務士への相談も視野に入れましょう。
6スタッフの研修・開業に関わる行政申請
開業1か月前くらいからスタッフの研修を始めましょう。院長である自身およびクリニックの理念をスタッフ間で共有し、医療機器や各種システムの使用方法をレクチャーしていきます。
また、保健所に「診療所開設届」、厚生局に「保険医療機関指定申請」といった、クリニックの開業に関わる行政申請も必要です。
行政手続きが遅れるとスケジュールどおりに開業できないため、余裕を持って申請しましょう。
クリニック開業における「資金調達」の3つのポイント

クリニック開業における「資金調達」には次の3つのポイントが挙げられます。
- 開業に必要な資金の目安
- 融資を行う金融機関
- 事業計画書の作成
1.開業に必要な資金の目安
クリニック開業においては、建物や内装の工事、医療機器代、そのほかにも広告費や生活費といった運転資金が必要になります。
環境や地域、導入する機器によって金額は異なりますが以下の金額を目安にするとよいでしょう。
建物や内装の工事 |
3,000万円 |
医療機器代 |
2,500万円~3,000万円 |
運転資金 |
2,500万円 |
この中で医療機器に関しては、近年ではリースができるようになりました。そのため、初期費用が安価となり、毎月のリース代金となることが一般的です。
逆に内装費用は年々高額になっている傾向にあります。
開業して1〜2年は軌道に乗らないことがあるので、十分な生活費を用意していくことをおすすめします。
2.融資を行う金融機関
クリニックを開業する場合は融資を受けることが一般的です。
メガバンクや政府系金融機関、地方銀行などさまざまな種類があり、それぞれ融資の基準やプランなどが異なるため比較をすることをおすすめします。
また、融資を受けるためにはクリニックの経営計画や収入の見込みを示した事業計画書が重要です。融資担当者が納得しなければ融資を受けられることはありません。
クリニックは一般的な企業と比べて、融資を受けやすい特徴があります。将来的な収入以外にもどのように地域に貢献できるかを説明できるとよいでしょう。
3.事業計画書の作成
次に事業計画書の作成をしていきます。事業計画書には、事業内容や収益の見込みなどを詳しく書いていく必要があります。
ほかにも、どのような人が患者さんの対象であるか、どのような診察をしていくかなどを書くことで融資を受けやすくなります。
【診療科別】クリニック開業に必要な自己資金額

ここでは、診療科別クリニック開業に必要な自己資金額を紹介します。
- 内科
- 外科
- 小児科
- 眼科
- 産婦人科
- 精神科
- 皮膚科
- 脳神経外科
- 泌尿器科
内科
内科の開業に必要な自己資金額は、約1,000万円です。
内科の中でも、消化器内科や循環器内科のように競合の多い診療科であれば、約1,000万円必要でしょう。とはいえ、診療科によっては自己資金が不要な場合もあります。
また、テナント開業の場合では自己資金がより必要な場合もあるので注意しましょう。
外科
外科を開業する場合は、自己資金0円でも開業可能です。
ただし、0円で開業できるのはすでに土地や物件を保有している場合になります。一から物件や土地を決める場合、3,000万円以上は必要です。
また、外科手術に必要な医療機器の導入を考えると、出来る限り多くの自己資金を用意しておくのが無難でしょう。
小児科
小児科を開業する場合に必要な自己資金額は、1,000万円以上です。土地や物件から決める場合は、3,000万円以上の自己資金を用意しておいてもいいでしょう。
眼科
眼科の開業には、2,000万円以上の自己資金が必要です。自己資金に加えて、設備や医療機器の導入を考えると約4,500万円程度、用意しておくといいでしょう。
産婦人科
産婦人科の開業に必要な自己資金額は、2,000万円以上です。2,000万円に加えて土地や物件の選定、医療機器を導入する場合、3,000万円以上かかる場合もあります。
精神科
精神科は、自己資金0円で開業できるケースもあります。
精神科は他の診療科と比較しても、費用を抑えやすいのが特徴です。特別な医療機器を必要とする場合が少なく、最低限の医療機器を揃えさえすれば開業できるでしょう。
皮膚科
皮膚科の開業に必要な自己資金額は、約500万円です。
他の診療科と比較しても、開業に必要な自己資金額は低い傾向にあります。ただし、手術に必要な医療機器を導入する場合は、開業資金は高くなるでしょう。
皮膚科を開業する際、どのような手術まで行うかを事前に決めておくと、自己資金額も計算しやすいです。
脳神経外科
脳神経外科の開業に必要な自己資金額は、約6,000万円です。
脳神経外科は、手術に必要な医療機器を導入する必要があります。画像診断装置の導入も考慮すると、トータル2億円以上かかる場合もあるでしょう。
泌尿器科
泌尿器科の開業に必要な自己資金額は、1,000万円以上です。設備によっては、約3,000万円が必要になるケースもあるでしょう。
クリニック開業後によくある4つのトラブル

クリニック開業後によくあるトラブルとして次の4点が挙げられます。
- 人間関係のトラブル
- システム面のトラブル
労使関係のトラブル
資金繰りのトラブル
1.人間関係のトラブル
スタッフ同士、スタッフとの間、また患者さんとの間など人間関係によるトラブルが起こりがちです。このような人間関係のトラブルを減らすためには、日頃からコミュニケーションをとりやすい環境を作ることが重要です。
2,システム面のトラブル
クリニックには電子カルテや精算システムなどシステムを導入するケースがあります。システムは機械を使っていることから、自然災害やそのほかの理由でトラブルになる可能性があります。
システムのトラブル対応は業者に依頼することがほとんどとなるため、保守作業やトラブル対応まで対応してくれる業者にシステム導入を依頼することが重要です。
3.労使関係のトラブル
医師とスタッフの間で、言葉の誤解や指示の曖昧さなどから労使関係のトラブルに発展するケースがあります。
労使関係のトラブルを防ぐためには具体的な対策が必要です。雇用条件や勤務規定などの法的な事項は、社会保険労務士に相談し、明確にルールを定めておくことをおすすめします。
また、日常的にスタッフとのコミュニケーションを取る機会を設けたり、定期的なミーティングやフィードバックの機会を与えたりすることも重要です。円滑なコミュニケーションを通して信頼関係を築き、労使間の円満な関係を構築しましょう。
4.資金繰りのトラブル
事業計画で策定した患者数に対して、実際に来院される患者数が少なく、運転資金が減っていくなどのトラブルに見舞われることがあります。
「このままで大丈夫なのだろうか」「開業は失敗だったのではないか」など不安に押しつぶされそうな時期もあるかもしれません。しかし、経営的な安定を築くには、ある程度の期間を要します。
特に都心部などの激戦区では、集患に時間がかかることはよくあります。集患の結果を評価するには1〜2年、経営の安定化を図るには3年程度の期間をみておきましょう。
もし予定通りに患者数が増えていなければ、経営戦略の見直し、マーケティングや広告活動、地域との連携など、多角的なアプローチを検討する必要があります。
クリニック開業を成功させるための7つポイント

クリニック開業を成功させるためのポイントは、以下の7つです。
- コンセプトを明確にする
- 開業地をしっかりと選定する
- 資金調達の目処をつける
- 取り扱う診療科目によってポイントが異なることを理解する
- 経営戦略をしっかりと練る
- 医院開業コンサルタントへの依頼を検討する
地域の医師会に加入する
それぞれのポイントについて解説していきます。
1.コンセプトを明確にする
まずは、患者のターゲット層やクリニックの雰囲気、開業しようと思った理由などクリニックのコンセプトを明確化することが重要です。開業準備を進めていく過程で、迷いが生じた際は、コンセプトを見返して判断基準の材料にしましょう。
例えば、クリニックの名称を決める際に、ファミリーを対象にするのか、働き盛りの方にターゲットを絞るのか、もしくは地域密着型をアピールするのか、専門性を協調するのかで、浮かんでくるアイデアも異なります。コンセプトがあらかじめ決まっていれば開業準備をスムーズに進めることが可能です。
2.開業地をしっかりと選定する
開業地は集客にも直結する他、後から変更してしまうと事業計画や開業までの工程を策定し直さなければならない重要なポイントです。
開業地を選定する際のポイントとして、次のようなものがあります。
- 物件形態(一戸建てやビルのテナント)
- 開業エリアの人口・年齢構成
- 交通インフラの充実性
- 競合医院の数・実態
- エリアの人の流れ
地図や開業コンサルタント、不動産会社の意見だけを取り入れるのではなく、現地に行って自分の目で確認することも大切です。
3.資金調達の目途をつける
クリニックの開業資金に目処をつけることも重要です。診療科目や地域によって資金はバラバラですが、クリニック開業資金は約5,000万〜8,000万円といわれています。
開業資金が8,000万円だと仮定した場合、建物・内装工事費用が約3,000万円、医療機器費が約2,500万円、広告費や生活費といった初期の運転資金が約2,500万円となります。
このうち、医療機器費についてはリース契約が一般的であるため、リース契約にした場合は、医療機器費については月々の支払いとなり、開業資金として準備する必要はありません。
したがって、開業資金は約5,500万円となります。自己資金がどれくらいで、どれくらい融資してもらう必要があるのか算出し、資金調達の目途をつけておくことが重要です。
4.取り扱う診療科目によってポイントが異なることを理解する
取り扱う診療科目によって、ポイントが異なることも理解しておかなければなりません。
例えば、小児科だと若い世代が主なターゲットとなるため、口コミやITツールといったデジタル戦略を駆使すれば、開業早期から経営を軌道に乗せられます。
また、整形外科や消化器内科は、自己資金1,000万円程度あれば余裕を持った開業ができます。しかし脳神経外科の場合、開業資金は6,000万〜2億円程度の自己資金が必要です。
5.経営戦略をしっかりと練る
事前に、経営戦略を練っておくことで、資金繰りのトラブルを回避できたり、患者の再診率の低下を抑えられたり、集患による経営の悪化を避けられる可能性は高くなります。他院との差別化を図るため、周辺の競合クリニックの調査を行うことも、優位性を向上・維持させていくために必要な経営戦略につながります。
また、クリニック経営において、失敗につながるリスク要因を把握し、事前に対策を練ることも経営戦略の肝要な部分です。
関連記事:クリニック経営について徹底解説|失敗する原因や成功させるためのポイントについてご紹介
6.医院開業コンサルタントへの依頼を検討する
医療においては専門家の医師でも、経営や事業計画、スタッフのマネジメントなどは苦手に感じる方も多いと思われます。
クリニック開業コンサルタントに相談すれば、事業計画の策定や適切な開業地の選定などのサポート、開業後の業務改善、人事管理、新システムの導入に至るまで、さまざまな支援を受けることが可能です。クリニック開業をスムーズに進めたい場合、医院開業コンサルタントの力を借りるのは一つの選択肢となります。
選択するコンサルティング企業によって、サポート体制の違いや専門分野に精通しているかどうかが異なってきます。コンサルティング企業の選定については、ポイントを抑えつつ慎重に選びしましょう。
関連記事:クリニック開業コンサルティング企業20選!!特徴や選び方を徹底解説します!
7.地域の医師会に加入する
クリニックの開業において、医師会への加入は自由です。非加入によるペナルティもありません。
ただし、医師会に加入することで、健診や予防接種などの委託業務が増える可能性があります。それに伴って収入の増加が期待できる、クリニックの知名度向上につながるなどのメリットを得ることが可能です。
医師会への入会には審査があるため、入会を希望する場合は、まず地域の医師会を訪れて挨拶するのが望ましいです。事前に入会の意向を伝え、審査を受けることで、スムーズに入会手続きを進められます。
最終的な入会の可否は医師会によって判断されますが、事前に意向を伝えることで、加入に関する情報や要件を詳しく説明してもらえるでしょう。
集患力アップに向けたシステムの活用方法

集患力アップに役立つシステムとして、次の3システムが挙げられます。
- オンライン診療
- 電子カルテ
- 診察予約システム
どのような活用方法があるのか、詳しくみていきましょう。
1.オンライン診療で患者の治療継続率・再診率を向上させる
オンライン診療とは、スマートフォンやパソコン、タブレットなどの情報通信機器を使用しての診療が可能な医療形態です。2018年4月から保険診療でも利用が可能となり、2020年の新型コロナウイルスの流行により、ますます需要が高まっています。
診療報酬が対面診療より低く抑えられているなどのデメリットもありますが、今後の制度改革によって、対面診療との差分が小さくなっていくと考えられております。
若年層をターゲットにしたり、交通の便の悪い地域での開業を計画したりする場合は、オンライン診療の導入により、患者の治療継続率・再診率を向上させることが期待できます。
関連記事:【医療機関必見!】オンライン診療の特徴から導入方法までわかりやすく徹底解説!
2.電子カルテ によって、患者の待ち時間を短縮する
近年、パソコンを利用して診療録を作成し、電子データとして保存できる「電子カルテ」の普及が進んでいます。電子カルテと、電子カルテと連携ができる周辺システムを活用することで、情報のシームレスな共有が実現可能になります。
結果的に、スタッフの業務が効率化することで、患者の待ち時間を短縮することに繋がります。電子カルテと周辺機器を組み合わせることによって、医療の質向上に直結するだけでなく、業務の効率化による高い患者満足度の獲得、集患力の向上につなげることが可能です。
関連記事:電子カルテとは?導入のメリットや課題について解説します
3.診察予約システム によって、患者が予約しやすいクリニックに
診療予約システムは、患者がインターネット上でクリニックの予約を行えるシステムです。クリニックに来院予定の方にとって、非常に利便性の高いサービスです。
インターネットに接続できる端末があれば、場所や時間に制約されることなく診療予約が可能です。
診療予約システムの活用によって、ホームページからの新規患者の流入が期待できたり、電話対応を省き業務の効率化を図れたり、外来の混雑状況をコントロールできたりとさまざまなメリットが得られます。
クリニック開業に関するよくある質問

クリニック開業に関するよくある質問は、以下の通りです。
- クリニック開業に利用した費用は経費にできる?
- クリニック開業に際して宣伝やスタッフ募集はどうすればいいの?
- 医師会に入る必要はある?
医療機器はリースと割賦どちらがよい?
クリニックの開業を思い立ったらまずやるべきことは?
疑問を解消できるように、詳しく紹介します。
クリニック開業に利用した費用は経費にできる?
クリニック開業に利用した費用は、経費にできます。開業に必要で購入した購入した医療機器などの領収書は、必ず保管しておきましょう。
クリニック開業に際して宣伝やスタッフ募集はどうすればいいの?
クリニックの宣伝やスタッフ募集は、求人サイトの利用や人材紹介業者へ依頼しましょう。
また、クリニックの認知度を高めるためにはSNSの活用も有効です。SNSを活用して認知度を高めることで、求人につなげることもできるでしょう。
医師会に入る必要はある?
クリニック開業後の医師会への入会は、経営者の自由です。医師会へ入会するメリットがあると感じる場合は、入会してもいいでしょう。
医療機器はリースと割賦どちらがよい?
経済耐用年数を考慮することが重要です。例えば、CR装置など、5〜7年程度での買い替えが予想される機器はリースを選択するのがおすすめです。
一方、長期間使用することが見込まれるレントゲン装置などについては、割賦の検討が適切であるといえます。リースを選択した場合、リース料に固定資産税や動産総合保険が含まれているため、費用の一本化が可能です。
経済耐用年数を考慮してリースと割賦を選択すれば、経済的な効果を最大化できます。各々の機器の特性や使用予定期間、資金計画に応じて、最適な導入方法を検討しましょう。
クリニックの開業を思い立ったらまずやるべきことは?
前述した通り、まずは患者のターゲット層やクリニックの雰囲気、開業しようと思った理由などクリニックのコンセプトを明確化することが重要です。コンセプトを決めることで、安定した開業準備や経営に向けての目標設定に繋がります。
開業を成功させるには、コンセプトの明確化は不可欠なステップです。自身の理念やビジョンを明確にし、それを実現するための計画を具体化させることで、開業準備と経営の基盤を築くことが可能になります。
まとめ

今回は、クリニックを開業するにあたっての手順や、オンライン診療そして電子カルテの活用方法について紹介しました。クリニック開業にはいくつか手順があるため、これらを1つ1つ乗り越えていかなければいけません。
手順を1つでも疎かにすると、開業直後に問題が発生しやすくなります。自分の理想とするクリニックを開業させるためには、ポイントを押さえながら、1つずつ確実にこなしていくことが重要です。