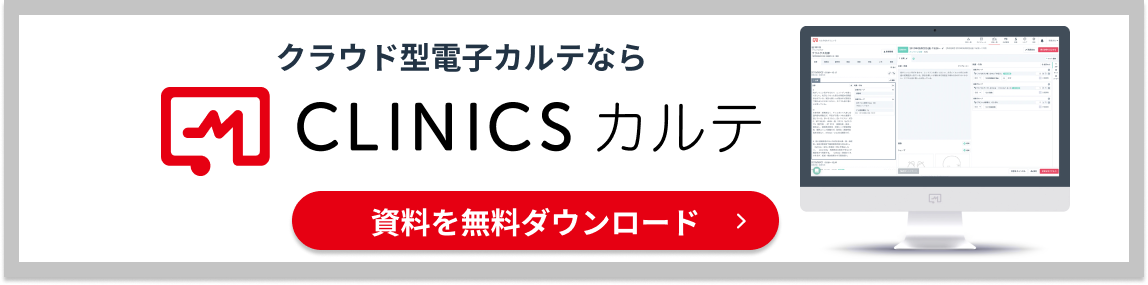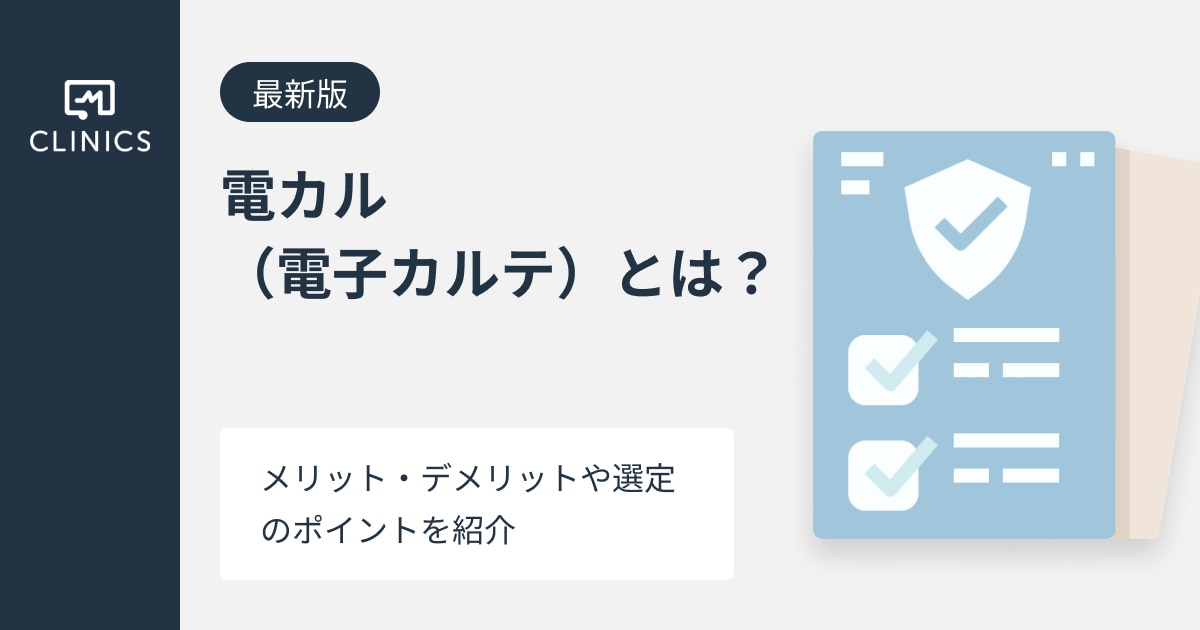
電カル(電子カルテ)とは?メリット・デメリットや選定のポイントを紹介

近年、医療現場のデジタル化が進み、電カル(電子カルテ)の導入が加速しています。電カルは、診療情報を電子的に記録・管理することで、業務の効率化や医療の質向上に貢献します。
しかし、導入にはコストやシステム障害のリスクなど、慎重に検討すべき点も少なくありません。本記事では、電カルのメリット・デメリット、導入時のポイントを詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.電カル(電子カルテ)とは
- 2.電カルと同様に知っておきたい医事システム
- 2.1.オーダリングシステム
- 2.2.レセプトコンピュータ(レセコン)
- 3.電カル導入のメリット
- 4.電カル導入のデメリット
- 4.1.初期導入コスト
- 4.2.操作習熟の必要性
- 4.3.システム障害のリスク
- 5.電カル選定のポイント
- 5.1.クラウド型かオンプレミス型か
- 5.2.既存システムとの連携性
- 5.3.操作性と使いやすさ
- 5.4.サポート体制
- 6.まとめ
電カル(電子カルテ)とは

電カル(電子カルテ)とは、従来の紙媒体で管理されていた患者の診療情報を電子データとして記録・管理するシステムを指します。のちほど詳しく紹介しますが、問診内容や検査結果、処方薬、会計情報など、患者に関わるさまざまな情報をパソコンなどで一元的に作成・保存・管理できるようになります。
電カル(電子カルテ)の導入率は、 厚生労働省の医療施設(静態・動態)調査によると、令和5年10月時点で55%を超えており、今後も増加する見込みです。詳しくは、次の記事を参考にしてください。
電カルと同様に知っておきたい医事システム
電カル(電子カルテ)は、病院や診療所で重要な役割を果たしているシステムです。医療の質や効率をさらに向上させるためには、電子カルテだけでなく、ほかの医療システムについても知っておくことが大切です。
特に、「オーダリングシステム」と「レセプトコンピュータ(レセコン)」は、診療の流れや医療費請求の効率化において欠かせません。ここでは、それぞれのシステムの役割と重要性について詳しく説明します。
オーダリングシステム
オーダリングシステムとは、診察時の指示を電子化し、看護師や薬剤師、検査技師などに素早く正確に伝えるシステムです。かつては医師が紙に指示を書き、各担当者が受け取る方法が一般的でしたが、伝達ミスや時間のロスが起こりやすいという問題がありました。
オーダリングシステムを導入すると、医師が入力した診療や処方の内容がすぐ各担当者に届くため、薬の準備や検査がスムーズに進み、患者の待ち時間も短くなります。
また、データが一元管理されることで、記入ミスや伝達ミスが減り、安全性も向上します。
詳しくは次の記事を参考にしてください。
レセプトコンピュータ(レセコン)
レセプトコンピュータ(レセコン)とは、病院やクリニックで診療報酬の請求業務を効率化するためのシステムです。診療や処方した薬の情報を入力すると、自動で保険の点数を計算し「レセプト(診療報酬明細書)」を作成します。
手書きでレセプトを作る場合、計算ミスや記入漏れが発生しやすいという課題がありました。しかし、レセコンは自動計算ができるため、書類作成の手間が大幅に減ります。また、入力ミスを防ぐチェック機能もあるため、正確な請求が可能です。
詳しくは次の記事を参考にしてください。
電カル導入のメリット
電カル(電子カルテ)の導入は、医療現場におけるさまざまな利点をもたらします。ここでは主なメリットを詳しく解説します。
業務効率の向上
電子カルテを導入することで、医療現場における業務効率が向上します。従来の紙カルテでは、情報の記入や検索に時間がかかり、紛失や記入ミスといったリスクも避けられませんでした。しかし、電カル(電子カルテ)は患者情報の入力や検索が迅速かつ正確に行えます。
さらに、検査結果や処方内容などの情報がリアルタイムで共有されるため、医師、看護師、事務スタッフ間の連携が円滑になり、患者さんの待ち時間の短縮や診療の質の向上にもつながります。
情報の一元管理
電カル(電子カルテ)は、患者さんの診療記録、検査結果、処方履歴などさまざまな医療情報を一元的に管理できます。必要な情報に素早くアクセスできるようになり、診療や診断の質の向上が期待できるでしょう。
また、他の医療機関との情報共有も容易になるため、地域医療の連携やチーム医療の推進にも大きく貢献します。
データの安全性向上
紙カルテでは、紛失や盗難、火災・水害といった災害による消失のリスクが伴います。しかし、電カル(電子カルテ)はデータをデジタル化するため、紛失するリスクを大幅に減らすことが可能です。
さらに、アクセス権限を設定することで、不正な閲覧や改ざんを防ぎ、患者さんのプライバシー保護も強化できます。クラウドサーバーを活用すれば、システム障害時にも迅速な復旧が可能です。
スペースの有効活用
紙でカルテを保管する場合、保管場所の確保が課題となっていました。電カル(電子カルテ)は、物理的な保管スペースが不要になるため、スペースを別の用途に有効活用できます。
電カル導入のデメリット
電カル(電子カルテ)の導入は多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。ここでは主なデメリットを詳しく解説します。
初期導入コスト
電カル(電子カルテ)の導入には、初期費用がかかります。特にオンプレミス型の場合、院内にサーバーを設置する必要があるため、導入費用はおよそ300万円から500万円程度になることも少なくありません。
また、導入後も保守費用やシステム更新費などのランニングコストが発生します。
クラウド型であれば、導入コストを大幅に減らすことが可能です。詳しくは次の記事を参考にしてください。
操作習熟の必要性
電カル(電子カルテ)は、従来の紙カルテとは操作方法が大きく異なるため、スタッフ全員が新しいシステムを習得しなければなりません。特に、IT機器の操作に慣れていないスタッフにとっては、操作方法の習得に時間がかかる可能性があるでしょう。
システムの操作に慣れるまでの間は、業務効率が一時的に低下することも考えられます。電子カルテ導入時には、十分な研修期間を設け、操作マニュアルやサポート体制を整備することが重要です。
システム障害のリスク
電カルは電子機器を使用するため、停電やシステム障害が発生した場合、カルテの閲覧や入力ができなくなるリスクがあります。特にクラウド型の電カルは、インターネット接続が必須です。
万が一のリスクに備えて、バックアップ体制や代替手段を検討しておきましょう。
電カル選定のポイント

電カル(電子カルテ)の導入は業務効率化や情報管理の向上に役立ちますが、適切なシステムを選定することが重要です。
ここでは電カル選定時に考慮すべき主なポイントを解説します。
クラウド型かオンプレミス型か
電カル(電子カルテ)の導入には、「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。
クラウド型は、インターネットを通じて外部のサーバーを利用するため、初期費用を抑えられるうえ、場所を選ばずに利用できるのが特徴です。一方、オンプレミス型は、院内にサーバーを設置し、データを自院で管理する方式です。初期費用が高額になるものの、カスタマイズの自由度が高く、セキュリティ面でも優れています。
自院の規模や予算、セキュリティ要件などを考慮し、最適な導入形態を選ぶことが重要です。
既存システムとの連携性
電カル(電子カルテ)は、レセプトコンピュータ(レセコン)や検査機器、予約システムなど、ほかの医療システムと連携させることで、業務の効率を向上できます。
導入を検討する際は、現在使用しているシステムとの互換性を確認し、情報をスムーズに共有できるかどうかをしっかりと見極めることが大切です。
操作性と使いやすさ
電カル(電子カルテ)は、医師や看護師、事務スタッフなど、さまざまな職種が日常的に使用するため、直感的で使いやすい操作性が求められます。
導入前にはデモ機を使って、各職種が実際に操作を試し、現場のニーズに合っているかどうかを確認することが重要です。
サポート体制
システム導入後のトラブル対応や診療報酬改定への対応など、充実したサポート体制は、電子カルテを安定して運用するうえで欠かせません。
メーカーによってサポートの内容や対応範囲は異なるため、導入前にしっかりと確認し、安心して運用できる体制が整っているかを見極めましょう。
まとめ
電カル(電子カルテ)は、診療情報を電子データとして一元管理するシステムであり、業務の効率化や情報共有のスムーズ化、医療ミスのリスク低減など、さまざまなメリットがあります。一方で、導入には初期費用や運用コストがかかるほか、システム障害やセキュリティ対策への備えも必要です。
電カルを選定する際は、クラウド型とオンプレミス型の違い、既存システムとの連携性、操作性、そしてサポート体制などを総合的に判断することが重要です。環境に合わせて最適なシステムを選び、適切な運用体制を構築することで、質の高い医療サービスにつながります。
クラウド型電子カルテにご関心のある方、または詳しい情報をお求めの方は、ぜひ下記より「CLINICSカルテ」の概要資料をお気軽にダウンロードください。