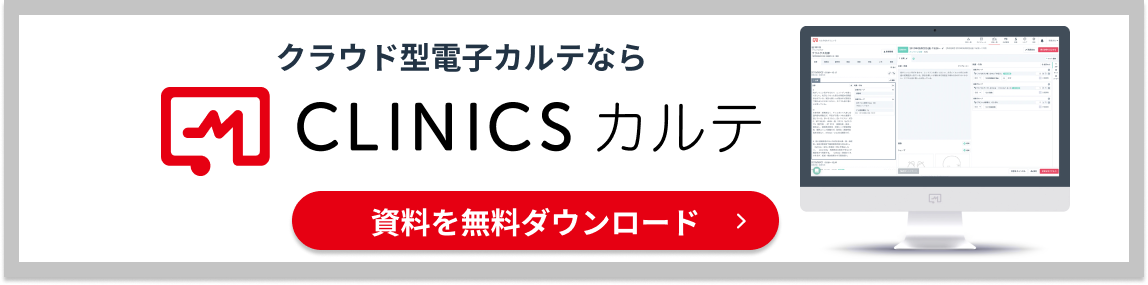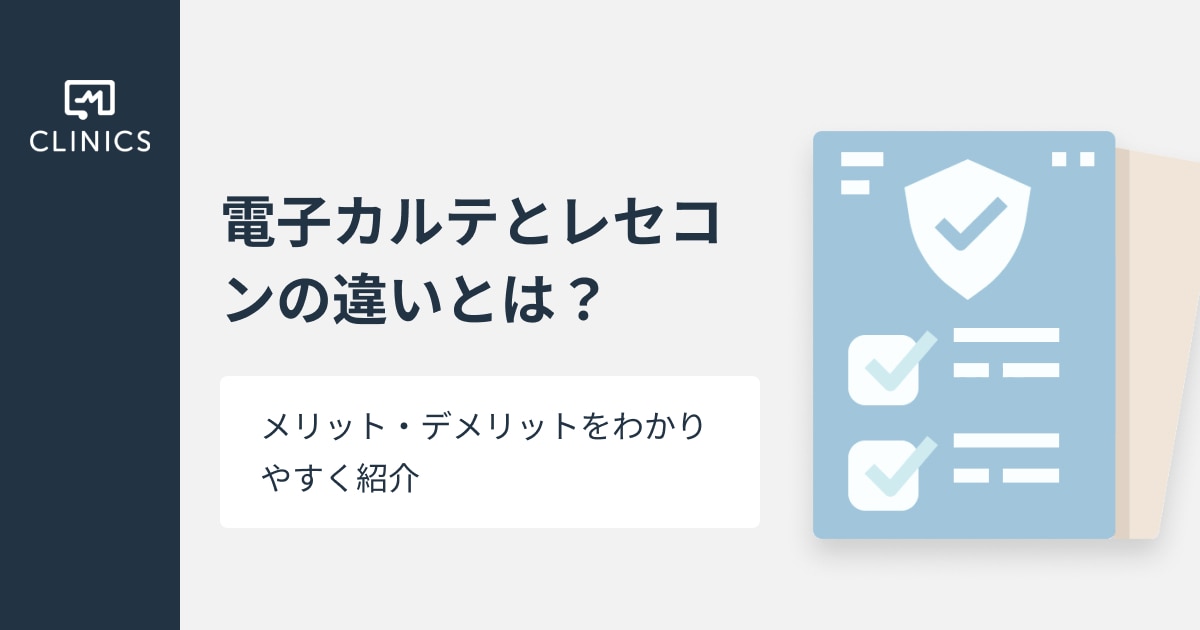
電子カルテとレセコンの違いとは?メリット・デメリットをわかりやすく紹介
レセコンとは、レセプトコンピュータの略で、レセプトを作成するソフトウェアのことです。レセコンは診療報酬の請求や会計に使用するイメージが強いと思いますが、実はクリニックの業務全体を効率化してくれる便利な存在でもあります。この記事では、レセコンとは何かから、今まさに普及拡大中の電子カルテとレセコンの違いまで解説します。
この記事を読むと以下のことがわかります。
- レセコンとは
- 電子カルテとレセコンの違い
- 電子カルテとレセコンの連携メリット
関連記事:レセコン選びの基礎知識|レセコンの機能とレセコンメーカー選びのポイントを紹介
目次[非表示]
- 1.レセコンとは
- 1.1.レセコンの導入によりできること
- 2.電子カルテとレセコンの違い
- 2.1.電子カルテとは
- 2.2.電子カルテとレセコンの違いとは
- 3.電子カルテとレセコンの連携メリット
- 3.1.受付から診療・会計まで一元管理できる
- 3.2.レセプト作成の効率化
- 3.3.業務の負担軽減・入力ミスの防止
- 4.電子カルテとレセコンの連携デメリット
- 5.おすすめの電子カルテシステム
- 5.1.CLINICSカルテ
- 5.2.MAPs for CLINIC
- 5.3.BrainBoxCloud
- 5.4.Qualis
- 5.5.SUPER CLINIC
- 5.6.M3DigiKar
- 5.7. CLIUS
- 5.8.Medicom-HRf Hybrid Cloud
レセコンとは
レセコンとは、レセプト(診療報酬明細書)を作成するためのコンピュータのことをさします。他に「医療事務コンピュータ」「医療コンピュータ」とも呼ばれています。
主に医療機関の窓口等で医療事務スタッフが使うことが多く、主に健康保険組合などの機関に対して、診療報酬を請求する「レセプト(診療報酬明細書)」の作成を行います。病院、診療所、調剤薬局でのレセプトコンピューターの普及率は96%ともいわれており(厚生労働省「レセプト請求状況」平成31年3月診療分より)、ほとんどの医療機関で広く利用されています。
レセコンの導入によりできること
レセコンを導入すると以下のようなことが可能となります。
- 診療内容の入力、保険点数の自動計算
- 記入データの点検
- レセコンと電子カルテの連携 など
ほかにも、請求関連情報を分析して経営状況に関するレポートを作成する機能付きのものもあり、医療機関の経営分析に活かすこともできます。
電子カルテとレセコンの違い
では、電子カルテとレセコンでは、どんな違いがあるのでしょうか。ここでは、電子カルテとレセコンの違いについて言及します。
電子カルテとは
電子カルテが世に出てから約20年。電子カルテは医療機関の中枢となるシステムになりました。弊社メドレーが提供している「CLINICS電子カルテ」は、使いやすいデザインで、医師の方々から高い満足度を得ています。
電子カルテは、紙のカルテと比較して、記入する速度も上がり記入漏れも失くしやすくなります。その結果、診療に関わる信頼性や正確性が上がり、診察にかかる時間を短縮できる効果が期待できます。また、記入された情報は電子情報として保管できるため、カルテの整理がしやすくなるのです。
加えて、電子カルテを利用すると、患者のデータをオンラインで検査センターとスムーズに共有できるようになることも特徴と言えます。。検査結果や、既往症、アレルギー、他の医療機関で処方されている薬などの情報を紐づけられるので、情報の精度が向上し、医療事故防止にも役立つとされています。
電子カルテとレセコンの違いとは
電子カルテとレセコンの大きな違いは「使用目的」です。電子カルテは医師や看護師などの医療スタッフが「医療情報をコンピューターに入力して、電子データとして管理、保存するもの」を指します。それに対してレセコンは主に医療事務スタッフが「診療報酬の請求業務を行うもの」を指します。
加えて、電子カルテとレセコンは「使用者」も違います。
電子カルテ |
レセコン |
|
|---|---|---|
目的 |
診療内容を記載するためのもの |
診療報酬の請求業務を行うこと |
使用者 |
医師・看護師・検査技師、薬剤師など実際に医療を行う人が中心 |
会計情報を管理する医療事務担当者や会計士 |
このように、電子カルテとレセコンでは、使用する目が異なることで、必然的に扱う人が異なるのです。
電子カルテとレセコンの連携メリット
レセコンと電子カルテを同時に使用するにあたって、「電子カルテ・レセコン連動型」と「電子カルテ・レセコン一体型」という2つのスタイルがあることを覚えておきましょう。
電子カルテ・レセコン連動型 |
電子カルテ・レセコン一体型 |
|
|---|---|---|
特徴 |
電子カルテとレセコンのシステムが別々 |
電子カルテとレセコンのシステムがひとつ |
メリット |
どちらかのみを導入しているクリニックの場合、後付けで新たなシステムを導入しやすい |
別々に入力する手間をはぶくことができ、受付・診察・会計までが一元で管理できる |
どちらの場合も電子カルテとレセコンの連動は可能です。ここでは、電子カルテとレセコンを連携させることによるメリットを紹介します。
受付から診療・会計まで一元管理できる
電子カルテは診療記録や検査結果の管理を行うシステムであり、医師や看護師などの医療従事者が利用するものです。一方で、レセコンは、診療報酬の請求業務や会計管理を目的としたシステムで、主に医療事務の担当者によって使用されます。
これを連携させることで、受付から診療・会計まで一元管理できるようになるのです。複数のシステムを横断する必要がなくなったり、紙情報を転記したりしなくて済むため、業務効率のスムーズ化にもつながるでしょう。
レセプト作成の効率化
レセプトを作成する際、医師が作成したカルテをもとに、さまざまな情報を入力する必要があるため、事務作業の工数がかかります。しかし、電子カルテとレセプトが連携していれば、この入力作業が不要になります。
毎月の請求書作成までの手間と時間を短縮することができるのは、電子カルテとレセコン連動の大きなメリットと言えるでしょう。
業務の負担軽減・入力ミスの防止
クリニックには毎日多数の患者が訪れます。紙のカルテや手書きの診療報酬明細書では作業量が多く、結果的に人為的なミスを引き起こす可能性があります。しかし、電子カルテとレセコンが連動することで作業量が減り、人為的ミスが減ることが想定されます。、結果として、日々の窓口業務の円滑化につながるのです。
作業時間が短縮されたことによる業務の円滑化は、ミスによって引き起こされる人間関係のトラブルも減らせます。それによって働く環境が良くなることにつながり、実際に作業を担当する人以外のクリニックで働く人にとっても、結果的にメリットとなると言えます。
電子カルテとレセコンの連携デメリット
電子カルテとレセコンの連携には便利な面もありますが、いくつかのデメリットも存在します。まず、システムトラブルが起きた場合、両方が使えなくなることがあり、診療や会計業務に大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、導入や運用には高額なコストがかかるため、特に小規模な医療機関にとっては大きな経済的負担となることもあるでしょう。
さらに、システム操作には専門知識が求められるため、スタッフの教育や研修に時間や労力が必要です。このように業務効率化の一方で、コストや運用面での課題をどう克服するかが重要です。
おすすめの電子カルテシステム
 電子カルテにはさまざまな種類があるため、「どれを選べばよいかわからない」という方も多いでしょう。ここでは8種類の電子カルテを紹介します。
電子カルテにはさまざまな種類があるため、「どれを選べばよいかわからない」という方も多いでしょう。ここでは8種類の電子カルテを紹介します。
- CLINICSカルテ
- MAPs for CLINIC
- BrainBoxCloud
- Qualis
- SUPER CLINIC
- M3DigiKar
- CLIUS
- Medicom-HRf Hybrid Cloud
それぞれ詳しく解説します。
CLINICSカルテ
CLINICSカルテは、当社が提供するクラウド型電子カルテシステムです。受付や診察、会計、レセプト作成まで、診療所やクリニックの業務をすべて一元管理できるため、作業効率が大幅に向上し、医療スタッフの負担を軽減できるでしょう。
さらに、患者向けアプリ「CLINICS」と連携することで、診察予約やオンライン診療、キャッシュレス決済が可能になり、患者側の利便性も向上します。
また、経営分析機能も備えているため診療業務だけでなく、診療所経営の効率向上を実現するサービス提供を行っております。
MAPs for CLINIC
「MAPs for CLINIC」は、株式会社EMシステムズが提供する無床クリニック向けのクラウド型電子カルテシステムです。シンプルかつ使いやすいデザインが特徴で、よく使う機能を画面に固定して効率よく入力できます。
ネットワークに問題が発生しても、自動でローカルモードに切り替わり、オフラインの状態でも診療を続けられます。検査結果の自動取り込みや外部システムとの連携もスムーズで、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
初期費用は不要で、1接続あたり月額20,000円、追加接続は1台ごとに月額5,000円と手頃な価格設定です。多くのクリニックで導入されており、操作のしやすさやサポート体制が高く評価されています。
BrainBoxCloud
「BrainBox Cloud」は、株式会社ユヤマが提供する無床診療所向けのクラウド型電子カルテシステムです。特徴の一つがAI機能「BB.INSIGHT」です。AIが電子カルテのデータを分析し、診察患者数や待ち時間の予測、経営判断をサポートします。
クラウド環境でも院内と同じようにリアルタイムで処方のチェックができ、他の医療機関と連携することで処方薬の一元管理も可能です。ネットワークに障害が発生した際には自動でサブサーバーに切り替わり、診療業務を途切れることなく継続できるのも大きな利点です。
セキュリティ面では、利用者ごとに仮想サーバーを構築し、高い安全性を確保しています。最新の医薬品データベース「MDbank Prime」を搭載しており、病名や医薬品に関連する情報をスムーズに検索・確認できます。
Qualis
「Qualis(クオリス)」は、株式会社ビー・エム・エル(BML)が提供する無床診療所向けの電子カルテシステムです。 医師やスタッフ、患者にとって理想的な電子カルテを目指して開発されており、わかりやすさ、効率性、安心感、便利さ、使いやすさを追求しています。
主な特徴として、カルテ入力の時間短縮を図るための直感的でわかりやすい画面構成や、音声入力機能、予約機能などが挙げられます。全国103か所の営業拠点と自社運営のサポートセンターによる万全のサポート体制を整えており、導入後の運用も安心です。
料金体系は、3台構成の場合、初期費用が2,400,000円、月額使用料が38,000円です。ソフトウェア、ハードウェア一式、レセプトオンライン請求の設定費用、導入設定費用、システム講習費用が含まれています。
SUPER CLINIC
「SUPER CLINIC」は、株式会社ラボテックが提供する無床診療所向けの電子カルテシステムです。 主な特徴として、カルテ2号用紙のレイアウトを踏襲した直感的でシンプルな画面構成が挙げられます。クリックやドラッグ&ドロップなどの基本操作だけで、簡単かつ迅速にカルテの作成が可能です。
過去カルテや問診情報、検査結果などを即座に確認できる機能も備えており、診療業務の効率化をサポートします。 症状や既往歴、服用中の薬剤、アレルギー情報などの問診データを一括入力でき、患者さんの待ち時間の短縮や混雑の緩和が期待できます。
オプション機能として、無線LANによるワイヤレス環境での運用や在宅医療に対応した往診システム、リハビリカルテ、服薬指導などが提供されており、診療所の規模や診療内容に応じて柔軟にカスタマイズが可能です。
M3DigiKar
「M3 DigiKar(エムスリーデジカル)」は、エムスリーデジカル株式会社が提供するクラウド型電子カルテシステムです。最新のAI技術を活用した自動学習機能とシンプルな画面設計により、カルテ記入時間を大幅に短縮します。
オンライン診療や訪問診療など、さまざまな診療形態にも対応できます。検査機器や外部システムとの連携も充実しており、クリニックごとの診療スタイルに合わせた運用が可能です。
初期費用が無料で、月額利用料は11,800円からとコストパフォーマンスに優れています。クラウド型の特性を活かし、診療報酬改定などのシステム更新は自動で行われ、追加費用も発生しません。
CLIUS
「CLIUS(クリアス)」は、株式会社DONUTSが提供するクラウド型電子カルテシステムです。MacやWindowsのパソコンだけでなく、iPadなどのタブレット端末でも利用可能で、外来診療や在宅医療など、さまざまな診療スタイルに対応しています。
CLIUSの特徴として、直感的でシンプルな画面設計が挙げられます。紙のカルテに慣れた医療従事者やパソコン操作が苦手な方でも使いやすいよう、診療の流れや視線の動きを考慮したデザインとなっています。AI機能を搭載しており、よく使用するオーダー内容を自動的に学習・表示できます。
さらに、WEB問診やWEB予約、オンライン診療、在宅医療機能など、クリニックのIT化を支援する多彩な機能を備えています。料金プランは初期導入費用が20万円から、月額利用料が12,000円(5ユーザーまで)です。
Medicom-HRf Hybrid Cloud
「Medicom-HRf Hybrid Cloud」は、ウィーメックス株式会社(旧PHC株式会社)が提供する医事一体型のハイブリッド型電子カルテシステムです。 オンプレミスとクラウドの利点を組み合わせ、診療所の業務効率化と診療の質向上を目指しています。
カルテ入力や経過確認、データ管理などの作業を簡単に行えるよう設計されており、医師一人ひとりの診療スタイルに合わせた画面カスタマイズも可能です。 約170社の機器と連携できるため、予約・検査・生産などのデータを統合し、診療のスピードと効率を向上させます。
デバイスや場所を問わず、院外でもカルテの閲覧・入力が可能です。ノートPCやタブレット、スマートフォン(今後対応予定)を使用して、自宅や訪問先からでも必要な情報にアクセスできます。
まとめ
厚生労働省も医療等分野におけるICT化を推進しており、今後、レセコンと連動した電子カルテも必要不可欠のシステムになるでしょう。レセコン連動の電子カルテを導入するだけですぐに業務効率化ができるわけではありませんが、よりよい医院運営の一助となることは間違いありません。
中小クリニックであっても、多くの選択肢の中からレセコン・電子カルテの導入がしやすくなっています。ぜひ今回の記事を参考にして、レセコンのバージョンアップを検討してみてはいかがでしょうか。