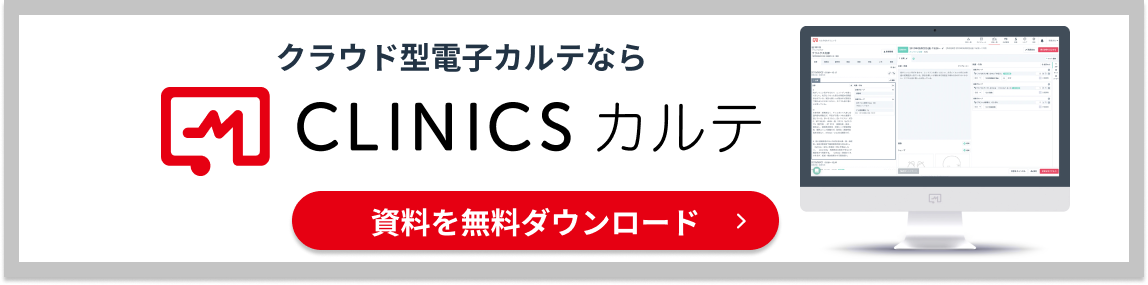電子カルテの仕組みとは?活用方法やセキュリティ対策まで徹底解説します!
当記事では電子カルテの仕組みや電子カルテのメリット・デメリット、セキュリティの高い電子カルテを選ぶポイントなどを紹介します。
目次[非表示]
電子カルテは医療システムの基盤となるシステム

電子カルテは、医療システムの基盤となるシステムです。
紙カルテを利用する場合でも、患者情報や検査結果の記録は可能でした。しかし、紙カルテだと保管場所が必要なうえにデータの取り出しも大変です。
さらにカルテの情報をもとに、データを再入力する場合もありますが転記に時間がかかり、業務負担が増えてしまうでしょう。
電子カルテがあると転記や再入力が簡単です。また、保管場所も必要ありません。
電子カルテの導入により、医療スタッフの業務を効率化させ、データを安全に保管できるようになります。
電子カルテの仕組み

電子カルテは、患者の受付と同時にカルテが呼び出されるようになっています。
診察では患者の所見や処置方法について記載し、データをもとにして処方箋などが作成される仕組みです。一度入力したデータは転記できるため、再入力する必要もありません。
電子カルテがあると受付スタッフが行う会計処理や、保険点数の計算も効率よく行えるようになります。
電子カルテと紙カルテの違いとは?

電子カルテとは、パソコンやタブレットなどで患者情報を管理できるシステムです。
サーバー上でデータを管理できるため、カルテの保管場所が不要でスムーズに情報共有できます。ただし、災害による停電などでは利用できない場合もあるのがデメリットです。
一方で、患者情報を紙媒体で管理するのが紙カルテになります。カルテ入力や情報共有に時間がかかったり、カルテの保管場所が必要であったりするのがデメリットです。
電子カルテのように停電時では利用できない場合でも、紙カルテならいつでも利用できる点がメリットといえるでしょう。
電子カルテの種類とは

電子カルテの種類は、以下の3つです。
- クラウド型
- オンプレミス型
- ハイブリッド型
それぞれ詳しく紹介します。
クラウド型
クラウド型電子カルテは、インターネットを利用する電子カルテです。
インターネットを通じてサーバー上のデータを保存できます。院内にサーバーを設置する必要がなく、外部に持ち出しての利用も可能です。
また、パソコンだけでなくタブレットでも利用できるのが特徴です。ただし、インターネットがつながっていない場所では利用できないのがデメリットといえるでしょう。
オンプレミス型
オンプレミス型電子カルテは、クリニック内に専用のサーバーを設置して利用する電子カルテです。
設置したサーバーでデータを管理します。セキュリティ面が強く、データ漏洩のリスクが低いのがオンプレミス型電子カルテの強みです。
ただし、クラウド型電子カルテと比較すると導入費用が高く、設置場所の確保が必要な点がデメリットでしょう。
ハイブリッド型
クラウド型とハイブリッド型の機能が融合しているのが、ハイブリッド型電子カルテです。ハイブリッド型電子カルテは、インターネットと院内サーバーどちらを経由しても利用できます。
例えば、院内で使う場合はサーバーを経由する、院外で利用する場合はインターネットを経由するなどの使い分けが可能です。状況に応じて使い分けられるのが魅力ですが、費用が高くなるのがデメリットでしょう。
電子カルテ比較表

電子カルテ比較表は、以下の通りです。
クラウド型 電子カルテ |
オンプレミス型 電子カルテ |
ハイブリッド型 電子カルテ |
|
インターネット上の サーバーでデータを 保存・管理する |
院内に設置する サーバーでデータを 保存・管理する |
インターネット上と 院内サーバー どちらでも利用可能 |
|
メリット |
・初期費用を抑えやすい ・院外でも利用できる |
・サポートの手厚い 電子カルテが多い ・データ漏洩の リスクが低い |
院内と院外 状況に応じて 使い分けられる |
デメリット |
・カスタマイズできないケースが多い ・オンプレミス型と比べてセキュリティが 弱い傾向にある |
・導入コストが高い 必要がある |
導入コストが 高い傾向にある |
電子カルテのメリット

電子カルテのメリットは以下の通りです。
電子カルテのデメリット

電子カルテのデメリットは、以下の通りです。
- システムに慣れるまで時間がかかる
- 電子カルテの運用に合わせる必要もある
- 停電になると利用できない
- 運用費用がかかる
電子カルテをストレスなく活用していくための3つのポイント

電子カルテをストレスなく活用していくためのポイントは、以下の3つです。
- 研修などを実施し電子カルテの機能・使用方法を習得させる
- 業務の定期的な棚卸によるカルテ運用の効率化
- 電子カルテに強い人材の確保・育成
それぞれ詳しく紹介します。
研修などを実施し電子カルテの機能・使用方法を習得させる
電子カルテをストレスなく利用するには、研修などを実施して電子カルテへの知見を深めましょう。
電子カルテは便利なシステムですが、慣れるまでに時間を要する場合があります。特に長期間紙カルテを使用していた方であれば、すぐに電子カルテに慣れるのは難しいでしょう。
データ入力や情報共有など、電子カルテの操作はマニュアル化されているため、一度理解すると簡単に利用できるケースが多いのです。
医療スタッフ全員が電子カルテの操作に慣れるためにも、研修を実施して機能や使用方法を習得しましょう。
業務の定期的な棚卸によるカルテ運用の効率化
業務を定期的に棚卸して、カルテ運用を効率化させましょう。電子カルテを導入しただけでは、医療スタッフの業務を効率化できるわけではありません。
電子カルテにはさまざまな機能が搭載されているため、使いこなすには定期的な業務の棚卸が必要です。実際に利用しながら、改善点やさらに有効活用できるポイントはないか確認しましょう。
電子カルテに強い人材の確保・育成
電子カルテに強い人材を確保したり育成したりすると、ストレスなく電子カルテを運用できます。
医師を含めた医療スタッフは、日々の業務で忙しく電子カルテに精通するのは難しいかもしれません。電子カルテを有効活用するには、現場の意見を電子カルテに反映させる必要があります。
電子カルテに強い人材の確保や育成ができると、業務の効率化が可能です。電子カルテを最大限活用できるように、事務作業や電子カルテに精通した人材の確保を目指しましょう。
セキュリティの高い電子カルテを選ぶポイント

セキュリティの高い電子カルテを選ぶ際のポイントは、以下の通りです。
- 3省2ガイドラインに準拠しているか
- 個人情報の保護・管理規格を満たしているか
それぞれ詳しく紹介します。
1.3省2ガイドラインに準拠しているか
セキュリティの高い電子カルテを選ぶには、3省2ガイドラインに準拠しているかが重要です。
3省2ガイドラインとは経済産業省と厚生労働省、総務省の3つが定めたガイドラインを意味します。ガイドラインは以下の2つです。
- 経済産業省・総務省:「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」
- 厚生労働省:「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
上記2つのガイドラインに準拠している電子カルテは、セキュリティが高いため情報漏洩のリスクを軽減できます。
2.個人情報の保護・管理規格を満たしているか
個人情報の保護と管理規格を満たしている電子カルテを選びましょう。満たすべき管理規格は以下の通りです。
- 「ISMS認証(情報セキュリティマネジメントシステム)」
- 「JIS Q 15001(プライバシーマーク)」
上記の管理規格を満たしている電子カルテは、高いセキュリティを誇っていると判断できます。
医療機関は、患者の個人情報など機密性の高い情報を扱うため、高いセキュリティの電子カルテを導入しましょう。
医療機関側が意識しておくべきシステム・運用セキュリティとは?

医療機関側が意識しておくべきシステム・運用セキュリティは、以下の通りです。
- 認証システム
- ファイアウォール
- ウイルス対策ソフト
- データバックアップ
- VPN接続
- 情報セキュリティ教育
- 運用管理規定の設定
電子カルテ仕組みのよくある質問

電子カルテ仕組みのよくある質問は、以下の通りです。
- 紙カルテとの違いとは?
- 電子カルテの種類と違いとは?
- 電子カルテが患者主体の医療につながるわけとは?
それぞれ詳しく紹介します。
1.紙カルテとの違いとは?
保管場所とデータ検索の快適さが、紙カルテとの違いです。
カルテの保管期間は5年と決められているため、保管場所が必要です。大規模の病院であれば、患者数も多いため広い保管場所が必要でしょう。
紙カルテはデータが必要なときに、保管されているカルテの中から探さなくてはいけないため、業務効率が低下します。
電子カルテだと、サーバー上にデータを保管できるうえ、簡単に情報を探せるでしょう。
また、電子カルテがあると職員同士で簡単に情報を共有できるため、業務の効率化が可能です。
2.電子カルテの種類と違いとは?
電子カルテの種類はクラウド型とオンプレミス型、ハイブリッド型の3つに分けられます。
クラウド型は、サーバー上でデータを管理できる電子カルテです。院内にサーバーを設置しなくても、インターネットに接続できる環境であれば利用できます。
オンプレミス型は院内サーバーでデータを管理する電子カルテで、クリニックごとに独自性を出せる自由度の高さが魅力です。
ハイブリッド型はクラウド型とオンプレミス型が融合した電子カルテで、停電など状況に応じて使い分けできます。
3.電子カルテが患者主体の医療につながるわけとは?
電子カルテの導入で患者は自分のカルテを閲覧しやすくなり、診療の目的や治療内容を把握できるようになります。
以前は、患者に治療の内容などが的確に伝えられないこともありました。しかし、電子カルテを導入すると患者がカルテの内容を理解しやすくなるため、主体的に医療を選べるようになります。
まとめ

ここまで、電子カルテの仕組みや電子カルテのメリット・デメリット、セキュリティの高い電子カルテを選ぶポイントなどを紹介しました。
電子カルテは慣れるまでに時間を要する場合があります。ストレスなく電子カルテを利用するには、電子カルテに精通した人材の確保や育成が必要です。
紙カルテから電子カルテへの移行を検討している方は、当記事を参考にセキュリティの高い電子カルテを選びましょう。