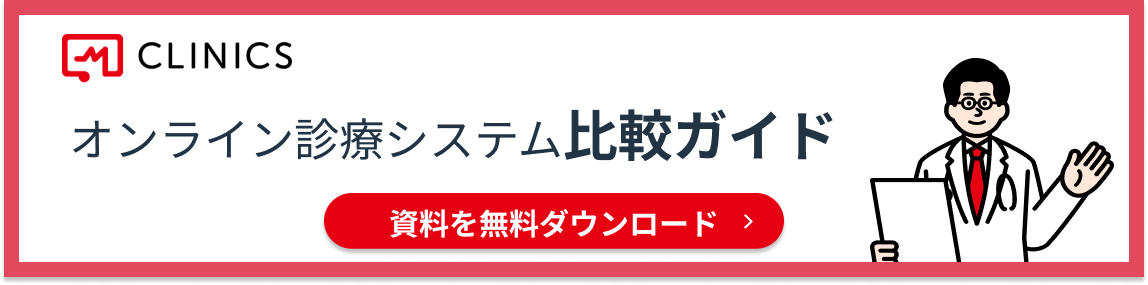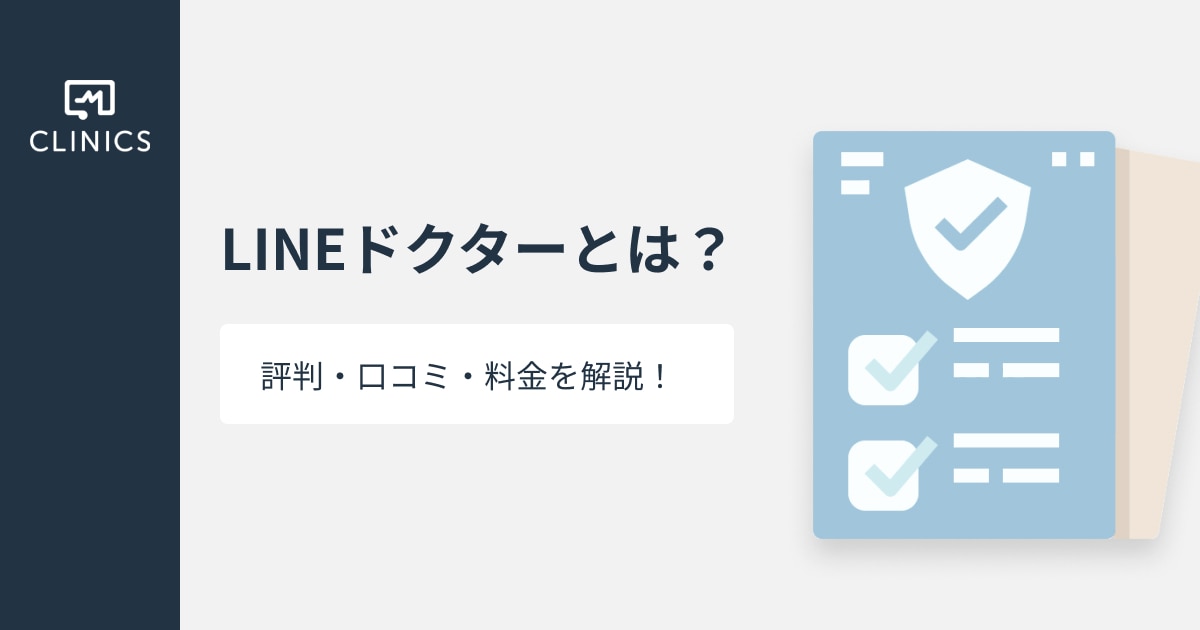
LINEドクターとは?評判・口コミ・料金を解説!
オンライン診療はオンラインで受けられる診療ですが、導入するシステムによって特徴や利用方法が異なるため、医療機関は導入するシステムを慎重に選ばなければなりません。
そこで当記事では、オンライン診療だけではなく決済まで可能な「LINEドクター」について解説します。
目次[非表示]
- 1.LINEドクターとは?
- 1.1.LINEドクターの料金プラン
- 1.2.LINEドクターの特徴
- 1.2.1.シンプルなデザイン
- 1.2.2.予約~決済までをシームレスに行える
- 1.3.導入までの流れ
- 1.4.導入サポート
- 1.4.1.ヘッドセット・Webカメラ
- 1.4.2.スターターキット
- 1.5.LINEドクターの導入事例
- 2.LINEドクターのメリット
- 3.LINEドクターを利用したオンライン診療の手順
- 4.LINEドクターの評判・口コミ
- 5.まとめ
\ 徹底比較 /
オンライン診療システム比較ガイド
LINEドクターとは?

LINEドクターとは、診療予約からテレビ通話での診療、決済までLINEアプリを使用し行うことができるオンライン診療サービスです。
患者はLINEアプリをインストールするだけですぐに使用できるため、LINEを日頃から使用していれば、別アプリをインストールする必要はありません。
参考:LINEドクター - LINEで使えるオンライン診療 | サービスについて
LINEドクターの料金プラン
LINEドクターのBasic Planは初期費用・月額固定費は無料ですが、サービス利用料として、患者へ請求する診療代金の3.5%を負担する必要があります。
現時点ではBasic Plan以外の料金プランはありません。今後サービス・機能の拡充に伴い他のプランも発表される可能性があります。申し込みをする際は、念のため料金プランを確認することをおすすめします。
LINEドクターの特徴
LINEドクターの特徴として次の2つが挙げられます。
- シンプルなデザイン
- 予約~決済までをシームレスに行える
それぞれ詳しくみていきましょう。
シンプルなデザイン
LINEドクターはシンプルな設計となっているため、見やすい画面と簡単な操作で診療業務を行うことが可能です。画面構成もわかりやすいため、複雑なマニュアルを見ながら操作せずともすぐに慣れることでしょう。
予約~決済までをシームレスに行える
医療機関向けシステムで、予約から患者への請求までシームレスに行えます。新規予約や予約キャンセルは、メールやLINEドクターのお知らせ画面で通知されます。
予約状況メニューでは、予約の詳細確認に始まり、担当医師の変更や予約キャンセル、保険証および医療証確認、テレビ通話、請求までをすべて行うことが可能です。なお、アカウントは施設管理者用と医師・スタッフ用で作成でき、それぞれ利用できるメニューが異なります。
予約状況メニューでは患者ごとに「キャンセル」「診療待ち」「通話終了」「請求待ち」といったステータスが表示され、対応漏れを防ぐことができます。診療当日に請求処理漏れが発生した場合は、翌日未処理となっていることをメールで知らせてくれるため、安心です。
導入までの流れ
導入するためには次の5ステップを踏む必要があります。
- 申し込み
- 登録
- 審査
- 契約締結
- 運用スタート
LINEドクターの導入には審査があります。申込内容に問題がなく審査に通れば、契約することが可能です。システムへの登録が完了すれば運用を開始することができます。
審査はなりすまし登録を防ぐ意図で行われるものです。また、複数の施設を一括で申し込むことはできないため、施設ごとに申し込みが必要です。
導入サポート
LINEドクターでは、申込審査が完了し運用可能となった医療機関に対して、次の2アイテムが配布されます。
- ヘッドセット・Webカメラ
- スターターキット
それぞれ詳しくみていきましょう。
ヘッドセット・Webカメラ
運営会社からヘッドセットとWebカメラが順次発送されます。数量限定につき、なくなり次第終了となるようです。
これらは「医師と患者がより円滑にコミュニケーションできるように」との意図で配布されます。したがって不要な場合でも、第三者への転売や目的外の使い方はしないようにしましょう。また、LINEドクターの運用を終了した際には廃棄するようにとの注意書きもされています。
スターターキット
LINEドクターを導入したことが一目でわかるポスターやステッカーが入った専用スターターキットも配布されます。こちらも、運用可能となった医療機関に順次発送されるため、活用しましょう。
その中には、患者に配布できるQRコードが印刷されているクリニックカードも含まれています。患者はQRコードを読み込めば、LINEドクター内のクリニックのページに直接アクセス可能です。
LINEドクターの導入事例
LINEドクターは内科、小児科、耳鼻科、皮膚科、心療内科といった、さまざまなクリニックでの導入事例があります。いずれの医科でも、外来とLINEドクターでのオンライン診療を組み合わせ、患者の状態によって判断しているようです。
その中で「特に心療内科はLINEドクターとの相性がいいのではないか?」との意見がありました。心療内科や精神科の受診に対して抵抗がある人や、症状や服用している薬によっては外出困難な人もいるためです。
また、リモートワークで通院しづらくなった患者、小さな子どもがいる患者、妊娠している患者も受診しています。
LINEドクターのメリット

LINEドクターを導入することで、クリニックに来院する患者が減少します。そのため、院内感染予防とともに待ち時間に苛立つ患者からのクレームによるストレスを軽減できるメリットがあります。
患者にとってのメリットは、LINEアプリをインストールしていればすぐに使用でき、自宅で診察時間まで自由に過ごせる点です。他にも、感染リスクに対する不安により通院をためらう患者も受診できます。
LINEドクターを利用したオンライン診療の手順

LINEドクターを利用したオンライン診療の手順は次の7ステップです。
- 施設の情報設定
- 医師のアカウント発行
- 診療スケジュールの設定
- テスト診療実施・医師のアカウント公開
- オンライン診療案内
- 予約確認・診療実施
- 請求
LINEドクターにおける診療費用の決済方法は「LINE Pay」と「クレジットカード」の2種類です。
LINEドクターの評判・口コミ

インターネット上にあるLINEドクターに関する口コミは、肯定的な意見と否定的な意見が混在しています。長期的に通院している患者からは、通院する機会が減ることは非常に嬉しいといった肯定的な意見がありました。
医師といつも変わらないやりとりをし、毎回同じ薬を処方してもらうために通院するのは疲れてしまうからといった意見です。一方、否定的な意見としては、個人情報の扱いについて不安の声が多くみられました。
\ 徹底比較 /
オンライン診療システム比較ガイド
まとめ

LINEドクターは、院内感染の予防に貢献するとともに、通院が困難なさまざまな患者にとっては気軽に利用できる有効なツールです。長期的に投薬が必要な患者も、薬をもらうためだけにクリニックに足を運ぶ必要もなくなるといったさまざまなメリットがあります。
また、来院患者が減ることで患者からの待ち時間に関するクレームが減少することにも期待でき、クリニックにとっても患者にとってもストレスを軽減できるツールとして活用できることでしょう。