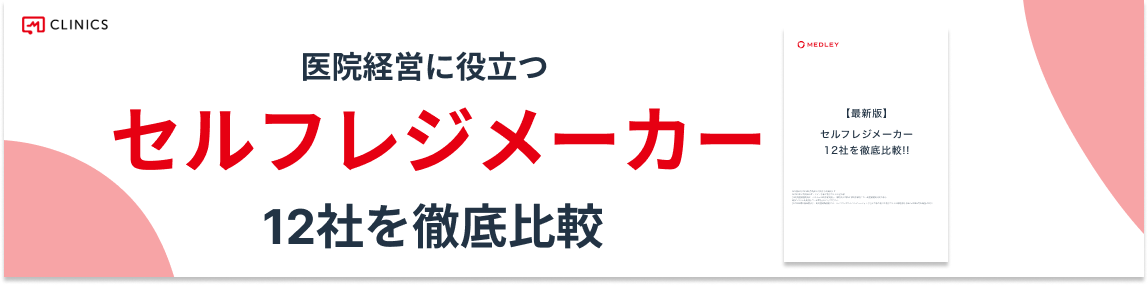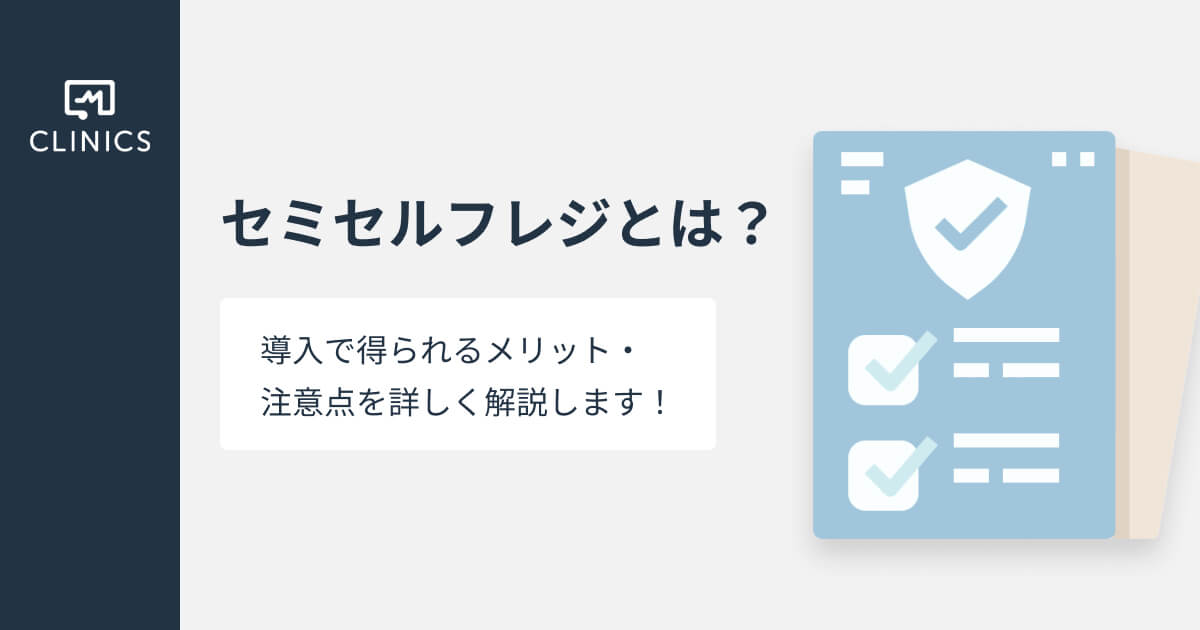
セミセルフレジとは?導入で得られるメリット・注意点を詳しく解説します!
受付の負担を減らす手段として、セミセルフレジの導入を検討されているクリニックは多いのではないでしょうか。最近ではスーパーやコンビニだけでなく、医療機関でも導入が増えてきています。しかし、セミセルフレジにもさまざまな種類や機能があり、その違いを見分けるのは容易ではありません。
そこで、本記事では、セミセルフレジに関する基礎知識から導入で得られるメリット・注意点について解説していきます。導入検討の材料として、お役立てください。
目次[非表示]
- 1.セミセルフレジとは?
- 1.1.セミセルフレジの特徴
- 1.2.セルフレジ(自動精算機)との違い
- 1.3.POSレジとの違い
- 2.セミセルフレジの導入状況
- 3.セミセルフレジ導入で得られるメリット
- 3.1.レジ締め作業が効率化できる
- 3.2.会計ミスの防止につながる
- 3.3.患者の待ち時間が短縮できる
- 3.4.多彩な決済方法に対応できる
- 3.5.感染予防・対策につながる
- 4.セミセルフレジを導入する際の注意点
- 4.1.設置スペースを確保できているか
- 4.2.電子カルテ・レセコンとの連携は可能か
- 4.3.メーカーのサポート体制が十分か
- 4.4.故障のトラブルに対応できる体制が取れるか
- 4.5.大幅な人員削減は見込めない
- 4.6.現金の取り扱いルールは明確になっているか
- 4.7.新紙幣への切り替えに対応しているかどうか
- 5.おすすめのセミセルフレジメーカー
- 6.セミセルフレジについてよくある質問
- 6.1.セミセルフレジはどうやって使うの?
- 6.2.セミセルフレジ導入に意味はあるの?
- 7.まとめ
セミセルフレジとは?

セミセルフレジは自動釣銭機とも呼ばれ、受付と会計の業務効率化に役立ちます。具体的な内容について、以下3項目を解説するため参考にしてください。
- セミセルフレジの特徴
- セルフレジ(自動精算機)との違い
- POSレジとの違い
セミセルフレジの特徴
セミセルフレジは、現金の支払いと釣り銭の計算・払い出しが機械だけで完結します。一般的には、通常のレジスターに電子端末を設置したもので、医療機関では、バーコードを使って電子カルテと連携して運用するケースが多いです。
会計の案内をした後は患者自身が精算するため、スタッフが釣り銭を計算する手間が省け、窓口業務の負担が軽減できるでしょう。
セルフレジ(自動精算機)との違い
セミセルフレジとセルフレジ(自動精算機)との主な違いは、金額の表示から支払い、釣り銭の受け取りまでが自動かどうかです。セルフレジは患者が会計を完結させるため、スタッフの手間が大きく削減される点が最大のメリットです。
一方、セミセルフレジの場合は、スタッフが伝票を読み取り(会計前処理)、合計金額を提示したうえで、患者に精算機で料金を支払うよう案内します。一見すると、セルフレジの方がスタッフの手間を削減できるため魅力的に感じますが、セミセルフレジの方が金額は安く、設置スペースが小さいため、導入しやすい傾向にあります。
また、形態も異なっておりセルフレジは、自立型と卓上型の2種類、セミセルフレジは卓上型がメインです。加えて、セルフレジは電子カルテとシステム連携し、患者情報を共有する運用が一般的に見られるスタイルであり、セミセルフレジは、バーコードを活用して金額を読み取るやり方が一般的です。
POSレジとの違い
「セミセルフレジ」と「POSレジ」は似ており、セミセルフレジの中にPOSレジが搭載されているものもあり、明確な違いを定義することは困難です。ただ、大枠としてそれぞれは異なる役割を持ちます。
POSレジは、販売時点情報管理とも呼ばれ、販売情報を管理することが目的のシステムです。POSシステムを通じて商品の販売情報や分析が可能であり、店舗の販売戦略を策定するのに役立ちます。売上のタイミングや金額を把握することも可能です。
一方、セミセルフレジは金銭の授受・釣り銭の計算と払い出しを自動化するレジです。
セミセルフレジの導入状況

セミセルフレジは、現在セルフレジ(自動精算機)よりも広く普及しています。セミセルフレジは、筐体がよりコンパクトであるため、規模の小さいクリニックでも動線を阻むことなく運用できる点が評価されています。
また、導入費用に関しても自動精算機と比較するとより安価であるため、導入のハードルは低い傾向です。
セミセルフレジ導入で得られるメリット

セミセルフレジの導入により得られるメリットは以下のとおりです。それぞれ詳しく解説するため、自院の状況と照らし合わせながらご覧ください。
- レジ締め作業が効率化できる
- 会計ミスの防止につながる
- 患者の待ち時間が短縮できる
- 多彩な決済方法に対応できる
- 感染予防・対策につながる
レジ締め作業が効率化できる
セミセルフレジは、精算部分を機械で行うため集計作業が自動化されており、レジ締め作業がスムーズになります。
一般的なレジの場合、集計作業や現金の計算などはスタッフが手で行うため、時間と負担がかかってしまい、ミスも発生しかねません。
セミセルフレジを導入すれば、スタッフの業務を効率化でき、スタッフ満足度も向上するでしょう。
会計ミスの防止につながる
セミセルフレジの導入は、会計ミスの防止に効果的です。従来のレジでは、釣り銭を渡す際にスタッフが手作業で金銭を数える必要がありました。
しかし、セミセルフレジは自動かつ正確な釣り銭を出金するため、ヒューマンエラーのリスクが大幅に低減されます。業務のストレスが軽減され、患者サービスの向上にも寄与するでしょう。
患者の待ち時間が短縮できる
通常、診察終了後にスタッフが電子カルテやレセコンで支払額を算出し、レジ操作をしてから金銭授受までの流れが会計の一般的な流れです。セミセルフレジを活用すれば、患者自身が入金処理をするため、レジ操作と金銭授受の手間が省けます。
その結果、スタッフの負担が減り、別の業務に時間を割けるため、患者の待ち時間短縮につなげられます。
多彩な決済方法に対応できる
セミセルフレジは、現金だけでなく、さまざまな決済手段に対応しています。最新のセミセルフレジでは、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済などの支払い機能が搭載されているものがほとんどです。
キャッシュレス化が進み、現金以外での支払いを希望する患者も多く見られます。複数の決済手段を用意しておくと患者満足度も向上するでしょう。
また、自費診療を導入している医療機関であれば、支払いが高額になる場合も珍しくありません。その際、クレジットカードでの支払いが可能であれば、ATMに行く手間も省け、未収金発生の防止にもつながります。
感染予防・対策につながる
セミセルフレジの導入により、感染対策が強化されます。入金は患者自身が行うため、スタッフが紙幣や硬貨に触れる必要がありません。
また、電子マネーやQRコード決済を導入できるタイプもあり、接触リスクを軽減できます。そのため、セミセルフレジの導入によって感染のリスクを最小限に抑えられます。
セミセルフレジを導入する際の注意点
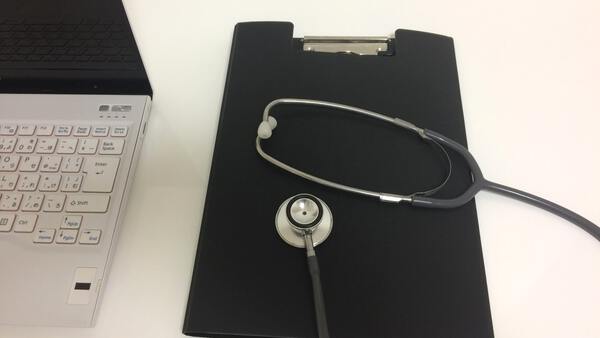
失敗しないセミセルフレジ導入のためには、以下7つの注意点をおさえておく必要があります。それぞれの内容について、チェックリストの要領でご確認ください。
- 設置スペースを確保できているか
- 電子カルテ・レセコンとの連携は可能か
- メーカーのサポート体制が十分か
- 故障のトラブルに対応できる体制が取れるか
- 人員削減はあまり見込めない
- 現金の取り扱いルールは明確になっているか
- 新紙幣への切り替えに対応しているかどうか
設置スペースを確保できているか
セミセルフレジの導入に際して、まず考慮すべきポイントが設置スペースです。新規開業の場合は、セミセルフレジの導入を想定した内装にすれば、スムーズに設置できる環境を整えられます。
しかし、既に開院済みの場合は、場所に余裕がないケースも考えられます。対策として、メーカーに設置予定場所の寸法を提供し、スマートに設置できるかどうかの判断を仰ぐとよいでしょう。
また、設置場所を決定する際には、患者やスタッフの導線も重要です。スムーズな操作と利便性を確保するために、どの場所に置くと適切かを慎重に検討しましょう。
さらに、ビス止めが可能かどうかもチェックすべきポイントです。災害時の予期せぬ事故を防ぐ観点から、固定できるかを確認しておく必要があります。
電子カルテ・レセコンとの連携は可能か
セミセルフレジの導入に際して、電子カルテやレセコンとの連携が可能かどうかも重要なポイントです。具体的な連携方法としては「データ連携」と「バーコード連携」の2つが挙げられます。
データ連携では、会計担当者との突合や予約システムの案内など、一連の業務を効率的に運用が可能となります。一方のバーコード連携は、データ連携ほどの機能はありませんが、バーコードの読み取りによって会計金額の入力ミス防止が可能です。
セミセルフレジの導入によって、具体的に何がどこまで解決できるかをスタッフと十分に話し合い、検討を進めるようにしましょう。
メーカーのサポート体制が十分か
メーカーのサポート体制が十分であるかも確認しておきましょう。システムの部分と筐体の部分でメーカーのサポート内容が分かれている場合があります。
また、土日・祝日に診療を行っているクリニックの場合、土日・祝日の対応についても、チェックしておきましょう。
迅速に問題解決できるよう、導入前にシステムと筐体、それぞれの連絡先を確認しておく必要があります。
故障のトラブルに対応できる体制が取れるか
セミセルフレジを導入する際は、使いやすいかどうかだけでなく、思わぬ故障トラブルへの対策が重要です。例えば、患者が持ってきた紙幣や硬貨によってレジがつまる可能性も考えられます。
その際、スタッフが適切な対処ができるように、マニュアルを作成したり、OJTを施したりして、セミセルフレジが故障した際の対策を検討しましょう。
大幅な人員削減は見込めない
セミセルフレジは、支払い手続きは患者自身で行います。しかし、精算までの準備や案内は、通常のレジと同様スタッフの対応が必要です。また、操作に不慣れな患者もいるため、適切なサポートができるようにしておかなければなりません。
セルフレジのように、すべての工程を患者だけで完結する訳ではないため、人員削減ではなく、スタッフの手間を減らす観点で導入を進めましょう。
現金の取り扱いルールは明確になっているか
セミセルフレジの導入にあたり、現金の取り扱いルールを明確にしておきましょう。毎日現金を引き出して、金庫に預けるか、セミセルフレジ自体を金庫として扱うかを明確にルール決めしておくと、導入後の運用がスムーズです。
なお、セミセルフレジは、一般のレジのように中身を持ち運ぶ運用は想定されていないため、注意が必要です。
新紙幣への切り替えに対応しているかどうか
セミセルフレジを導入する際には、新紙幣へ対応できる機種の選定が重要です。具体的な対応策について以下の点を確認しておきましょう。
- システムのアップデートで新紙幣に対応するのか、筐体自体を入れ替えて対応するのかを確認する
- 入れ替え作業の準備から完了までにかかる期間を把握する
- 切り替えにともなう費用や見積もりをメーカーに問い合わせて算出する
おすすめのセミセルフレジメーカー

以下の関連記事では、おすすめのセミセルフレジメーカーを9社ピックアップして紹介しています。
各メーカーの特徴も詳しく解説しているため、比較検討の際にぜひ参考にしてください。
セミセルフレジについてよくある質問

セミセルフレジについてよくある質問を2つピックアップしたので解説していきます。
- セミセルフレジはどうやって使うの?
- セミセルフレジ導入に意味はあるの?
セミセルフレジはどうやって使うの?
セミセルフレジの使い方はシンプルです。まず、スタッフが会計に必要な処理を実施し(レジ操作)、そのあと患者が精算機で入金手続きをします。
入金が完了すると、レシートが自動的に印刷されたりお釣りが出たりします。一般のレジとは精算の部分が変わりますが、マニュアル整備やメーカーサポートがあれば、それほど負担なく導入できるでしょう。
セミセルフレジ導入に意味はあるの?
スタッフの手間削減や、患者の待ち時間短縮への効果が期待できます。精算部分が患者と機械で完結することで、スタッフは受付や会計準備など、他の業務に対応することができます。結果として患者の待ち時間が短縮できるようになるでしょう。
まとめ
セミセルフレジは、会計前の処理をスタッフが担当しますが、入金手続きはすべて患者自身が行います。
スタッフは会計業務の負担軽減が図れ、患者は待ち時間が短縮されるため、双方にメリットをもたらすでしょう。ただし、セミセルフレジの導入にはコストや患者への操作負担などの注意点も存在します。これらを正しく理解し、適切な導入の検討が重要です。