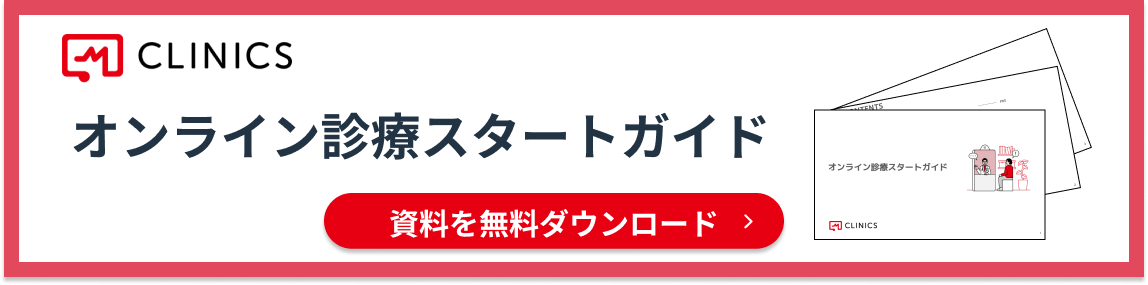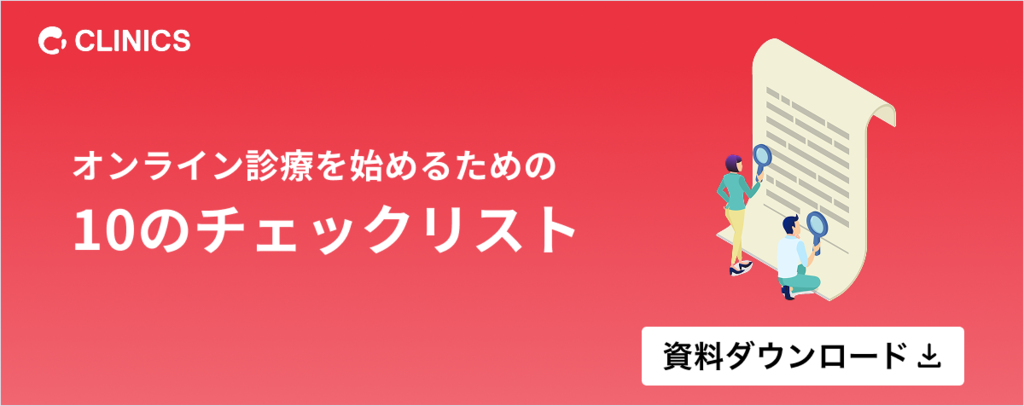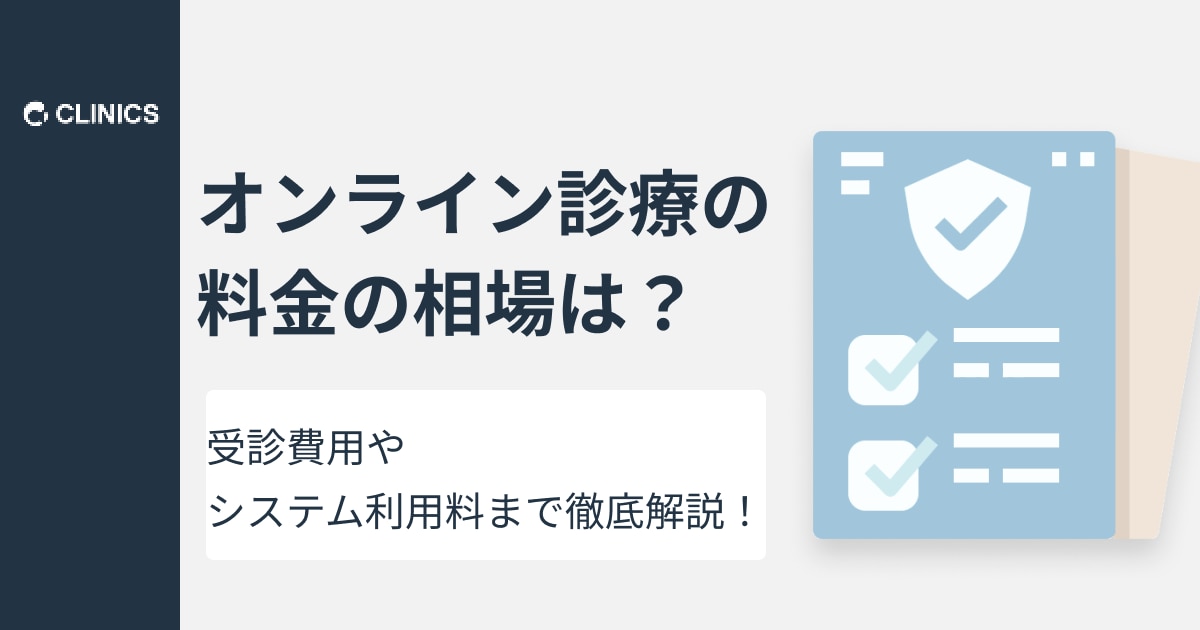
オンライン診療の料金の相場は?受診費用やシステム利用料まで徹底解説!
「オンライン診療の開始を検討しているが、発生する費用がわからない」
「導入した場合、患者さんはどのような流れで利用するのかを把握したい」
クリニックを経営する方のなかには、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。本記事では「オンライン診療に必要な料金」や「患者さんが利用する際の流れ」を解説します。オンライン診療導入の検討にお役立てください。
目次[非表示]
オンライン診療とは

厚生労働省は、オンライン診療を以下のように定義づけています。
「オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です」
引用:厚生労働省「オンライン診療について」
オンライン診療は、新型コロナウイルスの流行がきっかけとなり注目された、医師と患者が直接接触しない診察方法です。2020年に「対象疾患の制限」や「初診以降の対面診療期間の制限」などが特例措置として緩和されました。さらに、2022年の診療報酬改定では、2020年に特例で緩和された制限が、おおむね恒常化。その後も診療報酬の引き上げが続くなど、現在はオンライン診療を導入しやすい環境といえるでしょう。
これまで同様、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症療養中の方の診察にもオンライン診療が有用といえます。加えて、生活習慣病のように定期的な通院が必要な方の診察にも活用可能なため、患者さんにとっても「通院負担が減る」「治療が継続しやすい」などのメリットがあります。
CLINICSでは、オンライン診療に関する情報をまとめた「オンライン診療スタートガイド」を無料配布しています。こちらからダウンロードできるため、オンライン診療の導入を検討している方は情報収集にお役立てください。
オンライン診療・服薬指導の流れ

患者さんがオンライン診療を受診する際の簡単な流れは以下のとおりです。
予約
患者さんがスマートフォンやパソコンなどを使用して予約します。予約時には、担当医師や希望の日時、問診票などの入力が必要です。
↓
オンライン診療
医療機関側からの連絡を受け、医師と映像・音声をつなげてオンライン診療を受けます。その際、医療機関側が指定するアプリケーションを使用した診察が一般的です。
↓
会計(診察料)
診察が終わったら、診療に関する費用を支払います。クレジットカードで支払う場合、患者が事前に登録したクレジットカードに診察料が請求されます。クレジット決済が難しい場合は、来院時にまとめて支払うのが一般的です。
↓
服薬指導と会計(調剤料)
薬剤師からオンラインで服薬指導を受け、服薬指導の費用をクレジットカードで決済します。
決済後1〜3日程度で患者が指定した場所に薬が郵送され、オンライン診療は終了です。
オンライン診療に関する料金の内訳
オンライン診療では、診察料に加え、システム利用料など特有の費用も発生します。
オンライン診療に関する費用についてクリニック視点で見ていきましょう。
システム利用料
導入時にかかる初期費用と、毎月発生する月額利用料があります。メーカーによって料金体系は異なり、初期費用を抑えたプランや、診療件数に応じた従量課金制を採用しているケースもあります。
オンライン決済手数料
患者さんがクレジットカード等で支払う場合、診療代やサービス料の合計額に対して3.5〜4%程度の決済手数料が発生します。この手数料はシステム経由で自動的に差し引かれるのが一般的です。
配送および事務コスト
院内処方をした際の薬剤郵送費、処方箋を薬局へ送付する通信費など、オンライン診療特有のコストが発生します。これらは、事前に患者さんへ説明し同意を得た上で、「システム利用料」や「療養の給付と直接関係ない費用」として1,000円〜2,000円程度を請求することも可能です。この運用により、医療機関側の持ち出し費用を抑え、安定したシステム運用につなげることができます。
オンライン診療の支払い方法については、下記の記事もあわせてお役立てください。
オンライン診療で料金トラブルを防ぐには
オンライン診療では、従来の対面型診療と料金体系が異なります。
前述のとおり、システム手数料や決済手数料を患者さん負担とする場合、料金トラブルが生じるリスクがあるため注意が必要です。患者負担とする場合は、費用の内訳について患者に説明したうえで同意を得ることが大切です。また、トラブルを予防するために、院内での周知も徹底し、患者さんの理解を深めましょう。
オンライン診療の料金に関するよくある質問

オンライン診療に関するよくある質問は次の3つです。
Q1.そもそも該当の患者さんがいるかわからない
自院を利用する患者さんのニーズを把握するには、アンケートが有効です。アンケートを実施する具体的な方法として、年齢・疾患を分ける方法があります。
オンライン診療は、慢性疾患の方が利用しやすい傾向があります。しかしクリニックによって診療科目が異なるため、クリニックの患者において「どのような疾患を持つ方がオンライン診療の利用を希望しているか」をアンケートを通じて確認しましょう。年齢を絞らずに幅広くアンケートを実施することもポイントです。例えば「高齢の方がスマートフォンを活用している」「若年層の方が医師と毎月対面して相談したい」といった幅広いニーズが把握できる場合があります。
年齢・疾患を分けて、まとめて30~50名程度にアンケートが実施できれば院内の需要が把握できます。最初は該当患者のみにオンライン診療を順次案内し、需要が拡大したら本格的にスタートする方法も。需要に応じて、導入の準備を進めましょう。
Q2.オンライン診療は自費がメインなのでは?
コロナ禍を契機に、保険診療でのオンライン診療の利用が普及しています。株式会社メドレーの集計では、オンライン診療を利用する70%近くが保険診療です(※2021年3月末時点)。患者さん側の利用場面として、例えば「検査結果の説明を受ける」や「慢性疾患の通院に活用する」などの幅広いケースがあります。
Q3.一般的なビデオ通話システムとの違いは?
一般的なビデオ通話システムとの違いは「予約管理」と「決済」まで可能な点です。ZoomやGoogle meetなどの一般的なビデオ通話システムは「ビデオ通話のURLを患者へ送付する」「受診料を振込や来院時に決済する」などの手間がかかります。決済においては患者の行動に委ねられるため、未収金発生のリスクが伴います。
一方オンライン診療システムでは、「予約」から「決済」まで対応できるため、オンライン診療を実施するうえでの手間や準備にかかる負担の少なさが特徴です。また、未収金発生のリスク低減だけでなく、院内の業務効率化にもつながります。
まとめ

導入するオンライン診療システムによって、クリニックが支払う料金は異なります。例えば患者さんの費用負担を軽減したい場合は、患者さん側に手数料が発生しないオンライン診療システムを導入する必要があります。本記事で紹介したオンライン診療に必要な料金を参考に、自院への導入を検討しましょう。