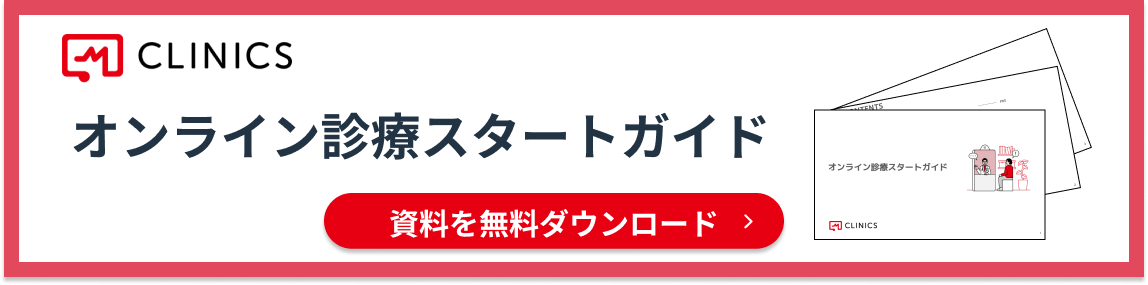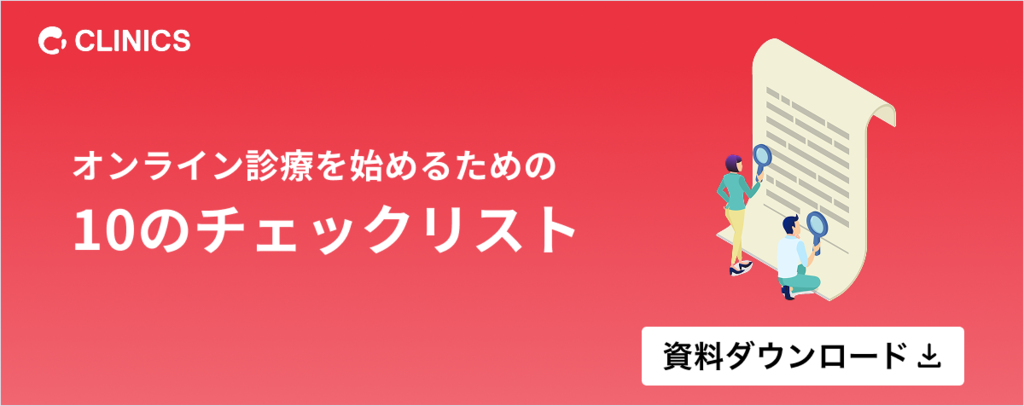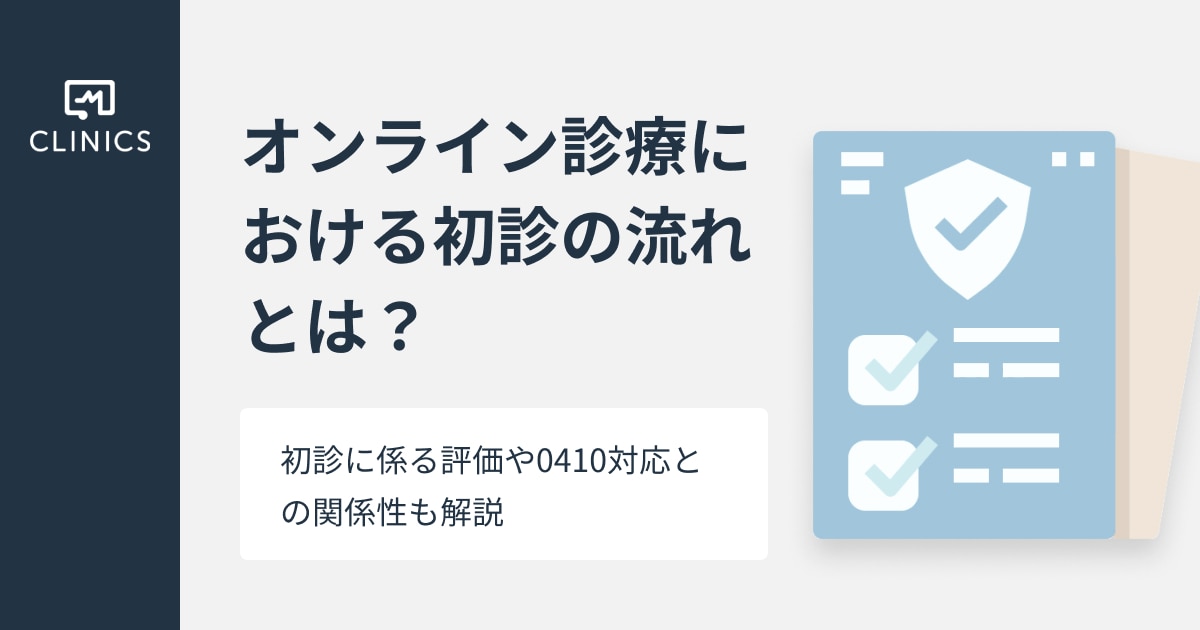
オンライン診療における初診の流れとは?初診に係る評価や0410対応との関係性も解説します
「オンライン診療の初診の流れがわからない」
「情報通信機器を用いた初診に係る評価が知りたい」
オンライン診療未導入の場合、オンライン診療における初診の流れや初診料など具体的にわからない医療機関の方もいるでしょう。当記事では、情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設やオンライン診療における初診の流れなどを紹介します。
目次[非表示]
- 1.情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
- 1.1.初診における算定要件
- 1.2.施設基準
- 2.オンライン診療における初診の流れ
- 2.1.1.患者との合意形成
- 2.2.2.診療前の相談を実施
- 2.3.3.診療計画の説明・合意
- 2.4.4.オンライン診療の実施
- 3.0410対応と令和4年度診療報酬改定の関係性とは?
- 4.オンライン診療初診でよくある質問
- 4.1.1.オンライン診療とは?
- 4.2.2.新設された初評である「初診」について
- 4.3.3.新設された「再診」について
- 4.4.4.医学管理料について
- 4.5.5.在宅医療について
- 5.まとめ
情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設

新型コロナウイルス感染症の流行で、オンライン診療のニーズが増加しています。ニーズの増加に伴い、令和4年度からオンライン診療の初診・再診が開始し、情報通信機器を用いた初診に係る評価が新設されました。
情報通信機器を用いた初診・再診の診療報酬は次の通りです。
- 情報通信機器を用いた場合の初診料:251点
- 情報通信機器を用いた場合の再診料:73点
- 情報通信機器を用いた場合の外来診療料:73点
続いて、以下についてそれぞれ詳しく紹介します。
- 初診における算定要件
- 施設基準
初診における算定要件
初診における算定要件に関して、次の項目が定義されています。
(1 )保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
(2) 情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。
なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(3) 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。
なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
(4) 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。
ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
- 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
- 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
(5) 指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。
また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
(6) 情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
施設基準
施設基準に関して、次の項目が定義されています。
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにあたって十分な体制が整備されていること。
(2) 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って、診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
オンライン診療における初診の流れ

オンライン診療における初診の流れは、以下の通りです。
- 患者との合意形成
- 診療前の相談を実施
- 診療計画の説明・合意
- オンライン診療の実施
それぞれ詳しく紹介します。
1.患者との合意形成
オンライン診療の際は、最初に患者との合意形成が必要です。合意形成は患者と医師の信頼関係構築を目的に行われ、患者が安心してオンライン診療を受けられるような働きかけが求められるでしょう。
医師は患者に対して以下のように説明します。
- オンライン診療では触診できないため、得られる情報には限界があり対面診療と組み合わせる必要がある
- オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否を判断する
- 「診療計画」(後述)に含まれる事項
上記3点の説明がメインですが「診療計画」(後述)に含まれる事項の内容説明も必要です。医師の説明に対して患者の同意を得られたら、診療前の相談に移ります。
2.診療前の相談を実施
オンライン診療を始める前に、診療前診断を実施します。
他院からの情報提供書などの書類があれば、初診であってもオンライン診療が可能です。しかし医学的な情報が無い場合は、医師がその場でオンライン診療の可否を判断しなくてはなりません。
3.診療計画の説明・合意
オンライン診療実施前には、診療計画の説明と合意が必要です。
診療計画には患者と医師間のルールが記載されています。医師は、合計9項目の診療計画を患者に説明しなければなりません。
診療計画に記載されている9項目は、以下の通りです。
- 具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
- オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)
- 診療時間に関する事項(予約制等)
- 使用する情報通信機器等
- オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む。)
- 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
- 急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)
- 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示
- 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲及びそのとぎれがないこと等の明示
参照:診療計画
4.オンライン診療の実施
患者に診療計画に目を通してもらい同意を得られたら、オンライン診療開始です。医師が本人確認した後、患者の状態を確認していきます。
オンライン診療に使用するツールはクリニックごとに異なるため、事前に何を使用するか確認しておきましょう。
0410対応と令和4年度診療報酬改定の関係性とは?

医療機関は、オンライン診療する際に0410対応と令和4年度診療報酬改定ルールどちらでも選べるようになりました。
しかし0410対応を利用すると、診療報酬の点数241点で令和4年度診療報酬改定ルールの点数251よりも低い評価になります。高評価を得るために、施設基準の届出が求められるようになりました。
オンライン診療初診でよくある質問

オンライン診療初診でよくある質問は次の通りです。
- オンライン診療とは?
- 新設された初評である「初診」について
- 新設された「再診」について
- 医学管理料について
- 在宅医療について
ここでは、オンライン診療初診でよくある質問について回答していきます。
1.オンライン診療とは?
オンライン診療とは、自宅にいながらスマートフォンやパソコンなどの端末で患者を診察できるシステムです。オンライン診療の導入により患者の通院負担軽減や、院内感染の予防などさまざまなメリットがあります。
2.新設された初評である「初診」について
初診では「医療機関と患者の家までの距離が概ね30分以内」「オンライン診療料の算定を1割以下」が撤廃されました。新設された初診では、情報通信機器を用いて実施した場合の初診報酬が251点と定義されています。
3.新設された「再診」について
再診に関して「オンライン診療費」「医療機関と患者の家までの距離が概ね30分以内」「オンライン診療料の算定を1割以下」が撤廃されました。また、新設された項目は以下の通りです。
- 情報通信機器を用いた場合の再診料:73点
- 情報通信機器を用いた場合の外来診療料:73点
4.医学管理料について
医学管理料は、算定可能な医学管理料を整理、追加して点数を引き上げています。具体的な内容は以下の通りです。
- 検査処置等を伴わない医学管理料を算定可能として追加して、現行の9種類から20種類へ増加
- 点数はすべて対面の場合87%に設定
5.在宅医療について
在宅医療は、在宅時医学総合管理料において活用場面を整理・拡大し、施設入居時等医学総合管理料にも対象を拡大しています。具体的な内容は以下をご覧ください。
- 「2月に1回の在宅診療と2月に1回のオンライン診療」「月1回の在宅診療と月1回のオンライン診療」の場合の点数を新設
- 施設入居時等医学総合管理料においても、同様の類型を新設
まとめ

ここまで、情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設やオンライン診療における初診の流れなどを紹介しました。オンライン診療は、新型コロナウイルス感染症の影響によりニーズが高まっています。
令和4年度からはオンライン診療の初診・再診がスタートして、初診に係る評価が新設されました。オンライン診療の初診の算定要件や、受診の流れが曖昧な方は当記事を参考にしてください。