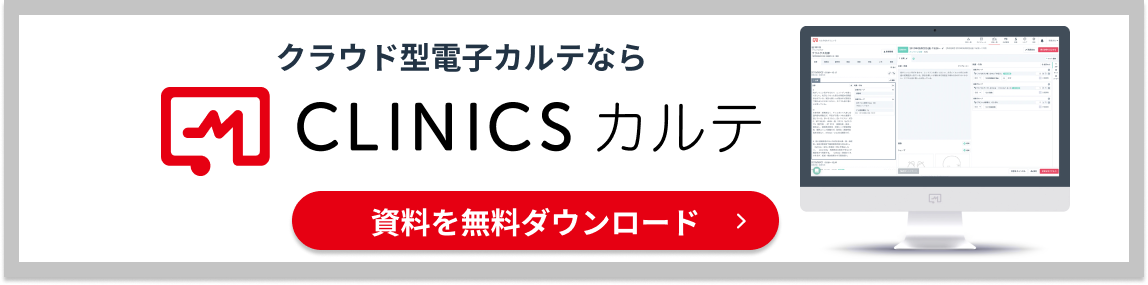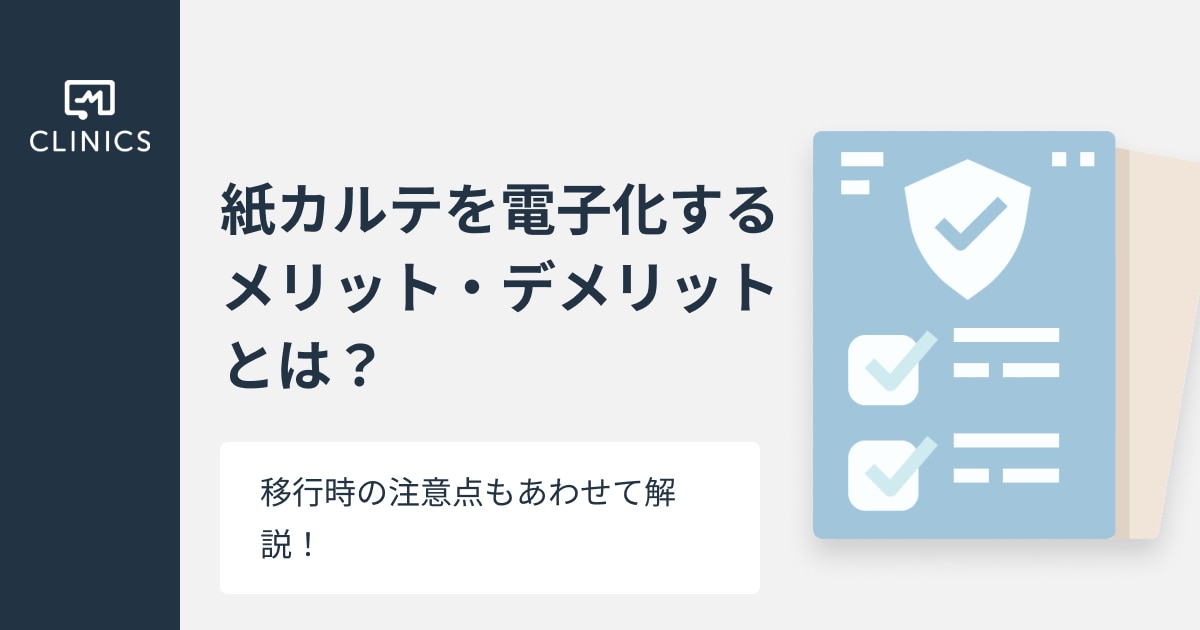
【最新版】紙カルテを電子化するメリット・デメリットとは?移行時の注意点もあわせて解説!
本記事では電子カルテへの移行メリットはもちろん、移行時に気を付けるべき注意点などについて解説します。
目次[非表示]
紙カルテから電子カルテに移行するメリット
紙カルテから電子カルテへ移行するメリットを紹介させていただきます。
1.保管スペースを減らせる
紙カルテの大きなデメリットは保管スペースです。患者数の増加に比例してカルテの量も膨大となるため、その分保管スペースを確保する必要がありました。 一方、電子カルテであればデータ化してサーバー内に保管できます。そのため、患者数が増えても紙カルテのように保存スペースを増やす必要がありません。 さらに、電子化以前の紙カルテを電子カルテにスキャンして取り込むことで、現在の保管スペースも減らせます。
2.カルテの劣化が存在しない
紙カルテの場合、外部・内部要因が影響し時間経過とともにカルテ劣化していきます。
劣化することにより文字の読み取りが不可能になる可能性もあります。
一方、電子カルテに移行することにより、上記の懸念がありません。
3.情報をリアルタイムに共有できる
電子カルテであれば、入力や編集などによって更新された新しい情報をリアルタイムで共有することが可能なので院内業務の効率化ができます。
4.ヒューマンエラーを防止できる
電子カルテを導入することで、算定漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを未然に防止できます。また、紙カルテとは異なり、記入者の字の特徴を読み解く必要がなく、医師の指示を的確に把握できる点も大きな特徴といえるでしょう。その結果として、間違いや勘違いを原因とする医療事故の未然防止にも効果があります。
5.検査結果をシステムに取り込める
紙カルテの場合は、検査会社の検査結果を受け取るまでに数日間から1週間程度を要します。一方、電子カルテであればデータの取り込みによって検査結果をすぐに反映することが可能です。 また、検査会社や利用するシステムによっては結果がオンラインでアップロードされるため、取り込みの操作自体が不要となるケースもあります。
6.業務負担を軽減できる
業務負担を軽減できる点も電子カルテの大きなメリットの1つです。前述の通り、記入するという行為がなくなるため、字の特徴を読み取る必要がありません。 そのため、医師の指示を的確に把握できるのはもちろんのこと、読みにくい文字について医師に確認していた手間を省くことができます。 また、情報をリアルタイムに共有できることから、診療情報提供書などの文書作成や処方などのオーダーリングといった複数の業務の時間短縮につながるでしょう。
紙カルテから電子カルテに移行するデメリット
紙カルテから電子カルテへ移行するデメリットを紹介させていただきます。
1.停電が起こると利用できない
電子機器で構成される電子カルテは、停電などによって電力供給がストップすると利用できません。そのため、災害の発生時には患者の受け入れ対応が困難になる可能性があります。 そのため、万が一に備えて電力が復旧するまでは紙カルテや検査伝票に一時的に切り替えるための備えや訓練が必要です。また、ノートパソコンやタブレットなどを用意して、停電時でも対応できる環境の構築が欠かせません。
2.業務フローの変更が必要になる
電子カルテへ移行する際は、従来の業務フローに大きな変更を加えることになります。例えば、医師によってカルテの入力内容に違いがあったり、システムの導入・刷新によってこれまでの帳票が使用できなくなったりするケースもあるでしょう。 そのため、入力内容をテンプレート化したり、帳票の代替手段を用意したりといった対策が必要です。また、操作に慣れるまでは業務効率が低下することも考慮しながら、余裕を持って移行を進めなければなりません。
3.セキュリティ対策を施す必要がある
カルテがデータ化された場合、サイバー攻撃や内部不正などによって情報が漏洩する恐れがあります。また、USBメモリなどを利用すれば大量のデータを簡単に外へ持ち出せるため、ヒューマンエラーによる漏洩リスクも高まりかねません。 そのため、ログ管理やアクセス制限などの入念なセキュリティ対策を施す必要があります。ちなみに、クラウド型の電子カルテであればデータは病院内に蓄積されず、クラウド上でセキュリティ対策も施されているため安心です。
紙カルテから電子カルテへ移行するステップ
紙カルテから電子カルテへの移行メリットはご理解いただけたかと思います。
本セクションでは具体的に、どのように移行するのかについて解説していきます。

- 紙カルテの情報を電子カルテへ入力(紙カルテへスキャンしてPDF化する方法もあります)
- 電子カルテ操作の研修をする
- 電子カルテへ完全に切り替える
いきなり、完全移行を目指すのではなく、徐々に移行を行っていくことがポイントになります。
電子カルテ更新について詳細な情報をまとめているガイドブックも弊社では用意させていただいております。以下よりダウンロード可能ですので、ぜひご確認ください。
紙カルテを電子化する際のガイドライン

紙カルテの電子化は、医療現場の効率化や情報管理の向上に寄与する重要な取り組みです。しかし、電子化を進める際には、適切な手順とガイドラインに従うことが求められます。
ここでは紙カルテを電子化する際のガイドラインについて詳しく解説します。
300dpi、RGB各8ビット以上でスキャンする
紙カルテを電子化する際には、スキャンの解像度と色の設定が重要です。推奨される設定は「解像度が300dpi、色の深さがRGB各8ビット以上」です。手書きの文字や細かな図表が鮮明になり、読みやすさや情報の正確性を保つことができます。
特に文字が小さいカルテや詳細な情報が含まれる資料の場合、スキャン後の画像を確認して、内容がしっかり判別できることを確認してください。スキャナーの性能によっては基準を満たさない場合もあるため、仕様を事前に確認することも大切です。
汎用性が高いフォーマットで保存する
電子化したデータは、誰でも閲覧や共有がしやすい形式で保存しましょう。多くの場合、推奨されるのはPDF形式です。PDF形式は異なる端末やソフトウェアでも互換性が高く、長期間の保存にも適しています。
データの圧縮方法にも注意が必要です。例えば、非可逆圧縮(データの一部を削除する圧縮方法)を使うと、画質が低下してしまう可能性があります。医用画像など特殊な資料を扱う場合には、DICOM形式のような専門的な保存形式が適切です。
紙カルテを廃棄する際は個人情報の取扱に注意する
紙カルテを電子化したあと、元の紙媒体を廃棄する場合には、個人情報の保護を徹底することが必要です。カルテには患者の診療記録や個人情報が記載されているため、不適切な廃棄方法を取ると情報漏洩のリスクが生じます。
廃棄する際には、シュレッダーで細かく裁断するか、信頼できる廃棄業者に依頼する方法が一般的です。
紙カルテを電子化する際に決めておきたいルール

紙カルテを電子化する際には、操作ルールを明確にしておくことが大切です。電子カルテは、電源の管理やアプリの起動など、紙カルテにはなかった準備が必要になるため、スムーズに進めるための手順を整える必要があります。
電子カルテをどの程度活用するのか、従来の紙メモを併用するのかといった運用方法もあらかじめ決めておきましょう。すべてを電子化するのではなく、必要に応じてクリアファイルなど従来の方法を部分的に残すといった選択肢も検討すると、より柔軟な運用が可能です。
電子カルテに移行すれば「ヒューマンエラーを防止できる」や「情報をリアルタイムに共有できる」といったさまざまなメリットを得られます。業務負担を軽減して効率化を図れることから電子カルテの導入率は高まっており、今後も電子カルテを利用するクリニックは増加すると予想されます。
ただし、停電によって利用できなかったり、一時的に業務の効率が落ちたりといくつかの注意点があるのも事実です。これから移行を目指す場合は電子カルテの特徴を踏まえながら、慎重に進めていきましょう。