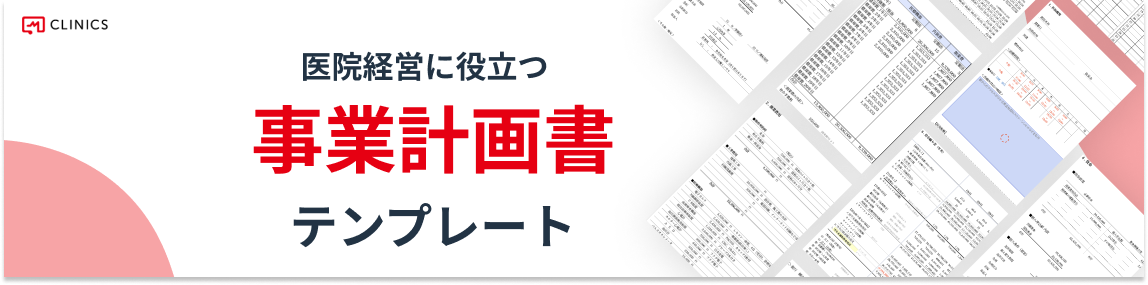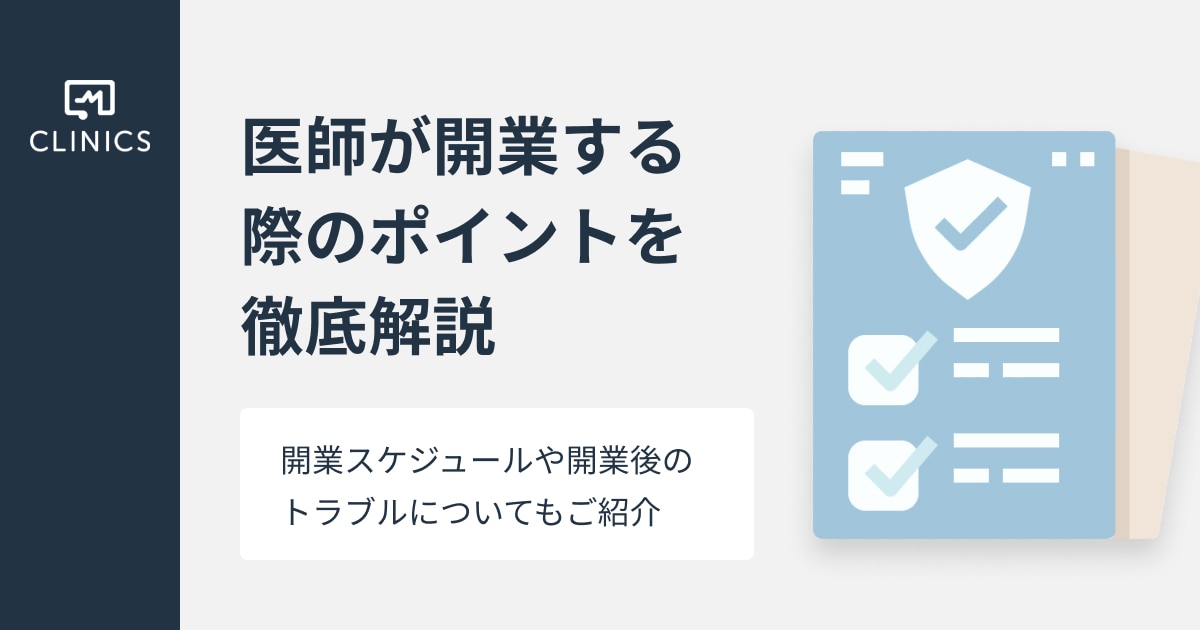
医師が開業する際のポイントを徹底解説|開業スケジュールや開業後のトラブルについてもご紹介
医師が開業するにあたり、開業のコンセプトを明確にしたり経営戦略を練ったりすることが必要です。さらに、開業地選びに失敗しないことも重要でしょう。
この記事では開業地選びの方法や開業資金の調達方法などを詳しく説明していきます。
また、すべてを自分で進めるのが不安な場合は開業をサポートしてくれるコンサルタントを活用することがおすすめです。
目次[非表示]
- 1.医師が開業する際の主なスケジュール
- 2.医師が開業に失敗しないための2つのポイント
- 2.1.1.開業のコンセプトを明確にする
- 2.2.2.綿密な経営戦略を練る
- 3.開業地選びを失敗しないための4つのステップ
- 3.1.1.開業場所形態を明確にする
- 3.2.2.希望の開業地を決める
- 3.3.3.開業物件を探す
- 3.4.4.開業物件が妥当か下見・検討する
- 4.開業資金を調達する際の3つのポイント
- 4.1.1.診療科目ごとの必要資金を把握しておく
- 4.2.2.融資を依頼する金融機関の選定
- 4.3.3.事業計画書の作成
- 5.医師の開業をサポートするコンサルタントの利用がおすすめ
- 6.開業後に起こりがちなトラブル
- 7.まとめ
医師が開業する際の主なスケジュール

医師が開業するためには、まず診療方針を決めて経営基本計画を作成します。基本計画をもとに開業地を決め、銀行と交渉して融資を受けます。そのあと医療機器やそのほかに必要なものを揃えながら、人材を募集しつつ開設手続きを進めていきましょう。
一般的に、これらのプロセスすべてを進めるためには1年間以上必要です。ちなみに、開業地を選ぶだけでも3〜4ヵ月かかることもあります。
医師が開業に失敗しないための2つのポイント

医師が開業に失敗しないためのポイントは、以下の2つです。
- 開業のコンセプトを明確にする
- 綿密な経営戦略を練る
1.開業のコンセプトを明確にする
開業するうえでまず重要なのが、コンセプトを明確にすることです。コンセプトを元に経営基本計画を策定し、開業地を選んだり融資を受けたりする必要があります。
2.綿密な経営戦略を練る
開業するまでにはいくつものステップがあります。そのため、綿密な経営戦略を練ることが重要です。
開業地選びを失敗しないための4つのステップ

開業地選びを失敗しないために次の4つのステップを踏む必要があります。
- 開業場所形態を明確にする
- 希望の開業地を決める
- 開業物件を探す
- 開業物件が妥当か下見・検討する
1.開業場所形態を明確にする
開業地選びを失敗しないためには、開業場所形態を明確にすることが重要です。 クリニックによって医療モールに入居したりビルのテナントに入ったり、また一戸建てで運営したりしていることもあります。それぞれの地域によっても特徴が異なります。首都圏の場合はほとんどがテナントになりますが、郊外の場合は一戸建てもあるでしょう。
2.希望の開業地を決める
開業地選びを失敗しないためには、希望の開業地を決めることが必要です。どのような患者が対象であるか、またどのような治療方法にするかといった点を軸にして開業地を決めていきます。例えば、自宅から近くを選ぶと移動時間が短縮できます。また、周辺に同じ開業エリアが少ないことも開業地を決める目安の1つになるでしょう。
3.開業物件を探す
開業地選びを失敗しないために、開業物件を探しましょう。物件探しは不動産を通すほかに開業コンサルタントに依頼する方法があります。
4.開業物件が妥当か下見・検討する
開業地選びを失敗しないためには、開業物件が妥当か下見・検討することが必要です。チェックしたいポイントとして、そのエリアの人口や人の動き、アクセス、競合となるクリニックの数が挙げられます。開業するエリアの人口や人の動きは来院患者数に直結します。
また、人口だけではなく年齢層についても把握しておくことが重要です。厚生労働省が受療率を発表しているのですが、ある特定の疾病治療のために通院や往診、入院などをした人口に対する割合を示した数値です。そのため、ある程度1日の来院数を予測できるのです。
さらに、クリニックに行くまでのアクセスも重要です。アクセスがよければ良いほど患者は通いやすいでしょう。しかし、アクセスが良い場所は競合となる病院やクリニックが多くあり、必ずしも来院数につながるとは限りません。
開業資金を調達する際の3つのポイント
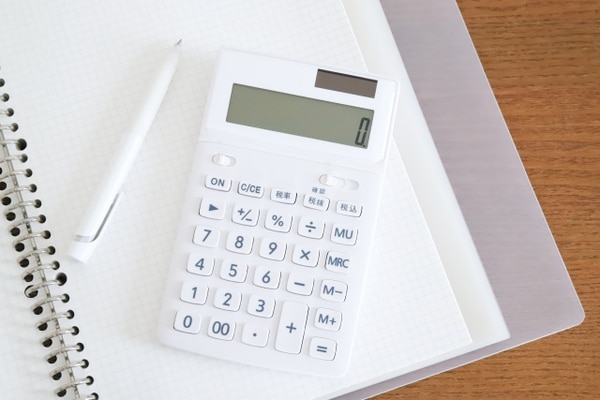
開業資金を調達する際のポイントは、以下の3つです。
- 診療科目ごとの必要資金を把握しておく
- 融資を依頼する金融機関の選定
- 事業計画書の作成
1.診療科目ごとの必要資金を把握しておく
開業資金を調達する際、診療科目ごとに必要な資金を把握しておくことが重要です。クリニックを開業する場合、建物や内装以外に医療機器が必要です。両方で5,000万円以上必要であり、安定した来院患者数を確保するまで2年かかるといわれています。また、運転資金は2,000万円ほど用意するとよいでしょう。
2.融資を依頼する金融機関の選定
開業資金を調達する際、融資を依頼する金融機関を選定することが重要です。開業する場合は融資を受けることがほとんどでしょう。そのため、どの金融機関に依頼をするか、慎重に選定する必要があります。メガバンクから政府系金融機関、地方銀行などさまざまな種類の金融機関があり、計画に対して納得してもらうことが重要です。
3.事業計画書の作成
開業資金を調達する際は、事業計画書を作成することが重要です。事業計画書には、診療方針や経営基本計画の策定などを記載し、対象となる患者や提供する医療内容を明確にすることが大切です。決して難しいものではなく、開業したい理由やどのような診療をしたいのかを掘り下げることで、明確に作成できるでしょう。
医師の開業をサポートするコンサルタントの利用がおすすめ

医師が開業するためには、必要な書類を揃えたり、具体的に考えたりすることが多くあります。一人ですべてをこなすには時間と労力が必要です。そんなときはトラブルの対応などを含めた経験やノウハウが豊富なコンサルタントを利用することをおすすめします。トラブル対応などは任せておいて、運営に集中することが可能です。
開業後に起こりがちなトラブル

開業をしたあとによくありがちなトラブルとして、人間関係と金銭的な面が挙げられます。まず、大きな心配事として挙げられるのが思った以上に患者が来院せず、資金繰りに苦労する点です。しかし、一般的に軌道にのるまでに1〜2年ほどかかるといわれています。そのため、はじめから2年をスパンで集客を考え、十分な運転資金を準備することが重要です。
次に挙げられるのが、スタッフとの間でのトラブル、またスタッフ同士で問題を起こすこともあるでしょう。少人数で運営していくため、日頃から十分なコミュニケーションをとることが重要です。また、労使関係に関しては社会保険労務士に初めから依頼するなど、明確にしておくべきです。
このほかにも、予約や入金などシステム面においてのトラブルも考えられるでしょう。
まとめ

医師が開業するためには、開業する場所や物件の選択、トラブルの対応、集客などさまざまなことが必要です。一般的にクリニック運営が軌道に乗るまで2年はかかるといわれているため、十分な経営資金を準備することが重要です。
また、トラブルを少しでも減らすため、医師の開業をサポートするコンサルタントに依頼することをおすすめします。サポート会社に依頼することで、すべて自分で対応する必要がなくなったり、必要なアドバイスをもらったりできるのです。