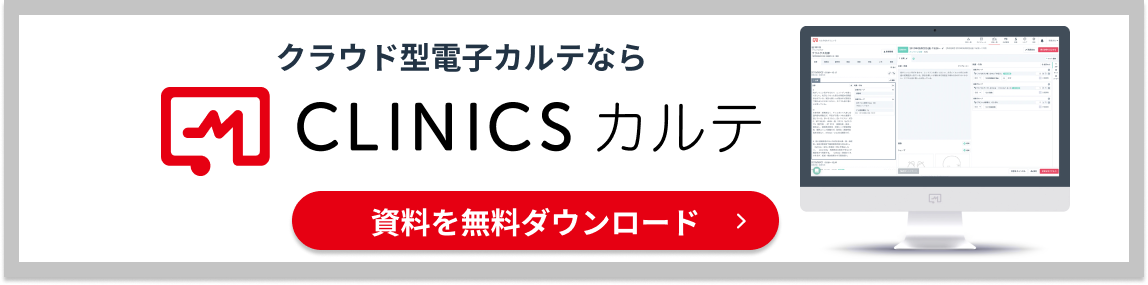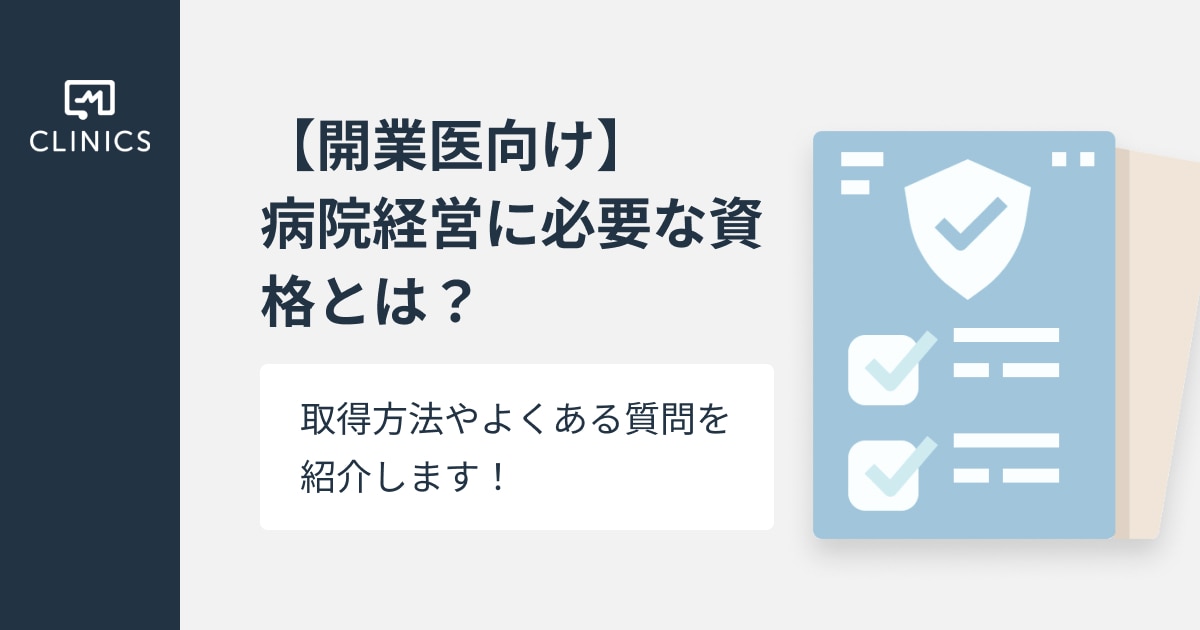
【開業医向け】病院経営に必要な資格とは?取得方法やよくある質問を紹介します!
勤務医として長く経験を積んだ医師の場合、開業を考えている医師も多いでしょう。開業医として開院する場合、医療の技術だけではなく経営の知識も持っておく必要があります。
当記事では、開業医についての解説をはじめ、必要な資格や資金について解説していきます。
目次[非表示]
- 1.開業医とは?
- 2.開業の際によくある5つの質問
- 2.1.1.病院経営に必須な資格とは?
- 2.2.2.準備しておくべき自己資金とは?
- 2.3.3.銀行借入はできる?
- 2.4.4.開業場所の選び方とは?
- 2.5.5.都市部で開業する際の注意すべき点とは?
- 3.病院経営に役立つ4つの資格と取得方法
- 3.1.1.病院経営管理士
- 3.1.1.病院経営管理士の取得方法
- 3.2.2.医療経営コンサルタント
- 3.2.1.医療経営コンサルタントの取得方法
- 3.3.3.防火管理者
- 3.3.1.防火管理者の取得方法
- 3.4.4.医療経営士
- 3.4.1.医療経営士の取得方法
- 4.経営者という意識を持つことが大切
- 5.まとめ
開業医とは?

開業医とは、個人で病院やクリニックを経営する医師のことをいいます。主に、地域の住民を診療するクリニックとして開業するケースが多い傾向です。
開業医として活躍したい場合「内科」「外科」はもちろん、その他の診療科まで、広範囲な初期治療の対応が求められます。
また、患者や従業員との信頼関係が経営成功のカギとなるため、コミュニケーション能力や人柄も重要です。
勤務医の違い
勤務医とは、大学や病院といった組織に雇用されている医師のことをいいます。開業医は経営者、勤務医は正社員と解釈すればわかりやすいかもしれません。
勤務医は給与所得者となるため、患者数や経営状況に影響されることなく、安定した収入を得ることができるメリットがあります。
開業医の主な業務
開業医の主な業務は以下の10個です。
- 診療
- スタッフの採用・育成・教育
- スタッフの勤怠管理
- 集患対策(マーケティング)
- 診療方針の策定
- 経営
- 経理
- 医薬品の購入
- 医療機器の導入
- 患者とのコミュニケーション
上記のとおり、開業医は診察からスタッフの採用や育成、集患対策といったマーケティングまで病院運営に関わる一切の業務を行わなければなりません。
また、医薬品や医療機器の導入などを行います。再来率をアップさせるためにも、患者とのコミュニケーションも大切にしてください。
開業医の平均年収
2017年6月に厚生労働省が公開した「医療経済実態調査報告」によると、開業医の平均年収は約2,748万円でした。
しかし、この金額から治療や経営に関わるコスト、つまり経費を差し引かなければならないため、2,748万円がすべて手元に入るわけではありません。
勤務医の給与とは性質が全く異なるため、開業する前にどれくらいの経費が発生するのかシミュレーションすることが大切です。
開業の際によくある5つの質問

開業の際によくある質問として、次の5つが挙げられます。
- 病院経営に必須な資格とは?
- 準備しておくべき自己資金とは?
- 銀行借入はできる?
- 開業場所の選び方とは?
- 都市部で開業する際の注意すべき点とは?
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.病院経営に必須な資格とは?
医師免許を有していることを前提に置けば、病院経営に必須な資格はありません。また、年齢条件もないため、医師としての経験が少ない場合でも、資金があれば開業は可能です。
2.準備しておくべき自己資金とは?
どの診療科目で開業するかにもよりますが、内科として開業を検討している場合、自己資金として1,000万円以上は準備しておいた方がよいでしょう。
ただし、自己資金が少ないからといって開業できないわけではありません。
家賃や人件費といった月々かかる固定費や開業時の内装費、医療機器など、どれくらいコストがかかるのかを把握し、無理のない事業計画書を策定すれば十分開業可能です。
自己資金は少ないけれど、借入に不安がある場合、開業コンサルタントに相談するのも1つの手段です。
3.銀行借入はできる?
地方銀行は無担保や保証人なしで医院開業の借入れを行っているケースが多いようです。
また、大手都市銀行でも医院開業向けに低金利かつ借入期間も長期で提示してくれる場合がほとんどだといわれています。
以上の点から、比較的有利な条件で銀行借入が可能なものの、返済計画が曖昧であれば当然、借入は難しくなります。
したがって、開業に向けた動機がしっかりしている趣意書と無理のない返済計画を踏まえた事業計画書を策定することが大切です。
4.開業場所の選び方とは?
開業場所は、以下のようにさまざまな要素を踏まえて選ぶことが必要です。
- 戸建かビルか
- 建て貸しの不動産か
- 診療科目はどうするか
- どの地域か
広ければその分コストは高くなり、狭ければ売り上げに影響が出てしまう可能性があります。
また、ビルの一部を借りる際「レントゲンを設置する場合、電気容量は足りるか」や「シンクやお手洗いといった排水設備を作るために、床下に十分なスペースがあるか」といった点も考慮しなければなりません。
しかし、不動産業者やネットの情報だけでは、このような細かい情報はチェックできないため、開業コンサルタントや医療専門の設計会社に依頼し、確認してもらうことをおすすめします。
5.都市部で開業する際の注意すべき点とは?
都市部はすでに開業している、もしくは開業を望んでいる医師が多い「激戦地区」です。
だからといって、都市部で開業が無理というわけではありませんが、都市部での開業は難しいというのが現状です。
事実、診療所激戦区だった世田谷区では、赤字経営の診療所が増えて、閉院数が開院数を上回っています。
都市部で開業する際は、どのような医療サービスを提供するのかコンセプトを決めて、コンセプトに沿った医療を提供し、なおかつ「経営力」を発揮できる場所かどうか慎重に判断することが重要です。
病院経営に役立つ4つの資格と取得方法

病院経営に役立つ資格は以下の4つです。
- 病院経営管理士
- 医療経営コンサルタント
- 防火管理者
- 医療経営士
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.病院経営管理士
病院経営管理士とは、一般社団法人日本医師会の認定資格です。
病院経営にかかわる全職種を対象としており、医療関連や経営管理関連の科目、経営管理演習といった幅広いカリキュラムとなっています。
病院経営管理士の取得方法
一般社団法人日本病院会の「病院経営管理士通信教育」を2年間受講し、以下の5つのカリキュラム内にある全39科目を修了すると、病院経営管理士を取得できます。
- 医療関連科目
- 経営管理科目
- 経営管理演習
- 特別講座
- 卒業論文
参考:病院経営管理士通信教育
2.医療経営コンサルタント
医療経営コンサルタントとは、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定している、クリニックや病院といった医療・介護施設向けの経営コンサルタントの資格です。
資格取得後も継続研修が義務付けられているため、資質と能力の向上を図ることができます。そのため、勤務医や開業医で取得者が増えている資格です。
医業経営コンサルタント協会が行っている「一般公開 医業経営実務講座」は医療機関勤務の事務・看護・コメディカル部門の方を、「医業経営管理能力検定」は大学生を対象としています。
医療経営コンサルタントの取得方法
医療経営コンサルタントの取得ステップは次のとおりです。
- 協会主催の指定講座を受講する
- 一次試験(筆記試験)を受ける
- 二次試験(論文審査)を受ける
- 協会の正会員になる
3.防火管理者
消防法に基づき、入居するテナントビルの収容人数が30人以上である場合、防火管理者を選任しなければなりません。
そのため開業する前に、所轄の消防署に防火管理者選任届や、消防計画書といった届け出が必要です。
防火管理者は施設管理者として必須の資格となります。防火管理者はスタッフでも問題ありません。
しかし、スタッフは退職する可能性があるため、開業前に医師が防火管理者の資格を取得することをおすすめします。
防火管理者の取得方法
防火管理者の取得方法は、一般社団法人日本防火・防災協会が実施する「防火管理者講習」を受講します。講習の内容は次の3種類です。
- 甲種防火管理新規講習
- 乙種防火管理講習
- 甲種防火管理再講習
講習修了後「効果測定」に合格すれば、取得できます。
参考:防火・防災管理講習
4.医療経営士
医療経営士は、一般社団法人日本医療経営実践協会が実施している試験制度です。
医療経営士の資格は、3級から1級までの3等級に分かれており、3級は医療や医療経営の基本レベル、1級は経営幹部として意思決定できるレベルとなっています。
医療経営士の取得方法
2・3級はマークシート形式です。3級は誰でも受験可能、2級は3級合格者かつ日本医療経営実践協会に正会員登録している方が受験できます。
1級の受験条件は2級合格者かつ医療経営士2級正会員の登録者です。試験内容も記述式の第一次試験合格後、口頭試問と個人面接の第二次試験に合格しなければなりません。
経営者という意識を持つことが大切

勤務医であれば診察・診療だけ行っていれば問題ありませんでした。
しかし開業医は、スタッフの採用や育成、勤怠管理、マーケティングなど病院経営に関わる幅広い業務をこなさなければなりません。
そのため開業医になる場合は、会社員から経営者になるという意識を持つことが大切です。
まとめ

当記事では「開業医と勤務医の違い」や「病院を経営するために役立つ資格」を解説しました。
開業医は、勤務医に比べ平均収入は多いですが、売上から治療や経営にかかるコストを自己負担しなければならないほか、業務の量が大幅に増加します。
したがって開業する前に、信頼できるパートナーに相談したり、どれくらいコストの負担があるのかシミュレーションしたりすることが大切です。