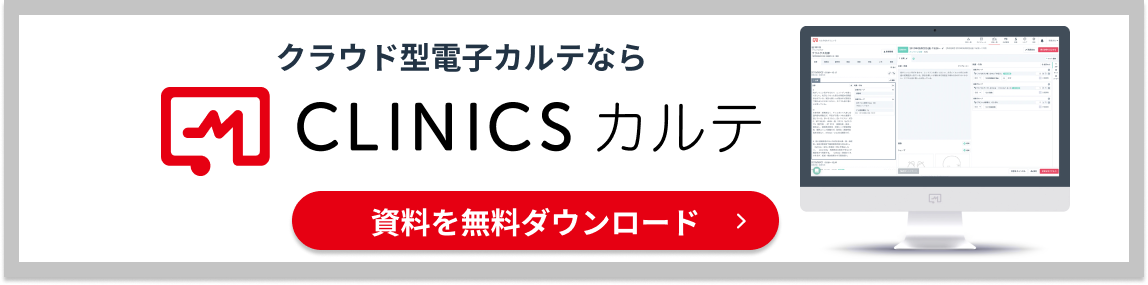電子カルテの音声入力で効率アップ!メリットやおすすめシステムを解説
当記事では、医療現場における音声入力の現状と導入する場合の注意点、おすすめの音声入力システムについて解説します。
目次[非表示]
- 1.電子カルテについて
- 1.1.電子カルテのメリット
- 1.2.電子カルテのデメリット
- 2.医療現場での音声入力について
- 3.電子カルテ入力で音声入力を導入する注意点
- 4.医療クラークと音声入力どちらがよいのか?
- 5.おすすめの音声入力システム5選
- 5.1.1.medimo
- 5.2.2.メルプVOICE
- 5.3.3.コエカルテ
- 5.4.4.AmiVoice
- 5.5.5.kanaVo
- 6.まとめ
電子カルテについて

「電子カルテ」は、患者の診療内容や処方薬といった治療における経過を紙ではなく、パソコンやタブレッドを用いて作成し、電子データとして保存したものです。
紙カルテを使用している医療機関はまだまだ多いのが現状ですが、利便性の良さや保存のしやすさといった観点から電子カルテの普及率も年々高まっています。
電子カルテのメリット
電子カルテのメリットは、主に以下の3点です。
- カルテの管理スペースを削減できる
- 窓口業務の負担が減る
- 医療DXを推進できる
電子カルテにすればカルテのデータをサーバーに保存できます。紙カルテのように管理スペースを確保する必要がありません。
また、電子カルテの検索機能を活用すれば、患者のカルテをすぐに見つけられます。紙カルテのように収納棚から目視で探す必要がなくなるため、窓口業務の負担を軽減できるでしょう。
連携可能なシステムであれば、電子カルテを基点に予約管理や問診票、自動精算機といったさまざまなシステムと連携できるため、医療DXを推進できます。医療DXが推進されれば、病院の部署全体で情報共有できるため、業務の効率化や負担軽減につなげることができるでしょう。
電子カルテのデメリット
電子カルテのデメリットは、主に以下の3つです。
- 災害時に弱い
- セキュリティの問題
- パソコン操作が苦手
電子カルテは主にパソコンで操作するため、災害によって停電が起きると使用できなくなります。したがって、災害時に備えて補助電源を用意しておいたり紙カルテを準備しておいたりといった対策が必要です。
また、セキュリティ対策が甘いと不正ログインやサイバー攻撃によって、患者の個人情報が漏えいする恐れがあります。アクセスログや二段階認証、セキュリティソフトの導入といったセキュリティ対策が欠かせません。
医療スタッフの中には、パソコン操作が苦手な人もいるでしょう。パソコン操作に気を取られてしまい、患者の話に集中できないといったデメリットが生じます。
ただし近年は、タッチペン操作によって入力できる手書き入力や、会話を読み取って入力してくれる音声入力が可能な電子カルテも登場しています。パソコン操作が苦手という方は、こういった電子カルテの導入を検討するといいでしょう。
医療現場での音声入力について

医療現場での音声入力の実情について、ここでは以下の2項目に分けて紹介します。
- 医療現場での音声入力の現状
- 医療現場における音声入力の活用シーン
それぞれ詳しくみていきましょう。
医療現場での音声入力の現状
医療現場において音声入力の使用頻度が最も多い診療科は「放射線科」です。放射線科では放射線読影レポートの入力において、音声入力が活用されています。
医療現場における音声入力の活用シーンは幅広くなってきている
医療現場における音声入力は、一般的に放射線科で使用されていますが、技術革新によって、音声認識精度が驚異的に向上しています。その精度は音声入力ソフトで原稿を作成し、必要な部分を後から修正すれば済むレベルです。
音声認識精度のレベルが向上したことで「音声入力で電子カルテを書く」「在宅医療の移動中にカルテ入力する」というように、音声入力の活用シーンは幅広くなってきています。
電子カルテ入力で音声入力を導入する注意点

電子カルテ入力で音声入力を導入する際の注意点は、以下の2つです。
- 日常会話のスピードだと認識率が低下する
- 会話の聞き分けができない
技術革新によって音声認識精度が向上している音声入力ですが、認識率が高いのは丁寧に会話している場合です。日常会話のスピードがはやかったり早口で不明瞭な話し方であったりすると、認識精度が落ちる可能性があります。
また現在の技術では医師と患者が会話している時に、どちらが発した言葉なのか音声入力では聞き分けられません。したがって、医師と患者、どちらの会話も拾おうとしている場合もあるため、注意が必要です。
医療クラークと音声入力どちらがよいのか?

医療クラークとは、医師が行う事務作業をサポートするスタッフのことです。主な業務は電子カルテ入力や各種書類作成の代行、オーダー補助といったものですが、クリニックごとに担っている業務は異なります。
医療クラークの業務が電子カルテの入力代行のみであれば、当然音声入力の方が低コストです。しかし、医療クラークの業務は幅広いため、さまざまな業務を担ってくれるという観点でいえば、医療クラークの費用対効果は非常に高いといえるでしょう。
特に長年勤務しているベテランの医療クラークであれば、医師の求めていることを素早く理解できたり各方面との連携をそつなくこなしたりと先回りした行動ができるため、医師の右腕と言っても過言ではありません。
両者ともメリット・デメリットがあるため、どちらがよいのか慎重に検討する必要があります。
おすすめの音声入力システム5選
おすすめの音声入力システムには、以下の5つがあります。
サービス名 |
提供企業 |
|
|---|---|---|
1 |
medimo |
株式会社Pleap |
2 |
メルプVOICE |
株式会社flixy |
3 |
コエカルテ |
Ubie株式会社 |
4 |
AmiVoice |
株式会社アドバンスト・メディア |
5 |
kanaVo |
kanata株式会社 |
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.medimo

medimoは、音声認識とAIを活用して、診察の音声からカルテを自動で作成するシステムです。医師と患者が話す内容をリアルタイムで正確にテキスト化し、カルテ原稿を自動生成します。これにより、医師の記録作業が大幅に軽減され、診療時間の効率化と患者ケアの質向上を実現します。
カルテの記載方法はSOAPをはじめとして、自由にカスタマイズ可能です。基幹病院の導入実績もあり、セキュリティ対策も万全。医療特化の高精度な音声認識と直感的なインターフェースで、日々の業務をスマートにサポートします。
参考:medimo
2.メルプVOICE

「メルプVOICE」は、株式会社flixyが提供しているメルプWEB問診の音声入力機能です。Apple Storeから「メルプカルテ」をダウンロードしましょう。ログインした後「Voice」タブを選択、右下のマイクアイコンをクリックして音声入力を行います。
入力した音声が文字変換されるため、誤字があれば修正し、表示された文章を電子カルテに飛ばす仕組みです。メルプVOICEはメルプWeb問診の音声入力機能であるため、メルプVOICEを使用したい場合はメルプWEB問診を導入する必要があります。
参考:メルプ VOICE
3.コエカルテ
 「コエカルテ」は、Ubie株式会社が提供している音声入力システムです。医療分野のIC専門用語を活用することで、症状説明の文字起こし精度を高めてくれるほか、症状や服薬歴といった情報をAIの音声認識によって、自動で医療用語に翻訳しカルテ化してくれます。
「コエカルテ」は、Ubie株式会社が提供している音声入力システムです。医療分野のIC専門用語を活用することで、症状説明の文字起こし精度を高めてくれるほか、症状や服薬歴といった情報をAIの音声認識によって、自動で医療用語に翻訳しカルテ化してくれます。
現在、スマホ版の開発が行われており、実装されればスマホでコエカルテの利用が可能です。病棟回診でパソコンの持ち運びが大変な場合は、利用を検討してみるとよいでしょう。
4.AmiVoice

「AmiVoice」は医療現場で古くから使用されてきた音声入力システムで、株式会社アドバンスト・メディアが提供しています。音声認識技術は世界トップレベルの評価を得ており、国内シェア1位を誇っているシステムです。
音声入力といっても、医療現場のシーンごとにさまざまなシステムが用意されています。代表的なシステムは主に以下の4つです。
- AmiVoice SBx Medical:医療や調剤薬局、介護向けシステム
- AmiVoiceIC-Support:電話やオンラインといったさまざまな診療スタイルに対応したシステム
- miVoice OAM:対面診療やオンライン診療向けのクラウド型システム
- AmiVoiceCLx:マイクに話しかけて文章を作成するクラウド向けのシステム
それぞれのシーンに適したシステムを選ぶことで、電子カルテ入力の負担を減らせるでしょう。
参考:音声認識システム:AmiVoice | SCSK株式会社
5.kanaVo
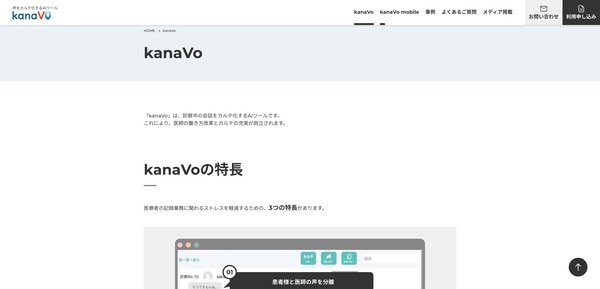
「kanaVo」はkanata株式会社が提供している音声入力システムです。診療中の会話をカルテ化するAIツールとも呼ばれ、患者と医師の声を分離するといった特徴があります。
各診察で記録された内容が一覧で表示されるため、記録の出だしや日時を頼りに診察内容の詳細画面に遷移し、記録の振り返りが可能です。また、汎用性が高いため「診察」「オンライン診療」「処置前説明」といった幅広いシーンで活用できます。
参考:kanaVo
まとめ

医療DXや医療ICTの促進に電子カルテは欠かせません。しかし、パソコンが苦手な医師の場合、操作に気を取られてしまうため、患者とのコミュニケーションが取りづらくなるといったデメリットがあります。
音声入力機能を使えば、医師の会話がそのまま文字として電子カルテに入力されるため、パソコン操作に気をとられる心配がありません。
したがって、電子カルテの導入を検討しているものの、操作が苦手で正しく入力できるか不安な方は、音声入力システムを使用できる電子カルテを導入してみましょう。